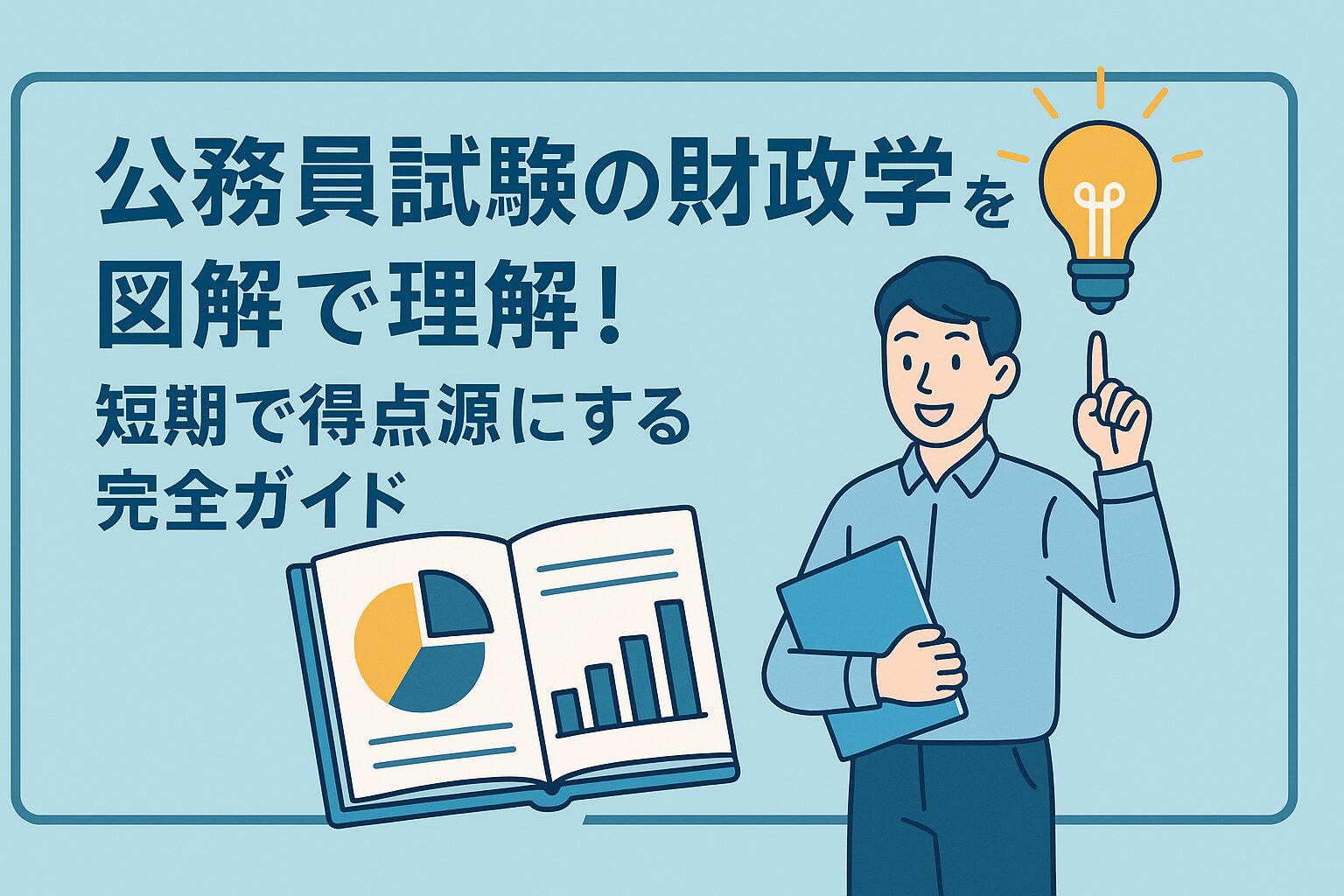第1章|マクロ経済学は公務員試験の「得点源」になる専門科目
この章では、公務員試験の専門科目のひとつであるマクロ経済学が、なぜ「合否を左右する得点源」と言われるのかをわかりやすく紹介します。
「経済は数字ばかりで苦手…」「ニュースは難しそうでスルーしてしまう」という方でも、まずはマクロ経済学の特徴・落とし穴・勉強するメリットをざっくりつかんでおきましょう。
・マクロ経済学がどんな専門科目かがイメージできる
・なぜ公務員試験で得点源になりやすいかが分かる
・このあとどんな順番で勉強すればよいか、道しるべができる
- 出題区分:多くの試験で専門科目(経済系)として出題
- レベル感:大学の教養レベル〜経済学部1〜2年生レベル
- 扱うテーマ:GDP・物価・失業・景気・財政・金融政策など
1-1|マクロ経済学はどんな専門科目?(ミクロとの違い)
マクロ経済学は、かんたんに言うと「国全体の経済をまとめて見る科目」です。
- 日本の経済成長率はどれくらいか?
- 物価が上がるとき、経済では何が起きているのか?
- 失業率が高くなるとき、どんな政策が必要なのか?
こうしたニュースでよく見るキーワードを、グラフや式を使いながら整理していくのがマクロ経済学です。
同じ経済学でも、ミクロ経済学が「個々の市場や企業・消費者」に注目するのに対して、マクロ経済学は「国全体」「経済全体」に注目している点が大きな違いです。
・ミクロ経済学:お店の売上や、1人の消費者の行動に注目する
・マクロ経済学:日本という1つの国の「家計簿」や「健康状態」をチェックするイメージです。
1-2|マクロ経済学が公務員試験で得点源になりやすい3つの理由
「経済系の科目は難しそう」と感じる受験生が多い中で、マクロ経済学はしっかり対策すれば点数を伸ばしやすい専門科目です。その理由を3つに分けて見ていきましょう。
-
出題テーマがある程度決まっている
マクロ経済学では、GDP・失業・物価・IS–LM・AD–AS・財政・金融政策といった定番分野からの出題が中心です。
→ 過去問とテキストをきちんと回せば、「見たことがあるパターン」の問題が多くなり、安定して得点しやすくなります。 -
グラフの型が少なく、慣れれば読みやすい
ミクロ経済のような細かい市場ごとのグラフと比べると、マクロ経済のグラフは「全体の動き」をざっくり捉えるものが中心です。
→ 例えば、AS–ADやIS–LMなど、よく出るグラフの種類が限られているので、慣れてしまえば一気に読みやすくなります。 -
暗記だけでなく「ストーリー」で理解しやすい
「景気が悪化すると失業率が上がる」「金融緩和で金利が下がる」など、ニュースで見たことがある知識とつながりやすい分野です。
→ グラフや式の裏にあるストーリーを押さえることで、丸暗記よりもラクに点が取れるようになります。
マクロ経済学は、「難しそう」に見えますが、出るところが絞りやすく、理解型の科目なので、対策次第で大きな得点源になります。
1-3|マクロ経済学で受験生がつまずきやすい3つの落とし穴
得点源にしやすい一方で、マクロ経済学にはよくあるつまずきポイントもあります。先に把握しておくことで、ムダな遠回りを防ぎましょう。
-
指標の意味が曖昧なまま先に進んでしまう
「実質GDP・名目GDP」「失業率」「インフレ率」などの用語を、なんとなくのイメージで覚えてしまうケースです。
→ 結果として、グラフや計算の問題で数字の意味が分からず詰まってしまうことに。 -
IS–LMやAD–ASを“線の形”だけ覚えている
「ISは右下がり、LMは右上がり」「ADは右下がり、ASは右上がり」とだけ覚えてしまい、
「なぜそう動くのか」が分からない状態になっているパターンです。 -
政策効果の方向がごちゃごちゃになる
財政政策・金融政策がそれぞれ、利子率・投資・所得・物価にどう効いてくるのかを整理できていないと、
選択肢問題でプラスとマイナスが逆になりやすくなります。
・まずは「用語の日本語訳」から押さえる(例:GDP=国の「ものさし」)
・グラフは「線」ではなく「ストーリー」として覚える
・政策の影響は、「金利 → 投資 → 所得 → 物価」のように流れで理解する
1-4|この記事(全体)を読むメリット
この記事では、マクロ経済学を 「地図」→「頻出テーマ」→「事例問題」→「ミスと対策」 の流れで整理していきます。
- マクロ経済学の全体像が図解付きでつかめる
- 公務員試験でどのテーマがよく出るかがわかる
- NG→OKの比較で、自分がハマりやすいポイントを事前に防げる
さらに、第6章ではスタディング公務員講座を使って、マクロ経済学を最短ルートで得点源にする方法も紹介します。
「独学だけだと不安」「時間をかけずに専門科目を固めたい」という方は、そこまで読むことで自分に合った勉強法のイメージが持てるはずです。
- ニュースで聞いたことがある言葉が出てきたら、「あの話か!」と結びつける
- グラフを見るたびに、「横軸・縦軸・動きの意味」を声に出して確認する
- 式や用語は、日本語1行で説明できるかをチェックする
それでは次の第2章から、マクロ経済学の全体像を図解(マクロ経済マップ)で整理していきましょう。
第2章|マクロ経済学の全体像を図解で理解する(地図化)
マクロ経済学は、「国全体の経済の動き」を扱うためテーマが広く見えますが、実は4つの大ブロックでシンプルに整理できます。まずは、マクロ経済を“地図”として頭に入れましょう。
2-1|マクロ経済の4大テーマをざっくり整理
公務員試験で出題されるマクロ経済は、次の4ブロックが中心です。
マクロの土台となる指標です。これが分からないと、後半の政策や分析が理解できません。
- 名目GDPと実質GDP(経済の“ものさし”)
- インフレ率・デフレ率
- 失業率・就業者数
財市場(IS)と貨幣市場(LM)が交わることで、利子率と国民所得が決まるという人気分野です。
- IS曲線:財市場の均衡
- LM曲線:貨幣市場の均衡
- 財政政策・金融政策の分析に直結
国の景気を良くしたり引き締めたりする政策分野。試験でも頻出です。
- 政府支出・減税(財政政策)
- 金利引下げ・量的緩和(金融政策)
- 景気刺激→物価や失業率の変化
総需要(AD)と総供給(AS)によって、物価・産出量の変化を読み取ります。
- インフレ・デフレの分析
- 短期ASと長期ASの違い
- 政策効果を「経済全体」で見る
2-2|この4ブロックを“つなげて理解”するのが合格のコツ
マクロ経済学は単元がバラバラに見えますが、実はすべてがつながっています。
・GDPや物価などの指標を理解する →
・IS–LMで市場の動きを理解する →
・政策がどんな影響を与えるか政策効果を知る →
・最終的にAD–ASで経済全体の変化を読む
この「つながり」を意識して学ぶことで、暗記に頼らず得点が安定する理解型の勉強ができるようになります。
上記4つのブロックの中から、公務員試験で特に出題率の高い5テーマをピックアップし、図解付きで解説します。
第3章|公務員試験でよく出るマクロ経済学の頻出テーマ5つ
ここからは、公務員試験の専門科目「マクロ経済学」で特に出題頻度が高い5つのテーマを、図解とミニ解説で整理していきます。
第2章で見たマクロ経済の「4大ブロック」の中から、過去問で何度も登場する鉄板分野だけをピックアップしました。
① GDPと国民所得(三面等価の原則)
② 景気と失業率(オークンの法則)
③ 物価とインフレ率(フィリップス曲線)
④ IS–LMモデル(財市場・貨幣市場の同時均衡)
⑤ AD–ASモデル(物価と産出量の変動)
3-1|GDPと国民所得:マクロの“ものさし”を理解する
マクロ経済学のスタートはGDP(国内総生産)と国民所得です。これが分からないと、景気が良い・悪いの意味があいまいなままになってしまいます。
- 名目GDP:その年の名目価格で計測したGDP
- 実質GDP:物価変動の影響を取り除いた、「量」に注目したGDP
- 三面等価の原則:生産=分配=支出の3つの面から見てもGDPは同じになる
・名目GDPと実質GDPを混同しない
・「経済成長率=実質GDPの伸び」とセットで覚える
・三面等価の原則は文章問題でも狙われやすいので要チェックです。
3-2|景気と失業率:オークンの法則で「悪化すると失業増」のイメージをつかむ
景気が悪くなると失業率が上がる──この関係を、定量的にとらえたのがオークンの法則です。
- 景気悪化(成長率の低下) → 企業の生産縮小 → 雇用削減 → 失業率の上昇
- オークンの法則は、「成長率の変化」と「失業率の変化」の経験則的な関係
- 細かい係数よりも、景気と失業の逆相関を理解しておくことが重要
3-3|物価とインフレ率:フィリップス曲線で「物価と失業のトレードオフ」を見る
マクロ経済では、物価と失業率の関係もよく問われます。その代表がフィリップス曲線です。
- 短期:失業率とインフレ率にはトレードオフ(逆の関係)がある
- 長期:期待インフレ率の変化などにより、長期フィリップス曲線は垂直と考えるモデルも重要
- 公務員試験では、「短期と長期の違い」が選択肢で狙われやすい
3-4|IS–LMモデル:財市場と貨幣市場の同時均衡
IS–LMモデルは、公務員試験のマクロ経済でほぼ確実に出題されるレベルの重要テーマです。
- IS曲線:財市場の均衡(投資と貯蓄の関係) → 右下がり
- LM曲線:貨幣市場の均衡(貨幣需要と供給) → 右上がり
- 財政政策:IS曲線がシフト/金融政策:LM曲線がシフト
・「どの政策が、どの曲線を、どちらに動かすか」を整理する
・グラフを動かしたあと、新しい均衡点(r, Y)の変化を読み取る練習をしておくと、本番で迷いにくくなります。
3-5|AD–ASモデル:物価と産出量の変動をとらえる
AD–ASモデルは、マクロ経済全体の物価水準と産出量がどのように決まるかを示すモデルで、こちらも頻出です。
- 需要ショック(消費・投資・政府支出の変化) → ADのシフト
- 供給ショック(原材料価格・賃金・生産性の変化) → ASのシフト
- 短期ASと長期ASを区別し、インフレギャップ・デフレギャップを理解する
・マクロ経済学の頻出テーマは、「指標(GDP・失業・物価)」と「モデル(IS–LM・AD–AS)」に集中している
・グラフを暗記するのではなく、「横軸・縦軸・曲線の意味」を日本語で説明できるようにしておくことが重要
・次の第4章では、ここまでの内容を使って実際の事例問題をNG→OK形式で解説し、解き方の流れを身につけていきます。
第4章|よく出る事例問題をNG→OKで攻略する
ここでは、公務員試験の専門科目「マクロ経済学」でつまずきやすい典型パターンを、NG解答→OK解答の順に比較しながら解説していきます。
実際の本試験をイメージしやすいように、簡略版の事例+図解で「どこで間違えやすいか」をハッキリさせていきましょう。
事例①:名目GDPと実質GDPを取り違えるミス
事例②:LM曲線の動きを勘違いするミス
事例③:AD–ASでインフレの読み方を誤るミス
4-1|事例①:名目GDPと実質GDPを「物価」とごっちゃにする
まずは、マクロ経済学の入口となる名目GDPと実質GDPの典型的な誤解から見ていきます。
ある年の名目GDPが前年比で10%増加し、物価水準も同じく10%上昇した。このとき、実質GDPの変化として正しいものを選べ。
名目GDPと実質GDPの違いを意識せず、「GDPが増えた=実質も増えた」と短絡的に考えてしまうパターンです。
- 物価の上昇分を取り除いていない
- 「実質=現実」とイメージし、「名目=実質」と思い込んでしまう
実質GDPは、名目GDPから物価の変化分を取り除いたものです。
- 名目GDP:+10%
- 物価:+10%
- 実質GDPのおおまかな変化率 ≒ 名目GDPの変化率 − 物価上昇率
よって、10% − 10% = 0% となり、実質GDPは変化しないと判断するのが正解です。
・「実質=量」「名目=値段込み」と言い換えて覚える
・成長率の問題が出たら、まず物価の動きを確認するクセをつけましょう。
4-2|事例②:LM曲線のシフト方向を逆に考えてしまう
次は、IS–LMモデルの中でも貨幣市場(LM曲線)に関する典型的なミスです。
中央銀行が公開市場操作によってマネーサプライを増加させた。このとき、LM曲線はどのようにシフトし、利子率・国民所得はどう変化するか。
「景気がよくなる=右上に動く」とざっくり考えてしまい、シフト方向を感覚で決めてしまうパターンです。
- LM曲線がどんな条件のグラフかを意識していない
- 「マネーサプライ増加 → LM左シフト」と逆に覚えてしまう
LM曲線は、貨幣需要=貨幣供給が成り立つ点の集まりです。マネーサプライ(貨幣供給)が増えると、同じ所得Yでも利子率が低くてよくなるため、 LM曲線は右下にシフトします。
- マネーサプライ増加 → LM曲線が右下(外側)へシフト
- 新しい均衡点では、利子率rは低下、国民所得Yは増加
つまり、正解は「LM曲線は右下にシフトし、利子率が下がって国民所得が増える」となります。
・LM:貨幣市場のグラフであることを常に意識する
・マネーサプライの増減は、「LMをどちらに動かすか」から考えるとミスが減ります。
4-3|事例③:AD–ASでインフレ時の物価・産出量を誤読してしまう
最後は、AD–ASモデルでよくある「インフレの読み違い」の事例です。
好況により民間消費・投資が増え、総需要ADが右にシフトした。このとき、物価水準と産出量はどう変化するか。
「インフレ=物価だけが上がる」ととらえてしまい、産出量Yの変化を見落としてしまうパターンです。
- ADとASの交点の移動として考えていない
- 物価Pばかりに注目し、Yの変化を読み忘れる
需要ショックでADが右にシフトすると、ADとASの交点が右上方向に動きます。
- 物価P:上昇(インフレ)
- 産出量Y:増加
よって、需要インフレの場合には「物価も産出量も増える」というのが基本パターンになります。
なお、供給ショック(原材料高騰など)によるインフレでは、物価↑・産出量↓というパターンもあり、ここを区別できるかどうかが得点の分かれ目です。
・AD–ASの問題は、必ず「交点の移動」として図で考える
・インフレの原因が「需要側」か「供給側」かで、Yの動きが変わることを意識しましょう。
・マクロ経済学の事例問題は、「なんとなくのイメージ」だけで解こうとするとNGパターンにハマりやすい
・名目GDP/実質GDP、LM曲線のシフト、AD–ASでのインフレの読み方は、いずれも頻出の落とし穴
・NG→OKの流れで、「どこで勘違いしやすいか」を意識しながら復習すると、ミスを大きく減らせます。
次の第5章では、ここまでの内容をふまえて、受験生が陥りがちなミス3つとその対策をさらに整理していきます。
第5章|受験生が陥りがちなミス3つとその対策
ここまで、公務員試験の専門科目としてのマクロ経済学の全体像・頻出テーマ・事例問題を見てきました。
この章では、実際の受験生がよくハマってしまう3つの典型的なミスと、その具体的な対策をNG→OK形式で整理していきます。
ミス①:指標(GDP・失業率・物価)の意味があいまいなまま進む
ミス②:IS–LMを「線の形」で丸暗記しようとして迷子になる
ミス③:政策効果(財政・金融)が、IS・LM・AD–ASのどこにどう効くか整理できていない
5-1|ミス①:GDP・失業率・物価の「意味」があいまい基礎指標
マクロ経済学の基礎になるGDP・失業率・物価は、一見わかりやすそうに見えますが、定義をきちんと理解していないまま進んでしまう受験生が多いです。
- 「GDP=国の売上げ」くらいのイメージで止まっている
- 失業率は「仕事がない人の割合」くらいしか説明できない
- 物価は「値段が上がるか下がるか」だけで、物価指数やインフレ率の定義があいまい
この状態だと、成長率やインフレ率を使った計算問題・文章問題で「何を聞かれているのか」がぼやけてしまいます。
まずは、各指標を日本語1行で言い切れるようにすることが大事です。
- 名目GDP:その年の価格で測った国全体の付加価値
- 実質GDP:物価の影響を取り除いた「量」に注目したGDP
- 失業率:労働力人口のうち、仕事を探しているが見つかっていない人の割合
- インフレ率:物価指数がどれくらいの割合で上がったか
これだけでも、式やグラフの意味がぐっとイメージしやすくなります。
・テキストで指標が出てきたら、「=」のあとに自分なりの日本語1行定義を書き込む
・過去問の選択肢を読んで、「この文はどの指標のどこを聞いているか?」と意識してチェックする
5-2|ミス②:IS–LMを「線の形」で丸暗記しようとしてしまうIS–LM
IS–LMモデルは図が特徴的なため、どうしても「右下がりがIS・右上がりがLM」といった形だけを覚えがちです。
- 「IS=財市場」「LM=貨幣市場」という役割の違いが曖昧
- 財政政策・金融政策がどちらの曲線を動かすかを混同しがち
- グラフのシフト後、利子率と所得の変化を論理的に追えない
IS–LMを攻略するコツは、「どの市場の話か」を常に意識することです。
- IS:財市場(投資・貯蓄・政府支出など) → 財政政策が効く
- LM:貨幣市場(貨幣需要・貨幣供給) → 金融政策が効く
- 財政拡張(G増加・減税) → ISが右シフト → Y↑・r↑
- 金融緩和(マネーサプライ増) → LMが右下シフト → Y↑・r↓
つまり、「どの政策がどの曲線をどちらに動かすか」を明確にできれば、グラフは怖くなくなります。
・ノートの見出しを「IS=財市場」「LM=貨幣市場」と書いてから解説をまとめる
・過去問を解くとき、「これは財政政策?金融政策?」と口に出して確認するクセをつける
5-3|ミス③:政策効果がIS・LM・AD–ASのどこにどう効くか整理できていない政策分析
マクロ経済学の山場は、財政政策・金融政策が、各モデルでどう表現されるかを整理する部分です。ここが曖昧だと、選択肢問題でプラス・マイナスを逆にしてしまう原因になります。
- 「財政出動→景気がよくなる」「金融緩和→金利が下がる」程度のざっくり理解で止まっている
- IS–LMとAD–ASを別々の話として覚えてしまう
- 「政府支出が増えると、利子率は?産出量は?物価は?」と聞かれると混乱する
政策効果は、①どの曲線が動くか → ②Y・rがどう変わるか → ③AD–ASではどう表現されるかの順で整理するとスッキリします。
-
財政拡張(政府支出増)
・IS–LM:IS右シフト → Y↑・r↑
・AD–AS:需要増 → AD右シフト → 物価P↑・産出量Y↑(需要インフレ) -
金融緩和(マネーサプライ増)
・IS–LM:LM右下シフト → Y↑・r↓
・AD–AS:利子率低下→投資増 → AD右シフト → 物価P↑・産出量Y↑
このように、「政策 → IS・LM → AD–AS」と矢印でつなげて覚えておくと、文章問題でも迷いにくくなります。
・政策ごとに「IS–LMでは?」「AD–ASでは?」と2段階でメモを作る
・ノートの端に、「財政拡張:Y↑・r↑・P↑」「金融緩和:Y↑・r↓・P↑」のようにまとめ表を作っておく
・マクロ経済学の失点パターンは、「指標のあいまいさ」「グラフ丸暗記」「政策効果の整理不足」の3つに集約される
・グラフや式は、必ず日本語の一言説明+イメージとセットで覚える
・NG→OKの比較で、「自分はどこでつまずきやすいか」を明確にしておくと、復習の効率がぐっと上がる
次の第6章では、ここまでの内容を最短ルートで身につける勉強法として、スタディング公務員講座の活用方法を詳しく紹介していきます。
第6章|スタディングを使ってマクロ経済学を最短攻略する方法
マクロ経済学は、公務員試験の専門科目の中でも「グラフ」「計算」「政策分析」など覚える量が多く、 独学でつまずく受験生が非常に多い科目です。
- 講義が図解中心で、グラフの意味がすぐ理解できる
- IS–LM/AD–ASをアニメーションで動かして解説
- 「GDP・失業率・物価」など基礎を超わかりやすく噛み砕く
- 問題演習 → AI復習で自分だけの弱点克服ルートを自動生成
- スマホで完結するので、スキマ時間で毎日5分の積み上げができる
6-1|講義 → 演習 → AI復習の3ステップで最速インプット
スタディングのマクロ経済講義は、グラフをただ見せるだけでなく、アニメーションでなぜ動くのかまで解説してくれます。
「線の形を覚えるのではなく、理屈で理解する」ので、本番で応用が効きます。
マクロ経済はアウトプットの量が差をつける科目。スタディングでは、スマホでスキマ時間に何度も問題演習ができます。
- 過去問のエッセンスを抽出した良問
- 「なぜ間違えたのか?」が一目で分かる解説
- 復習すべき問題に自動フラグが立つ
スタディングのAI復習は、あなたの解答データから忘れるタイミングを予測して、最適なタイミングで問題を再出題してくれます。
「覚えたと思っていたのに忘れていた…」が激減します。
6-2|マクロ経済の得点力が一気に伸びる理由
・グラフを“動き”で理解するので、暗記に頼らない
・IS–LM → AD–ASの流れが自然と頭に入る
・スマホで復習できるので、反復回数が増える
・復習管理が自動なので、弱点が消えるのが早い
6-3|レビュー記事も参考に(内部リンク)
スタディングの詳しい特徴やデメリットも知りたい方は、こちらの記事で徹底解説しています。
6-4|今すぐマクロ経済を得点源にしたい方へ
マクロ経済学は、正しく学べば最短1〜2ヶ月で得点源になります。 そのための最速ルートとして、スタディングは非常に相性が良い教材です。
【今すぐチェック】スタディング公務員講座を見るマクロ経済は「理解さえできれば一気に伸びる科目」です。 独学に時間がかかっている方は、スタディングを使うことで学習コストと失点リスクを大きく下げられます。
第7章|マクロ経済学の総まとめ(重要ポイントの再確認)
ここでは、第1章〜第6章までの内容を振り返りながら、公務員試験でマクロ経済学を得点源にするための重要ポイントを整理していきます。
「どこから復習し直せばいいか分からない…」というときは、この章をチェックリストとして使ってください。
マクロ経済学は、個々の市場を見るミクロ経済学と違い、国全体の経済の動きを扱う科目です。
- 扱うテーマ:GDP・物価・失業・景気・財政政策・金融政策など
- ニュースでよく目にする指標と直結しており、ストーリーで理解しやすい
- 出題範囲が比較的整理されているため、対策次第で安定した得点源になりやすい
第2章で見たように、マクロ経済学は次の4つのブロックで整理すると理解しやすくなります。
- ① GDP・物価・失業(基礎指標)
- ② IS–LM分析(財市場+貨幣市場)
- ③ 財政政策・金融政策(マクロ政策)
- ④ AD–AS分析(物価と産出量の決定)
この4つが「バラバラの単元」ではなく、つながったストーリーとして頭に入っているかが、得点力の差になります。
公務員試験で何度も問われるのは、次の5テーマでした。
- GDPと国民所得(三面等価、名目・実質)
- 景気と失業率(オークンの法則)
- 物価とインフレ率(フィリップス曲線)
- IS–LMモデル(財市場・貨幣市場の同時均衡)
- AD–ASモデル(物価水準と産出量の決定)
これらは「横軸・縦軸・曲線の意味」を日本語で説明できるかどうかを目安に復習すると、理解度が一気に上がります。
第4章・第5章では、受験生が陥りがちなミスをNG→OK形式で整理しました。
- 名目GDPと実質GDPを「物価」とごっちゃにする
- IS・LMのシフト方向を感覚で決めてしまう
- 需要インフレと供給インフレの違いを図で確認していない
- 政策(財政・金融)が、Y・r・Pにどう効くかを整理できていない
自分のNGパターンに当てはまるところをピックアップし、OKパターンの考え方を真似することで、失点を大きく減らすことができます。
第6章では、マクロ経済学を効率よく学ぶツールとしてスタディング公務員講座を紹介しました。
- 図解・アニメーション中心の講義で、グラフの意味から理解できる
- 講義と連動した演習で、過去問レベルをスマホで繰り返し解ける
- AI復習機能により、忘れる前に自動で復習問題が出てくる
独学で手一杯になりがちなマクロ経済学も、「何を・どの順番で・どれくらいやるか」を任せられるので、時間のない社会人・大学生受験生には特におすすめです。
・マクロ経済学は「4大ブロック」と「頻出5テーマ」に絞って学ぶと効率的
・グラフや式は、必ず日本語1行の説明+イメージとセットで覚える
・NG→OK比較で、自分のつまずきポイントを特定しておくと復習の質が上がる
・スタディングを活用すれば、講義 → 演習 → AI復習の流れで最短ルートの学習が可能
この流れを意識して学習を続ければ、マクロ経済学は安定して得点できる強力な専門科目になります。
次の第8章では、マクロ経済学の学習とあわせて読みたい関連記事(内部リンク)をカード形式で紹介します。
第8章|関連記事リンク
マクロ経済学とセットで学ぶと理解が深まる、えびうるブログ内のおすすめ記事をまとめました。 すべてスマホで読みやすい図解つきなので、スキマ時間の復習にも最適です。
・関連記事はブックマークしておくと復習がスムーズ ・マクロ経済学+ミクロ経済学はセット学習で理解が最速になります ・スタディングを併用すると、専門科目の得点力を短期間で底上げできます