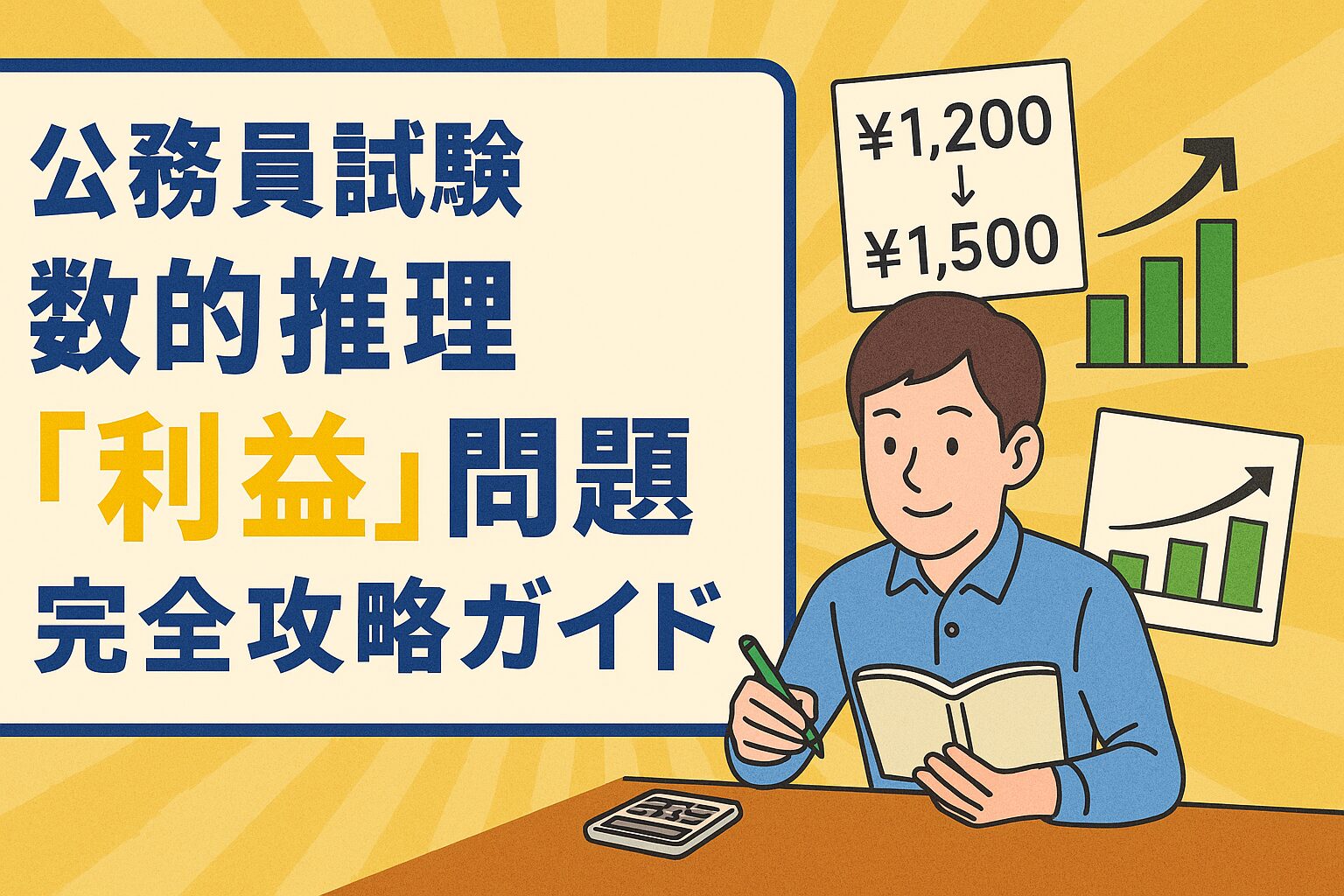数的推理「濃度」:得点を最短で積み上げるコツ
はじめに:苦手をチャンスに変えるテーマ
「食塩水の濃度って苦手…」「混ぜたり薄めたり、何が何だか混乱する💦」 ——そんな方にこそおすすめなのが濃度問題です。 実はここ、出題頻度が高く計算がパターン化しやすい“狙い目”ジャンル。 公務員試験の数的推理を得点源に変えたいなら、まずはこの分野を押さえるのが最短ルートです。
なぜ「濃度」は伸びしろが大きいのか?
濃度問題は一見むずかしそうですが、考え方はとてもシンプル。
どんな問題でも、結局は「食塩の量=濃度×全体量」という
1本のルールに集約されます。
この式を「混合」「希釈」「蒸発」「入れ替え」の4パターンにあてはめるだけで、
ほぼすべての問題が整理可能です。図にすると以下のようなイメージ👇
食塩水A(10%・200g)+ 食塩水B(20%・300g)→ 合わせて500g・何%?
つまり「食塩の合計 ÷ 全体量 ×100」だけ。 構造をイメージすれば、文字の式よりずっとわかりやすくなります。
ミニ例題:まずは基礎を確認!
考え方:食塩の量は変わらない(保存)。
200×0.10=20g → (200+x)×0.08=20 → x=50g。
👉 「保存+全体量の更新+1本の式」でOK。
この記事で得られること
✔️ 濃度の基礎を“図で理解” ✔️ 頻出4パターンの型をマスター ✔️ 暗算・近似で時短解法を習得 ✔️ ミスを減らすチェックリスト付き 最後に、スマホでスキマ学習できるスタディング公務員講座も紹介します。 自分のペースで反復→理解→得点アップを実現しましょう。
濃度の定義と計算の考え方:図で理解しよう
「濃度」とは何を表している?
公務員試験の数的推理で扱う濃度は、食塩水・アルコール水溶液などの 「溶質(とかしたもの)」と「溶媒(水など)」の割合を表します。 よく出る「%」は“全体のうち食塩が何%あるか”を示すだけ。つまり――
例えば、10gの食塩を90gの水に溶かすと全体100g。 食塩10 ÷ 100 ×100=10%。 単純ですが、ここがすべての出発点です。
・溶質=食塩など、とけているもの。
・溶媒=水など、とかしている液体。
・溶液=両者を合わせた全体。
式では「溶液=溶質+溶媒」を常に意識しましょう。
計算で使う3つの基本操作
濃度問題は「混ぜる・薄める・濃くする」の3操作だけで構成されます。 それぞれの考え方を簡単にまとめると:
② 希釈(水を足す)→ 食塩は増えず、全体量だけ増える。
③ 蒸発(濃縮)→ 食塩は変わらず、水が減るので%上昇。
ミニ例題:基礎式の確認
解法:
食塩量=150×0.12=18g(保存)
(150+x)×0.10=18 → 15+0.1x=18 → x=30g。
✅ 答え:30gの水を加える。
ここまで理解できれば、次章の「頻出4パターン」もスムーズに読めます。 濃度問題の本質は、“食塩の量はどう変化したか”を追うだけです。
頻出パターン4選:型で覚える濃度問題
濃度問題は、出題形式こそ違って見えても、ほとんどが以下4つのパターンに分類されます。 各パターンの“考え方の型”を覚えれば、文章を読んだ瞬間に式が立つようになります。
① 混合:A%+B% → C%(平均型)
異なる濃度の溶液を混ぜると、食塩量は合計、全体量も合計。 濃度は「食塩の合計 ÷ 全体量」で求めます。
食塩量=200×0.10+300×0.20=20+60=80g。
全体量=500g → 80÷500=0.16=16%。
・濃い液体と薄い液体の「中間値」になる。
・食塩量の保存を使えば、比でもOK(10:20なら中間16%など)。
② 希釈:水や溶媒を足して薄める
水を加えると、食塩量はそのまま、全体量だけ増えます。 濃度が下がる典型問題で、“食塩保存”を使うのが鉄則。
食塩保存:300×0.12=36。
(300+x)×0.10=36 → x=60g。
✅ 答え:60gの水を加える。
・濃度が下がる=「分母が増える」だけ。
・食塩保存の式が作れれば一瞬で解けます。
③ 蒸発:水分が減り、濃くなる
水が蒸発して全体量が減ると、食塩の割合(濃度)は上がります。 水だけが減る=食塩は保存、と考えるのが基本。
食塩=200×0.10=20g(保存)
全体=180g → 20÷180=0.111…=約11.1%。
・蒸発量=全体量減少 → 濃度アップ。
・「保存+減少」のダブル意識が鍵。
④ 入れ替え:一部を捨てて同量を足す
タンクやビーカーから一部を抜いて水を足すタイプ。 計算は少し複雑ですが、手順は「減少→補充」をセットで扱えばOK。
捨てた分の食塩=100×0.20×(40/100)=8g減少。
残り食塩=20−8=12g。全体は再び100g。
12÷100=12%。
① 捨てた食塩量を求める。
② 残った食塩量を出す。
③ 補充後の全体量で割る。
→ この3ステップで一発解決!
以上の4パターンを「食塩保存+全体変化」で捉えれば、 濃度問題はほぼ自動的に解けるようになります。 次章では、これらを使った「実践例題&時短テク」を紹介します。
例題で確認!混合・希釈のステップ解説
STEP①:混合問題(比で一瞬に解く)
混合では「AとBの濃度の差」と「混合後の差」を比で扱うとスピーディー。 式を立てずに比で処理できるのがこの分野の最大の時短ポイントです。
👉 よって「8%液:20%液=2:1」で混ぜればOK。 (例えば 200g と 100g の組み合わせでも成立)
・「差の比」=食塩量の比。 ・比をそのまま混合量比として使える。
・数的推理の文章題では、暗算で済ませられる典型パターンです。
STEP②:希釈問題(保存の式でスピード解法)
希釈は食塩が変わらない=保存式を作るだけ。 「濃度が下がる=全体が増える」と覚えておけば瞬時に反応できます。
食塩保存:200×0.15=30。
(200+x)×0.12=30 → 24+0.12x=30 → x=50g。
✅ 答え:50gの水を加える。
・濃度15→12の差=3。 ・3/15=1/5=20%薄め。200gの20%=40g前後 → 近似でx≒50gと推定可。 → 試験中は「おおよそ」で判断して時間を短縮!
STEP③:混合×希釈の複合型(過去問頻出)
本試験では、混ぜたあとに水を足す「複合型」がよく出ます。 焦らず「①混ぜる→②薄める」の順に整理すればOKです。
混合段階:10×300+20×200=3000+4000=7000。全体=500g → 14%。
水を加えた後:(500+100)=600g、食塩量7000/100=70g。
70÷600=0.1166…=約11.7%。
① 食塩量を合計する(混合)。
② 全体量を更新(希釈)。
③ 食塩量を割る。
→ 手順を「上から順に書くだけ」で正答に届きます。
STEP④:計算を時短する3つの小技
- 百分率は小数に直さず、分数で処理(例:12%=3/25)。
- 端数が出るときは「概算→選択肢確認」で時間短縮。
- 「保存」か「差の比」か、どちらの型かを冒頭で判断。
この章の狙いは、式を立てるよりも考え方の順序を体で覚えること。 次章では、こうした計算でありがちなミスと対策表をまとめて確認します。
ミスしやすいポイントと対策表
濃度問題は「考え方は簡単」でも、計算手順の混乱や 基準の取り違えが起こりやすい分野です。 以下の表では、特に公務員試験で多いミスとその回避法を整理しました。
| よくあるミス | 原因と対策 |
|---|---|
| 💧「濃度=食塩÷水」として計算 |
原因:全体量と水量を混同。 対策:必ず「食塩÷全体」で計算。水ではなく溶液全体が分母です。 |
| 📉 水を加えても食塩量を変化させてしまう |
原因:保存の意識が抜ける。 対策:「食塩は保存!」を口グセに。問題を読んだら最初に「保存or変化?」を判断。 |
| ⚖️ 入れ替えで“抜いた後の量”を忘れる |
原因:全体量の更新忘れ。 対策:「減る→足す→全体100gに戻る」など、段階を順番にメモする。 |
| 🌀 比の向きを逆にしてしまう |
原因:“高いほう−中間”“中間−低いほう”の順を逆に。 対策:比を使うときは「外側の差を比べる」と覚える。 |
| ⏱️ 小数の掛け算に時間がかかる |
原因:%をそのまま小数化して計算。 対策:%を分数にして暗算(例:12%=3/25)。試験では速くて正確。 |
| 📊 濃度が上がるか下がるか判断できない |
原因:イメージ不足。 対策:「水を足せば下がる/蒸発すれば上がる」だけ先に判断してから式を書く。 |
- 「食塩は保存!」
- 「全体を分母に!」
- 「上がる?下がる?まず予想!」
この章を頭に入れておくと、試験本番でのケアレスミスを7〜8割減らせます。 次章では、得点をさらに伸ばすための勉強法・時間短縮テクを紹介します。
得点を伸ばす勉強法:型練習×反復×時間短縮
① 「型」を反射的に出せるようにする
濃度問題で点を取る鍵は、型の自動化です。 「混合 → 希釈 → 蒸発 → 入れ替え」4パターンを毎回“式を立てずに”書けるように練習しましょう。 最初は紙に図を書きながら、「保存」「全体量」「変化」のどれかを声に出して確認するのがおすすめです。
② スタディングで「反復→記憶定着」
スタディング公務員講座の数的推理講座では、 スマホ学習+AI復習システムで、理解→練習→復習が自動化されています。 1回10分の講義で図解つき解説を見ながら、スキマ時間に繰り返し演習可能。 特に濃度問題は「例題→即ミニテスト」で定着率が大幅に上がります。
① 出勤前に1問解く(理解段階)
② 昼休みに復習テスト(反復段階)
③ 夜にAI復習で誤答分析(定着段階)
→ 1日15分でも、1週間で「濃度」は得点源になります。
③ 時間短縮のための思考ルーティン
数的推理は「理解力」より「手順の速さ」が得点を左右します。 以下のように“決め打ちルーティン”を作ると、迷わず進めます。
① 状況を読む:「混ぜる?薄める?蒸発?」
② 食塩の変化を確認:「保存 or 減少 or 増加」
③ 公式を書く:「食塩=濃度×全体量」
④ 式を立てて暗算。 👉 この順で3問練習すれば、次から自動的に手が動くようになります。
④ 継続のコツ:短時間×高頻度
長時間よりも、1回10分×1日2〜3回の方が記憶が定着します。 スタディングの講義はスマホ1本で完結するため、 通勤・昼休み・寝る前など「決まったタイミング」で繰り返すのが最も効果的です。
このように「型練習 × 反復 × AI復習」を組み合わせることで、 濃度問題はほぼノーミスで解けるようになります。 次章では、実際にスタディングを活用した講座紹介&導線を解説します。
講座紹介:スタディング公務員講座で数的推理を攻略!
なぜスタディングが選ばれるのか?
公務員試験の数的推理は、独学だと「苦手克服までの時間が長い」「復習の効率が悪い」という悩みがつきもの。 そこで注目されているのが、スタディング公務員講座です。 AIを活用した復習機能とスマホ完結の学習システムで、通勤中・スキマ時間でも得点力を積み上げられます。
✅ 図解つきの動画講義で「比・割合・濃度」など抽象概念が直感的に理解できる。
✅ 1問3分のスマホ演習で、テンポよく反復練習が可能。
✅ AI復習機能が「間違えた問題だけ」を自動で再出題。
✅ 解説はすべて講師オリジナル、基礎~応用を一気にカバー。
おすすめの活用法:濃度問題での反復ループ
たとえば、今回の「濃度」分野を例にとると、 スタディングの講義動画(図解)→ ミニ演習 → AI復習 の流れを1セットにして回すだけ。 この“学習ループ”を3周すれば、ほぼミスゼロに近づけます。
・Day1〜2:動画で基礎理解(混合・希釈の型)
・Day3〜5:スマホで反復演習(AI復習ON)
・Day6〜7:過去問で総まとめ+誤答分析
→ 1サイクルで得点安定化!
受講者の声(抜粋)
「短時間で解法パターンが整理できて、模試で数的推理が得点源になった!」(市役所志望・20代)
「動画がわかりやすくて、濃度や割合の問題が“数字の意味”として理解できた!」(国家一般職・合格者)
実際の講座内容・受講プランは以下のリンクから確認できます。 公務員試験対策の「最短ルート」を探している方は、ぜひ一度チェックしてみてください👇
なお、スタディング講座の詳細レビューは別記事でも紹介しています: スタディング公務員講座の合格率アップ実例 → 体験談ベースで、さらに具体的な学習法が分かります。
次章では、記事全体のまとめと、関連するおすすめ記事を紹介します。 「比と割合」や「損益算」など、濃度とセットで得点を底上げできるテーマも要チェックです!
まとめ:濃度問題を得点源に変えるために
ここまで学んできたように、濃度問題は決して難問ではありません。 ポイントは、型で覚えて、保存の考え方で整理すること。 文章の形が違っても、「混ぜる・薄める・蒸発・入れ替え」の4型に分類すれば、 どんな問題でも安定して点が取れるようになります。
- 濃度=「食塩の量 ÷ 全体量」で整理する。
- 4つの型(混合・希釈・蒸発・入れ替え)をマスター。
- 保存と比のどちらを使うかを判断する。
- スタディングのAI復習で自動反復 → 定着率UP!
公務員試験の数的推理では、1問の得点が合否を分けることも少なくありません。 濃度問題のようにルールが明確な分野は、「得点源」にできる絶好のチャンスです。 今のうちに、スタディング講座を使って基礎→応用→演習の流れを固めておきましょう。
公務員試験の学習は、最初は難しく感じても「パターンで整理」すれば必ず得点に結びつきます。 一歩ずつ確実に、効率よく学びを積み上げていきましょう💪