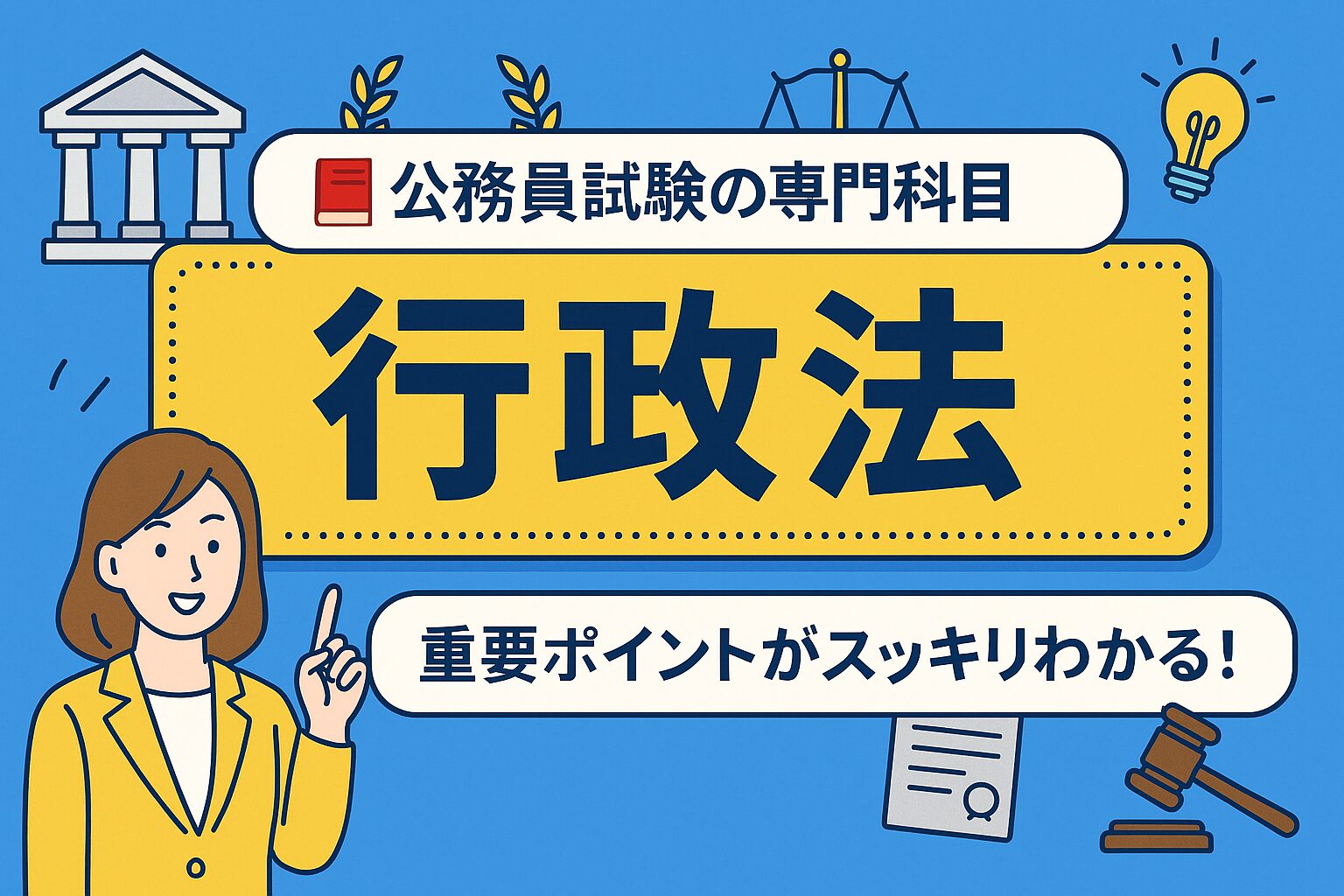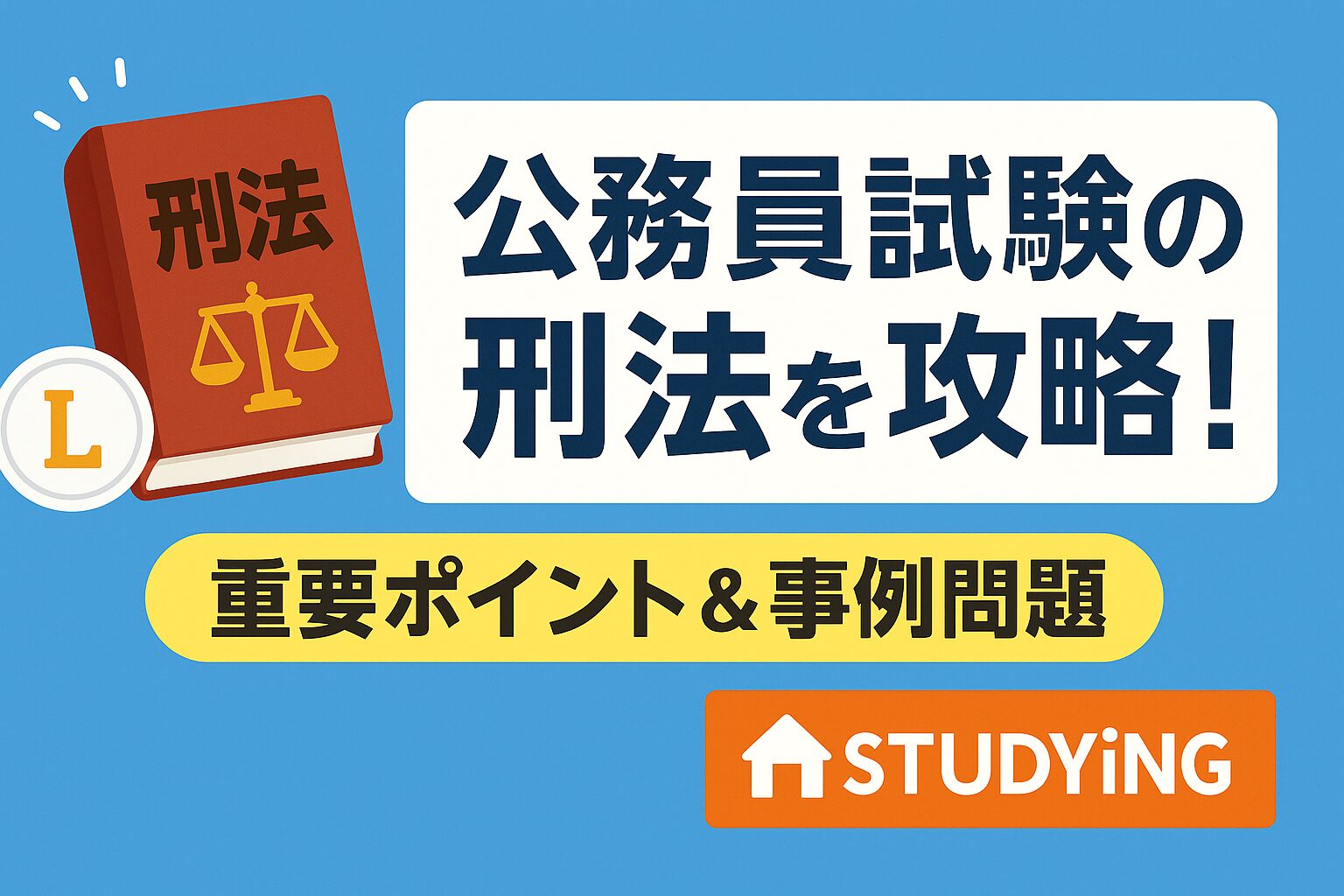第1章|はじめに:労働法は“得点調整が効くコスパ科目”
労働法は、公務員試験の専門科目の中でも 「短期間で得点が伸びやすいコスパ科目」です。 なぜなら、毎年出題されるテーマがほぼ固定されているうえ、 条文そのものよりも“考え方・流れの理解”が問われる割合が非常に高いからです。
- 出題範囲が“狭い”ので覚える量が少ない
- 条文問題が多く、パターンを覚えればすぐに点が取れる
- 複雑な判例が少なく、暗記の負担が軽い
- 労働基準法・労働契約法・労働組合法の構造だけで8割が読める
さらに、勉強の仕方次第でわずか数日〜1週間でも合格ラインに到達できるため、 「専門科目の得点が足りない…」という受験生にとって救世主のような科目です。
労働法は「どの条文が何を守るためのものか」を理解すると、 選択肢の正誤がスラスラ判断できるようになります。
本記事では、労働法の出題範囲を体系的に整理し、 図解で“わかりやすく”・例題で“実戦的に”理解できる内容に仕上げています。 さらに、最短で得点源にするための学習ルートとして スタディング公務員講座の活用方法も紹介します。
第2章|人事院試験で問われる労働法の全体像(3つの柱)
労働法は、3つの法律(労働基準法・労働契約法・労働組合法)を中心に出題されます。 まずはこの3つが「何を守る法律なのか」を理解するだけで、試験問題の読みやすさが一気に変わります。
労働法は3つの法律で体系が決まる(図解)
労働法はこの3本柱を押さえるだけで合格ラインに届く科目です。 特に労働基準法と労働契約法は、毎年ほぼ確実に出題されます。
① 労働基準法(最低基準を守る法律)
労働時間、休憩、休日、割増賃金など、 「働く時間と環境」を守るための最低ラインを定めた法律です。 出題数が最も多く、ここだけで5〜6問出ることもあります。
- 労働時間(1日8時間・週40時間)
- 休憩(6h→45分 / 8h→1時間)
- 有給休暇(比例付与・時季変更権)
② 労働契約法(個別労働関係のルール)
労働者と会社との「契約」に関するルールを定めた法律。 解雇・懲戒・労働条件の変更が頻出テーマです。
- 解雇の合理的理由
- 懲戒の相当性
- 労働条件の不利益変更
③ 労働組合法(労働者が団結する権利を守る法律)
労働組合の権利や団体交渉・争議行為のルールを定めた法律。 不当労働行為は毎年必ず出題される最重要テーマです。
- 団体交渉権・団体行動権
- 不当労働行為の3類型
- 雇用者側の支配介入・不利益取扱い
- 労働法は3つの法律の体系で理解するのが最短ルート
- 特に「労基法・労契法・労組法」の頻出テーマだけで8割取れる
- この後は「頻出テーマ5選」で得点ゾーンを徹底攻略
第3章|頻出テーマ5選(図解でスッキリ理解)
労働法は、出題されるテーマがほぼ固定されているのが特徴です。 ここでは公務員試験で毎年狙われる5つの頻出テーマを、図解と一緒に整理していきます。
① 労働時間と割増賃金(8時間・40時間の原則)
労働時間の問題は、「原則」+「例外(36協定)」+「割増率」のセットで出題されます。
- 原則:1日8時間・週40時間を超えて働かせてはいけない
- 36協定+届出があれば時間外労働はOKだが、割増賃金が必要
- 深夜・休日労働ではさらに割増率が上がる
「次のうち、労働基準法上の労働時間と割増賃金に関する記述として正しいものはどれか。」
② 休憩・休日・年次有給休暇(セットで覚える)
休憩・休日・年休は、数字と要件をおさえるだけで一気に得点源になります。
- 休憩:6時間超→45分 / 8時間超→60分
- 休日:少なくとも毎週1回、または4週4日
- 年次有給休暇:6か月継続勤務+8割以上出勤で10日付与
③ 解雇の有効性(合理的理由と社会的相当性)
労働契約法では、解雇が有効かどうかを「合理的理由」「社会的相当性」で判断します。
- 「問題行動があったか?」だけでなく、手続・配慮などの相当性も見られる
- 形式的に就業規則違反でも、直ちに解雇が有効とは限らない
- 問題文では「事情」と「対応の仕方」が分けて書かれていることが多い
「次の解雇に関する記述のうち、労働契約法の趣旨から適切なものはどれか。」
④ 不当労働行為(使用者側のNG行為3パターン)
労働組合法の中心となるのが不当労働行為です。 使用者がやってはいけない行為が3パターンに整理されています。
- 不利益取扱い:組合活動を理由に解雇・異動などで不利益に扱う
- 団体交渉拒否:正当な理由なく団体交渉を拒否する
- 支配介入:会社が組合の運営に口出しする・御用組合を作る など
⑤ 団体交渉権・団体行動権(労働三権の中身)
労働三権(団結権・団体交渉権・団体行動権)は憲法でも登場しますが、 労働組合法では具体的にどのような場面で保障されるかが問われます。
- 団結権:労働者同士が団結して組合を作る権利
- 団体交渉権:使用者と団体で交渉する権利
- 団体行動権:ストライキなどで意思を示す権利
「次のうち、労働組合法上の不当労働行為に該当するものはどれか。」 「労働三権の内容に関する説明として妥当なものはどれか。」 など。
第4章|受験生が陥る労働法のミス3つと対策(NG→OK比較)
労働法は出題パターンがはっきりしている一方で、 「数字」「要件」「NG行為」の区別でつまずきやすい科目です。 過去問を分析すると、受験生がよく犯すミスは以下の3つに絞られます。
① 労働時間の例外(36協定・休憩)の混同
「36協定があれば何時間でも働かせてOK」と誤解してしまう。
36協定は「法定時間を超えて働かせるための手続き」であって、 無制限ではない。割増賃金も必ず必要。
▼ よくある誤読の理由: 「36協定=全て許される」と思ってしまうため。
「36協定の本質=法の“例外”を認める届出」と理解しておく。
② 解雇の有効性(合理的理由と相当性)を混ぜる
「問題行動があれば即解雇は有効」と早合点してしまう。
解雇は合理的理由(事情の有無)と 社会的相当性(対応の仕方)の 2つが揃って初めて有効と判断される。
▼ なぜ間違える? 「就業規則違反=即解雇可」という誤解が多い。
「事情(Why)」と「方法(How)」の2軸で選択肢を読む。
③ 不当労働行為の3類型を“意味で”覚えていない
名前だけ丸暗記して、実際に「どの行為が該当するか」が判断できない。
不当労働行為は
・不利益取扱い(組合員への不利益)
・団体交渉拒否(正当理由なしの拒否)
・支配介入(組合の内部に介入)
と“行為の意味”で覚えると選択肢が読める。
▼ 間違える理由: 「どれがどれ?」と名称だけ暗記してしまうため。
名称ではなく「会社がやったNG行為」をイメージして覚える。
第5章|スタディングで労働法を最短攻略する方法(PR)
労働法は、出題範囲が比較的コンパクトで「一気に点が伸びやすい」科目です。 その一方で、条文や数字を独学で詰め込もうとして挫折する受験生も少なくありません。 そこでおすすめなのが、スマホ1台で学べるスタディング公務員講座です。
◎ 労働法を得点源にする3ステップ(理解→暗記→演習)
この3ステップをすべてアプリ内で完結できるのが、スタディングの大きな強みです。
① 講義で「条文の意味」と「数字の理由」を理解する
労働法は、ただ条文の数字を暗記するだけではなく、 「なぜその数字なのか?」を理解すると一気に覚えやすくなります。 スタディングの講義では、労働基準法・労働契約法・労働組合法を 図解と具体例でわかりやすく解説してくれます。
- 労働時間・休憩・休日などの数字の意味がイメージで理解できる
- 解雇・不当労働行為などの難所を事例ベースで解説
- 1本あたりが短いので、通学中や休み時間にもサクッと見られる
② 過去問レベルの演習で「出題パターン」をつかむ
労働法の本試験問題は、毎年似たパターンの条文・数字・用語が繰り返し出題されます。 スタディングの問題演習では、本試験と同じ形式の選択肢に慣れることができます。
- 労働時間・割増賃金(1日8時間・週40時間・36協定)
- 休憩・休日・年次有給休暇の数字と要件
- 解雇の有効性(合理的理由・社会的相当性)
- 不当労働行為の3類型(不利益取扱い・団交拒否・支配介入)
「この選択肢、前にも見たな…」と思えるレベルまで解くと、 労働法はほぼノーミスの得点源になります。
③ AI復習で「数字」と「要件」を自動的に焼き付ける
労働法は、6時間・8時間、6か月・8割、といった数字の組み合わせが多く、 放っておくとすぐに混ざってしまいます。 スタディングのAI復習は、あなたが間違えた問題や忘れそうな論点を 自動で優先的に出題してくれます。
- 条文数字の暗記を「自動で反復」できる
- 弱点になっているテーマだけ重点的に出題
- スマホでスキマ時間に5問ずつ解けるから継続しやすい
まとめ 労働法はスタディングと相性バツグンの“短期得点源”
労働法は、出題範囲が限られている分、 正しい順番でインプットと演習を回せば短期間で仕上がる科目です。
- 講義で「条文の意味」と「数字の理由」を理解する
- 問題演習で本試験レベルの選択肢に慣れる
- AI復習で数字・要件を自動的に定着させる
「専門科目の点数をあと数点伸ばしたい」「短期間で伸ばせる科目を探している」 という人は、労働法×スタディングの組み合わせがとてもおすすめです。
▶ スタディング公務員講座の詳細を見る第6章|まとめ(労働法は“数字×意味理解”で一気に伸びる)
労働法は、公務員試験の専門科目の中でも 「短期間で点が伸びるコスパ最強科目」 です。 その理由は、出題テーマが固定化されており、 「数字」と「条文の意味」さえ押さえれば得点が安定するからです。
- 労働法は3つの柱(労基法・労契法・労組法)で体系が決まる
- 頻出テーマ5つ(労働時間/休憩・休日/解雇/不当労働行為/団体交渉)を理解すればOK
- つまずきやすいポイントはNG→OK比較で整理すると頭に残りやすい
- スタディングを使えば“理解→暗記→演習”の流れを自動化できる
特に労働法は、36協定・割増賃金・年休の数字など、 「数字の暗記+理由理解」ができれば一気に得点源になります。
▶ スタディング公務員講座を今すぐチェックする