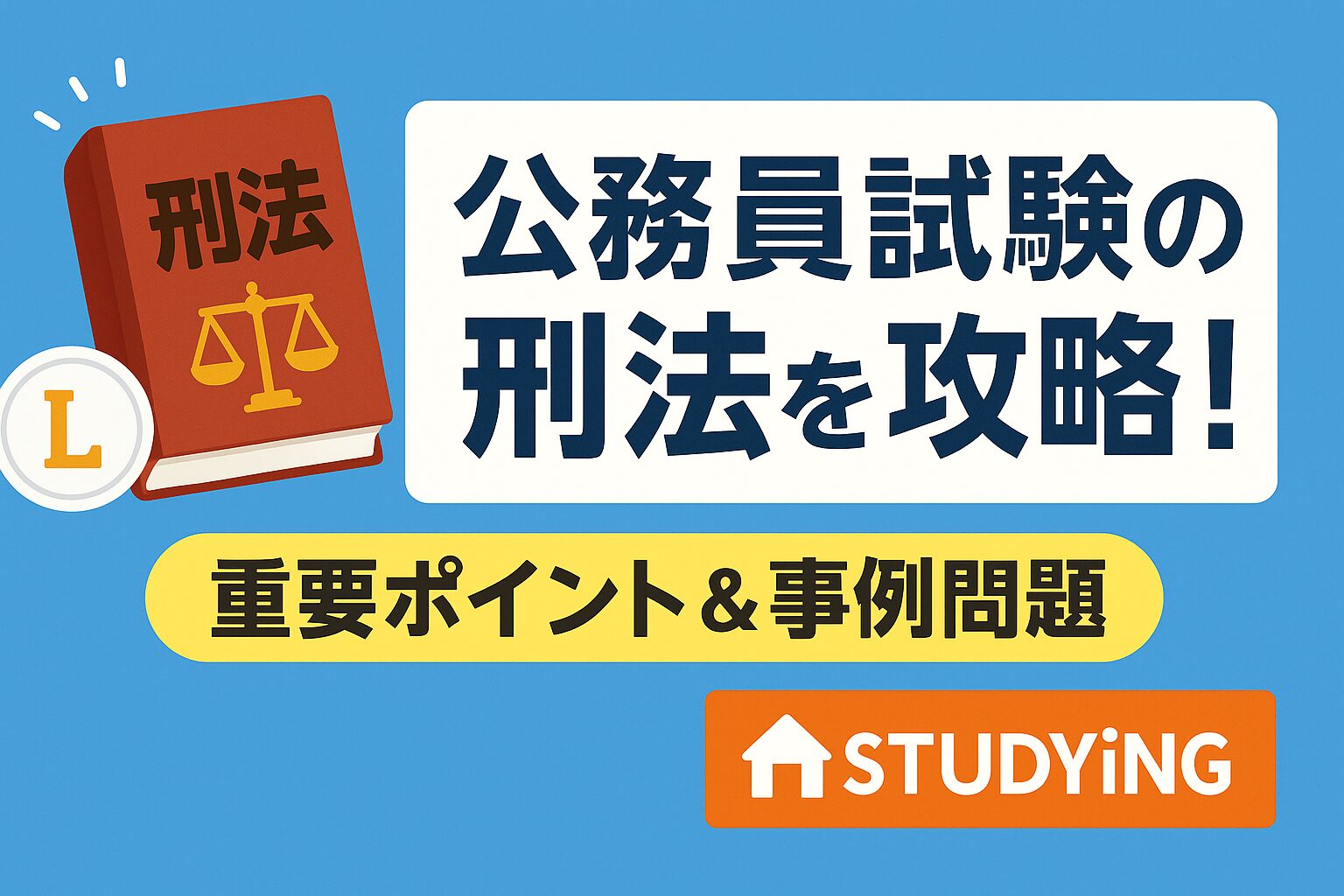第1章|はじめに:刑法は“点が伸びる”実力科目
刑法は、公務員試験の専門科目の中でも 「理解すれば点が伸びる」科目です。 なぜなら、刑法は他の科目と違い、 “判断の順番”が決まっているため、 正しいステップで問題を読めば、誰でも安定して得点できるようになるからです。
- 構成要件 → 違法性 → 有責性 の順番が毎回同じ
- 頻出テーマ(故意・過失・正当防衛・共犯など)が固定化
- 事例問題でも判定の流れに従えば正答率が上がる
- 暗記よりも「理解」で戦えるので差がつきやすい
特に公務員試験の刑法は、 憲法・行政法・民法よりも“短期間で仕上がる”傾向があります。 理由は、出題される論点が決まっているうえに、 条文よりも論理的な判断の流れが問われるからです。
「この行為は犯罪か?」と考えると難しいですが、 「①構成要件 → ②違法性 → ③有責性」 の3ステップで順に判断すると驚くほど理解しやすくなります。
本記事では、公務員試験で毎年出題される刑法の重要論点を、 図解とケースでやさしく整理しています。 また、短期間で得点を伸ばしたい人向けに スタディング公務員講座の活用法も紹介します。
第2章|刑法の全体像(構成要件 → 違法性 → 有責性)
刑法の最大の特徴は、どんな犯罪でも 「構成要件 → 違法性 → 有責性」 の3段階で判断するという点です。 この“判断の順番”を理解するだけで、事例問題の処理速度が一気に上がります。
刑法の判断ステップ(全体像)
これを“刑法の三段階審査”と呼びます。 どれかが欠ければ犯罪は成立しません。
① 構成要件該当性(まずは「行為の外側」をチェック)
「その行為が法律に書かれた犯罪類型に当てはまるか?」 を判断するステップです。
- 行為が犯罪に“形式的に当てはまる”か
- 故意・過失があるか
- 結果犯なら因果関係が成立するか
ここで「そもそも犯罪の型に当てはまらない」と判断すれば、 その時点で犯罪不成立になります。
② 違法性(正当防衛などで“違法”が消える場合)
構成要件に当てはまった後でも、状況によっては 「違法ではない」と認められることがあります。
- 正当防衛
- 緊急避難
- 被害者の承諾
これらに該当すると、その行為は 「形式的には犯罪だが違法ではない」 という扱いになります。
③ 有責性(行為者に責任を問えるか?)
最後に、「その人に責任を問える状態だったか」を判断する段階です。
- 責任能力(心神喪失 etc.)
- 期待可能性(避けられる行為だったか)
- 故意の有無の再評価など
有責性が認められなければ、たとえ行為自体が違法でも 犯罪としての責任は問われません。
「外側(行為) → 中身(違法) → 最後に“人”を見る」 という順番で考えると頭にすっと入ります。
第3章|頻出の刑法テーマ5選(図解つき)
公務員試験の刑法は、毎年ほぼ決まったテーマが繰り返し出題されます。 ここでは、その中でも「絶対に落としたくない5つの頻出論点」を 図解とともに整理していきます。
① 構成要件該当性と故意・過失
最初のステップである構成要件該当性では、 行為が犯罪の「型」に当てはまるかどうかを判断します。 ここで重要になるのが故意・過失です。
- 故意:結果の発生を認識・認容している(わかっててやった)
- 過失:注意すれば防げたのに、注意しなかった(うっかり)
- 結果犯では「行為→結果→因果関係」のセットで見る
「次のうち、過失犯が成立するのはどの事例か。」 「故意の有無に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。」 など。
② 違法性阻却事由(正当防衛・緊急避難など)
構成要件に当てはまっても、正当防衛・緊急避難などで違法性が阻却されると 犯罪とはなりません。ここは公務員試験で必ず出る鉄板テーマです。
- 急迫不正の侵害があること
- 権利を守るための防衛行為であること
- 防衛行為が「相当」な範囲であること
正当防衛かどうか迷ったら、 「①本当に危なかった? ②守るため? ③やりすぎてない?」 の3点でチェックすると整理しやすいです。
③ 共犯(教唆・幇助)の整理
公務員試験では、正犯・共犯(教唆・幇助)の区別がよく出題されます。 誰の行為がどこまで犯罪成立に影響するかを押さえましょう。
- 教唆犯:人をそそのかして犯罪を決意させる
- 幇助犯:犯罪実行を手助けする(道具提供など)
- 原則として、教唆・幇助も正犯と同じ刑が科される
「教唆犯・幇助犯の説明として正しいものはどれか。」 「Aの行為は教唆にあたるか、幇助にあたるか。」 など。
④ 未遂犯・予備罪(どこから犯罪になるか)
未遂犯・予備罪の論点では、「どの時点から犯罪として処罰されるか」が問われます。
- 予備:準備段階の行為(道具をそろえるなど)
- 未遂:実行行為に着手したが結果が生じなかった
- 既遂:結果まで生じて犯罪が完成した状態
「被害者側から見て危険が現実化したか?」 という視点で「着手」のタイミングを考えると整理しやすいです。
⑤ 刑の減軽・併合罪(処罰のされ方)
最後に、「どの程度の刑が科されるのか」という処罰のルールも 公務員試験でよく問われます。特に併合罪は頻出です。
- 複数の犯罪が成立したときの刑の決め方が「併合罪」
- 原則として、最も重い刑を基準にして加重される
- 「減軽・酌量などがあるとどう変わるか」が出題されることも
「次のうち、併合罪に関する説明として妥当なものはどれか。」 「刑の減軽に関する記述のうち、刑法の規定に照らして正しいものはどれか。」 など。
第4章|よく出る事例問題を図解で攻略(NG→OK比較)
公務員試験の刑法は、条文知識だけでなく 「事例をどう評価するか」を問う問題が多く出題されます。 ここでは、特によく出る3つのパターンを NG解釈 → OK解釈+簡易図解で整理していきます。
① 正当防衛の事例(やりすぎかどうかの判断)
正当防衛は頻出ですが、「やりすぎ」かどうかの判断でミスが起こりがちです。
「攻撃されたのだから、どんな反撃でも正当防衛になる」と考えてしまう。
正当防衛が認められるには、
- 急迫不正の侵害(今まさに不法な攻撃がある)
- 権利防衛の意思(自分や他人の権利を守るため)
- 防衛行為の相当性(やりすぎていない)
「攻撃 > 防御」になっていないかをイメージすると、 相当性の判断がしやすくなります。
② 共犯事例:教唆か幇助かを見分ける
共犯の事例問題では、人の関わり方を正しく整理できるかがカギです。
「一緒に関わっていれば全部“共犯”で同じ」とまとめて考えてしまう。
- 教唆:そそのかして犯罪の決意を生じさせる
- 幇助:道具提供などで実行を手助けする
- 正犯:実際に実行行為を行う
事例を読んだときに、「この人は犯行を思いついた本人か?」「そそのかした側か?」「道具を渡しただけか?」と役割で整理するとミスが減ります。
③ 未遂犯:どこから“着手”といえるか
未遂犯の事例問題では、「準備」なのか「実行に着手した」のかがポイントになります。
「道具を買った時点ですぐ未遂になる」「家を出た時点で未遂になる」など、準備段階と未遂を混同してしまう。
- 予備:犯罪をしようとして準備している段階(包丁を買う、現場を下見するなど)
- 未遂:実行行為の一部に踏み出した段階(被害者に包丁を振りかざす など)
- 既遂:予定していた結果が実際に生じた段階
「被害者側から見て、現実的な危険が始まっているか?」 を基準に、“着手”かどうかを判断するのが試験的な読み方です。
第5章|受験生が陥る刑法のミス3つと対策(NG→OK比較)
刑法の事例問題で点を落とす受験生の多くは、 条文の知識ではなく“読み方の順番”でつまずいています。 ここでは公務員試験でよく見られる3つのミスと、その解決策をNG→OK形式で整理します。
① 三段階審査(構成要件→違法性→有責性)を飛ばす
「これは正当防衛っぽい」「これは悪いことしてる」 と印象だけで判断してしまう。
どんな犯罪でも ①構成要件 → ②違法性 → ③有責性 の順に機械的にチェックする。
・「外側(行為)→中身(違法)→責任(人)」の順番で読む
・順番を決めておくと迷う選択肢が激減します
② 正当防衛の「やりすぎ」基準を正しく理解していない
「攻撃されたなら反撃は何でもOK」と 防衛行為の相当性を無視してしまう。
正当防衛は
- 急迫不正の侵害
- 防衛意思
- 防衛行為の相当性(やりすぎNG)
「攻撃 > 防御」になっていないか? とイメージして考えると判断が安定します。
③ 予備・未遂・既遂の区別が曖昧(特に“着手”)
「道具を買った=もう未遂」 「家を出た=未遂」など、 準備と着手を混同してしまう。
着手とは、 “被害者側から見て危険が現実化した段階”。 その前の準備行為は予備にとどまる。
・予備=準備、未遂=実際に危険が向けられた段階
・図解の「予備→着手→既遂」を思い出すと迷わない
第6章|スタディングで刑法を最短攻略する方法
刑法は、「判断の順番」さえ身につけば一気に点が伸びる実力科目です。
その一方で、独学だと「どの順番で考えればいいのか」「事例をどう読めばいいのか」が分からず、
伸び悩む受験生も多いのが実情です。
そこでおすすめなのが、スマホで完結するスタディング公務員講座です。
◎ 刑法×スタディングは「事例×解説×復習」がワンセット
刑法はこの「理解 → 事例演習 → 復習」の回転数がそのまま得点に直結します。 スタディングなら、このサイクルをすべてオンラインで回せます。
① 講義で「三段階審査」と頻出論点を一気に整理
スタディングの刑法講義では、 構成要件 → 違法性 → 有責性の三段階審査をベースに、 故意・過失、正当防衛、共犯、未遂犯などの頻出論点を体系的に整理してくれます。
- 独学で条文を読んでもイメージが湧かない
- 正当防衛や共犯の「判断の流れ」がわかりにくい
- 判例ベースの話をかみ砕いて説明してほしい
② 本試験レベルの事例問題で「読み方の型」を身につける
公務員試験の刑法は、短い事例を読んで 「どの犯罪が成立するか?」「正当防衛が認められるか?」を判断させる問題が多いです。 スタディングの問題演習では、こうした本試験レベルの事例問題を スマホでテンポよく解いていくことができます。
- 故意・過失の有無を問う事例
- 正当防衛・緊急避難の成立/過剰防衛の判断
- 教唆・幇助・正犯の区別
- 未遂犯・予備罪・既遂のライン
解説では「①構成要件 → ②違法性 → ③有責性」の順に検討する流れが示されるので、 そのまま自分の“答案思考の型”としてコピーできます。
③ AI復習で「忘れかけた論点」を自動的に出題
刑法は、一度理解したつもりでも時間が経つと 「あれ、正当防衛の要件ってどうだったっけ?」と抜けてしまいがちです。 スタディングのAI復習は、あなたが間違えた問題や時間が空いた論点を 優先的に出してくれるので、“忘れかけた頃にちょうどいい復習”ができます。
- 苦手な論点(正当防衛・共犯など)が何度も出てくる
- 「どこが弱点か」を自動で分析してくれる
- スキマ時間に5問ずつ復習できるので、忙しくても続けやすい
まとめ 刑法は「順番」と「事例」がカギ。スタディングで時短攻略
刑法は、
①三段階審査の順番を覚える
②頻出論点の事例に慣れる
③定期的に復習する
という3つを押さえれば、難しい理論を完璧に暗記しなくても合格点に届く科目です。
独学で一から事例集をそろえるのが大変だと感じる人や、 スマホでスキマ時間に効率よく刑法を仕上げたい人は、 スタディング公務員講座をうまく活用してみてください。
▶ スタディング公務員講座の詳細を見てみる第7章|まとめ(刑法は「順番」と「事例力」で勝てる)
公務員試験の刑法は、範囲こそ広いものの、 「考える順番が決まっている」「頻出論点が固定されている」 という特徴があります。
- 三段階審査(構成要件 → 違法性 → 有責性)で読む
- 正当防衛・共犯・未遂など頻出論点を優先
- 事例問題で“読み方の型”を体得
- 弱点論点はAI復習で繰り返し定着
この4つさえ押さえれば、刑法は初心者でも十分に得点源になります。