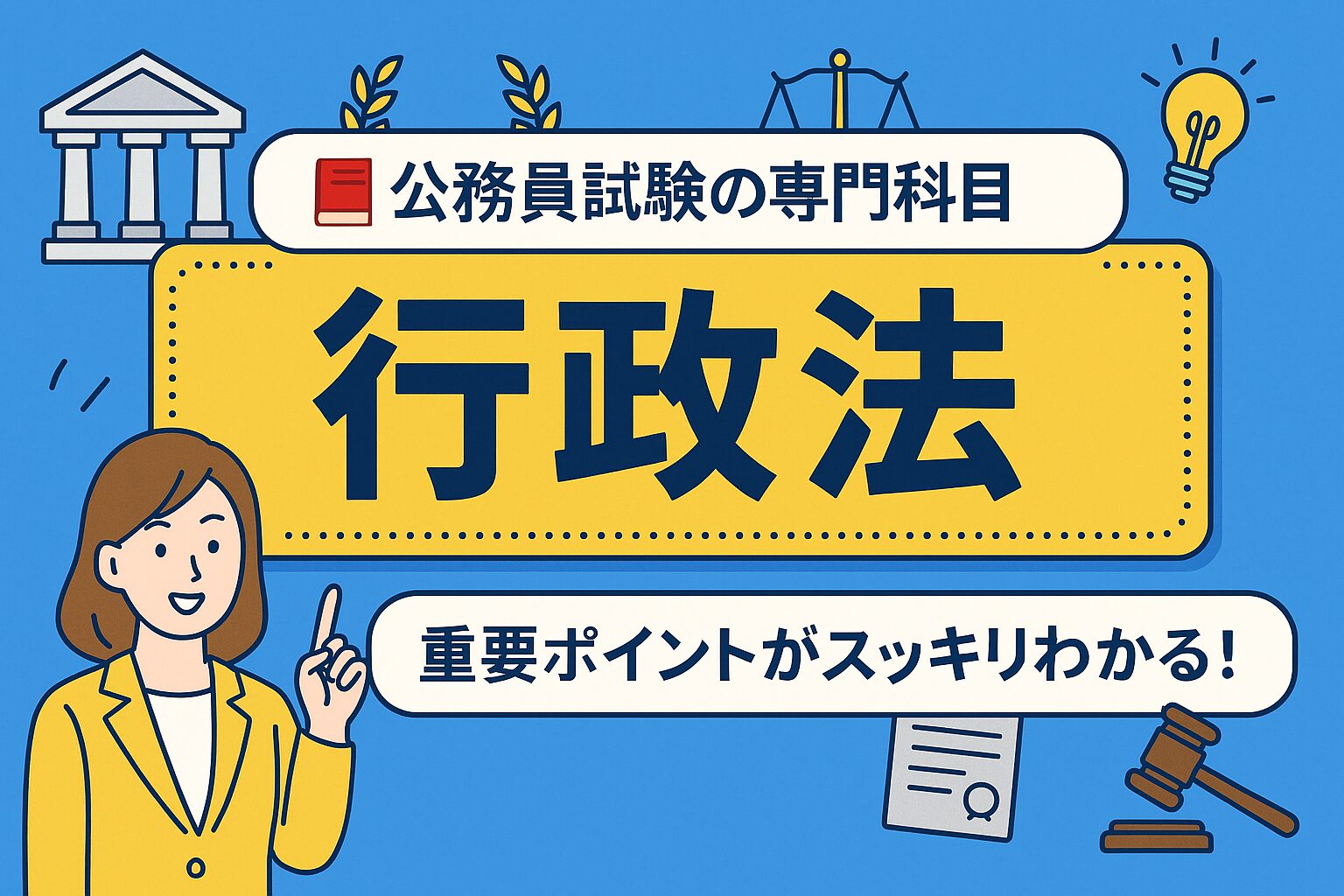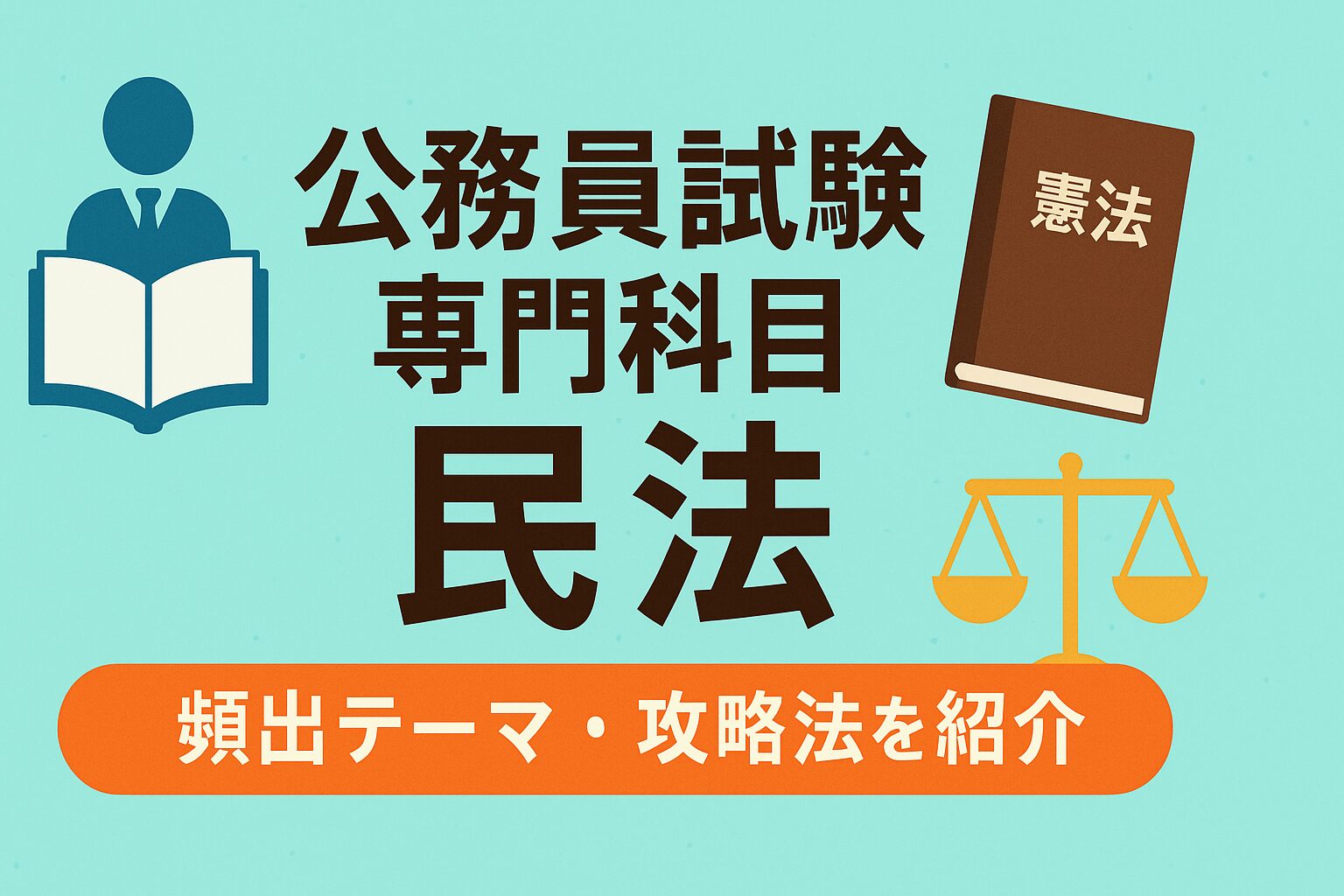第1章|公務員試験の行政法は何を勉強する?(出題範囲の全体像)
行政法は、公務員試験の専門科目の中でも“最重要科目”と呼ばれるほど頻出です。 まずは難しいイメージを捨てて、全体像を構造化して理解することが得点力UPの第一歩です。
概観 行政法は「4つの柱」で理解すると超わかりやすい
行政法はこの4つの柱で理解すると、問題文の読み方が劇的に変わり、得点が安定します。
① 行政作用法(行政行為・手続・義務付け)
行政行為(許可・認可・命令・禁止など)や、行政が国民に対してどう作用するかを扱います。 行政法の中で最頻出のメイン分野です。
- 行政行為の種類
- 行政行為の効力(公定力・執行力 等)
- 不利益処分の手続(通知・聴聞・弁明)
② 行政救済法(審査請求・取消訴訟)
行政により不利益を受けた国民を救うための制度を扱います。 審査請求・取消訴訟・国家賠償法は頻出中の頻出です。
- 行政不服審査法(審査請求)
- 行政事件訴訟法(取消訴訟・不作為訴訟)
- 国家賠償法(1条・2条)
③ 行政組織法(国・自治体がどう動くか)
国・地方公共団体・行政庁など、行政組織の構造を扱います。 比較的軽めですが、落としたくない基本問題が多い分野です。
- 行政庁とは?
- 権限委任・権限代理
- 自治体の組織構造
④ 行政手続法(通知・聴聞・理由提示)
行政が処分を行う際の手続きを定める法律です。 不利益処分の流れは毎年狙われます。
- 処分の事前通知
- 聴聞・弁明の機会
- 理由提示の義務
重要 行政法が“最重要科目”と言われる理由
- 出題数が多く、配点が高い
- 毎年似た論点が繰り返し出る(パターン化しやすい)
- 理解で差がつきやすく、得点しやすい
- 行政法の知識は他の科目(憲法・地方自治)と関連性が強い
第2章|まず押さえるべき行政法の基礎3つ(法律原理・行政行為・手続法)
行政法の理解で最初に押さえるべきポイントは 「法律による行政」「行政行為」「行政手続法」の3つです。 この3点を押さえておくと、後の頻出テーマがすべてつながります。
① 法律による行政の原理(超重要・最頻出)
国民に義務を課したり、自由を制限する場合には 「必ず法律の根拠(留保)」が必要です。 また、行政は法律に反する行為はできない(優位)という基本原則です。
| 法律の留保 | 国民の権利を制限するなら、必ず法律の根拠が必要 |
|---|---|
| 法律の優位 | 行政は、法律に違反することは絶対にできない |
② 行政行為とは?(効力・瑕疵・取消しが頻出)
行政行為は、行政が国民の権利・義務を直接変動させる「一方的な行為」です。 行政法の得点源であり、効力・取消し・瑕疵は超頻出です。
| 許可 | 本来禁止されている行為を例外的にOKにする(免許など) |
|---|---|
| 認可 | 当事者の合意に行政が「お墨付き」を与える(学校法人認可など) |
| 命令・禁止 | 行政が一方的に義務を課す(営業停止命令など) |
- 公定力:行政行為は「有効なものとして扱われる」
- 不可争力:一定期間を過ぎると争えない
- 執行力:義務を強制できる
③ 行政手続法|不利益処分の流れを理解する
行政手続法は、行政が何か処分をする前に どのような手続きを踏む必要があるかを定めた法律です。 特に「不利益処分」の流れは毎年出ます。
第3章|行政法の頻出テーマ3選(図解でスッキリ理解)
行政法の中でも、毎年ほぼ必ず出題される“鉄板テーマ”があります。 この章では、特に重要な「行政行為の効力」「不利益処分の流れ」「行政救済法」を図解で整理します。
① 行政行為の効力(公定力・不可争力・執行力)
行政行為には、成立した瞬間から特別な効力が生じます。 特に公定力・不可争力・執行力の3つは毎年登場します。
- 公定力:行政行為は「有効」なものとして扱われる(誤りがあってもすぐには無効にならない)
- 不可争力:争える期間(不服申立て期間)が過ぎたら争えない
- 執行力:行政が義務を強制できる(行政代執行・強制徴収など)
「行政行為の効力に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。」
② 不利益処分の流れ(通知→聴聞→理由)
行政法で超頻出なのが 不利益処分の手続の順番。 必ず「通知 → 聴聞 → 理由提示」の順で行われます。
③ 行政救済法(審査請求/取消訴訟/国家賠償)
行政救済法は、行政に対して不服申立て・訴訟・賠償請求を行うためのルール。 行政法の得点源であり、毎年必ず出題されます。
| 審査請求 | 行政庁に対して「処分を取り消してほしい」と申し立てる |
|---|---|
| 取消訴訟 | 裁判所に対して「その処分は違法なので取り消してほしい」と訴える |
| 国家賠償法 | 行政のミスで損害を受けた場合に損害賠償を請求する |
第4章|受験生がつまずく行政法のミス3つと対策
行政法は「用語が似ている」「流れを混同しやすい」という理由から、 間違いやすいポイントが決まっています。 この章では、受験生の典型的なミスを NG→OK の比較 でわかりやすく整理します。
① 行政行為の効力を混同する(公定力・不可争力・執行力)
公定力=「行政行為を争えないこと」だと思ってしまう。
公定力:行政行為はとりあえず有効として扱う。
不可争力:一定期間が過ぎたら争えない。
執行力:義務を行政が強制できる。
▼ ミスの理由: 公定力と不可争力の違いが曖昧なまま暗記しているから。
② 不利益処分の手続の順番を間違える
聴聞 → 通知 → 理由 と順番を入れ替えて覚えてしまう。
通知 → 聴聞(または弁明) → 理由提示 の順が絶対。
▼ ミスの理由: 行政手続法の条文を「なんとなく」覚えているだけ。
③ 行政救済法の“どこに申し立てるか”を誤解する
審査請求と取消訴訟を混同し、どちらも「裁判所」へ提出すると思ってしまう。
審査請求 → 行政庁へ申立て
取消訴訟 → 裁判所へ提起
国家賠償 → 裁判所へ請求
▼ ミスの理由: 「不服申立て」と「訴訟」の区別が曖昧。
第5章|スタディングで行政法を最短攻略する方法(PR)
行政法は一度理解すると一気に得点源になりますが、 独学だと“理解の壁”にぶつかりやすい科目でもあります。 スタディングは、この壁を最短で突破できる効率学習ツールです。
ルート 行政法を最短で得点源にする3ステップ
このルートは行政法の“理解 → 演習 → 記憶”の流れを最速で作ることができます。
① 講義で「抽象概念」をわかりやすく可視化
行政法は抽象的で理解が難しいと感じる受験生が多い科目です。 スタディングの講義では、行政行為・不利益処分・救済法などを 図解とアニメーションで“視覚的に理解”できます。
- 行政行為の種類・効力が一発で理解できる
- 不利益処分の流れを図で把握できる
- 救済法の仕組みを関係図で理解できる
② 演習で「出題パターン」を完全に身につける
行政法の問題は毎年同じパターンが繰り返し出ます。 スタディングの演習は、本試験レベルの選択肢が多数収録され、 「選択肢の癖」を読み取る力が身につきます。
- 行政行為の効力(公定力・不可争力)
- 不利益処分の流れ
- 取消訴訟・不作為訴訟の要件
- 国家賠償法1条・2条の違い
③ AI復習で「忘れない仕組み」を自動化
行政法は用語が多いため、放っておくと記憶が薄れます。 スタディングのAI復習は、 「あなたが忘れそうな箇所」を判別して自動で出題します。
- 間違えた問題が優先的に出てくる
- 忘却曲線に合わせて出題を自動調整
- スマホで5問ずつできるから継続しやすい
まとめ 行政法はスタディングで“短期間の得点源”になる
行政法は最初に理解の壁がありますが、 スタディングを使えば 「理解 → 演習 → 復習」のサイクルが完全自動化できます。
- 講義:図解で理解が早い
- 演習:本番形式でパターンを習得
- AI復習:忘れない仕組みが構築できる
第6章|まとめ(行政法は“構造理解”で一気に伸びる)
行政法は、最初は難しく感じる科目ですが、 「構造理解」を意識すれば得点が一気に安定する科目です。 毎年同じパターンが繰り返し出るため、短期間で得点源にできます。
- 行政法は4つの柱(作用法/救済法/組織法/手続法)で理解する
- 行政行為の効力・不利益処分・救済法は毎年の鉄板テーマ
- つまずきやすい論点は「NG→OK」で整理して覚える
- “理解→演習→復習”のサイクルを作ることが最速攻略の鍵
本記事で紹介した考え方を押さえておけば、行政法の問題文が 「読める → 解ける → 正答できる」に変わります。
▶ スタディング公務員講座を今すぐチェックする