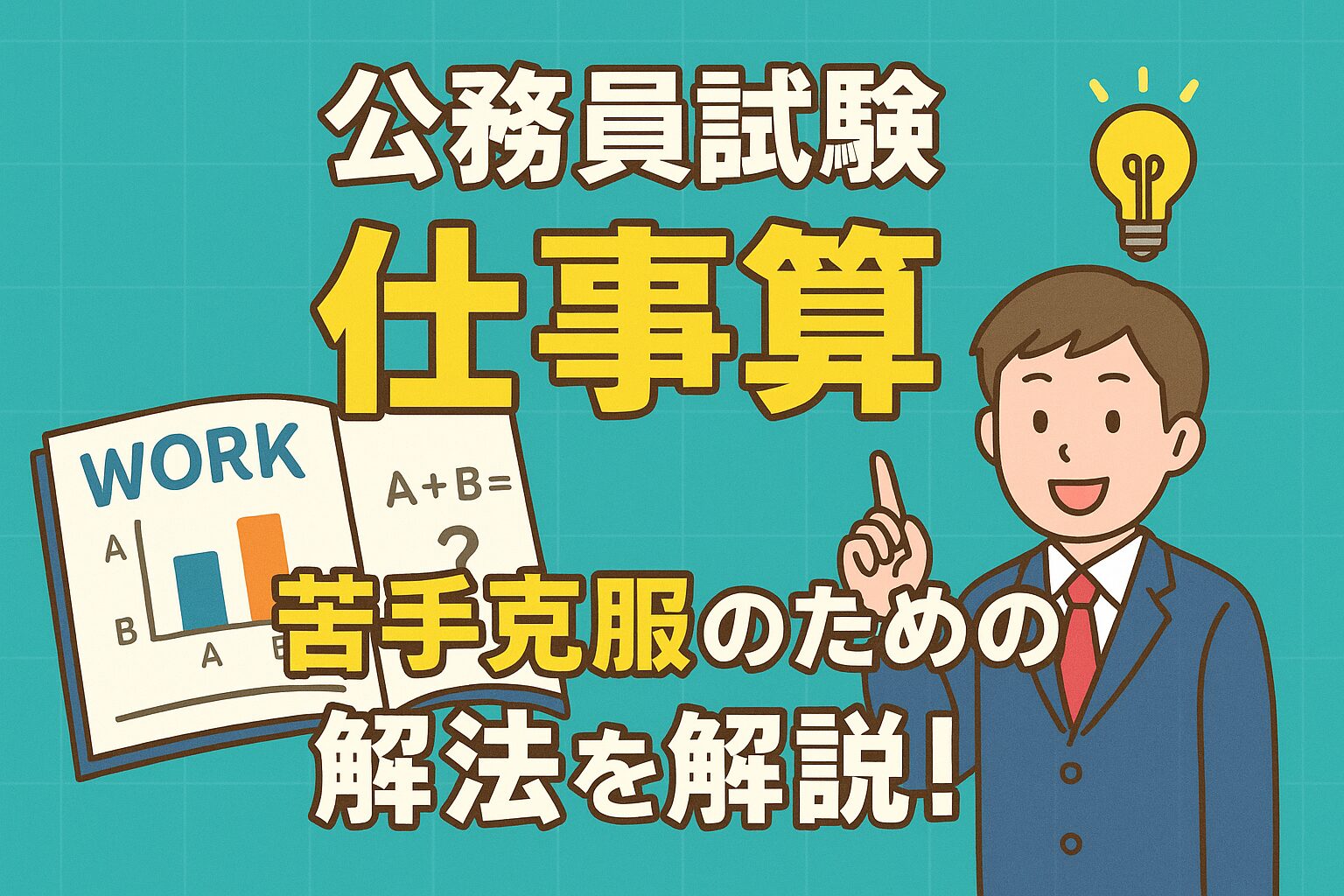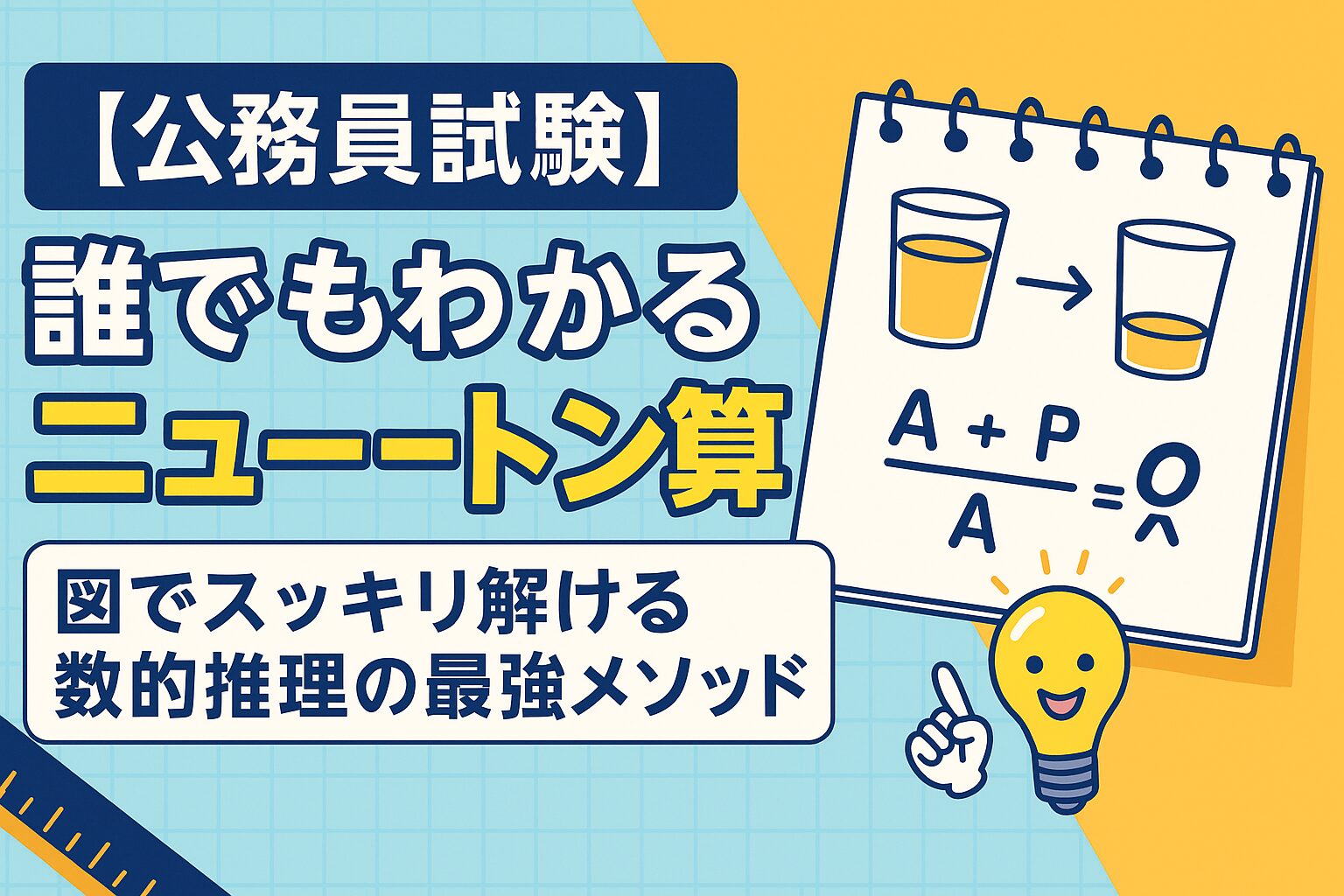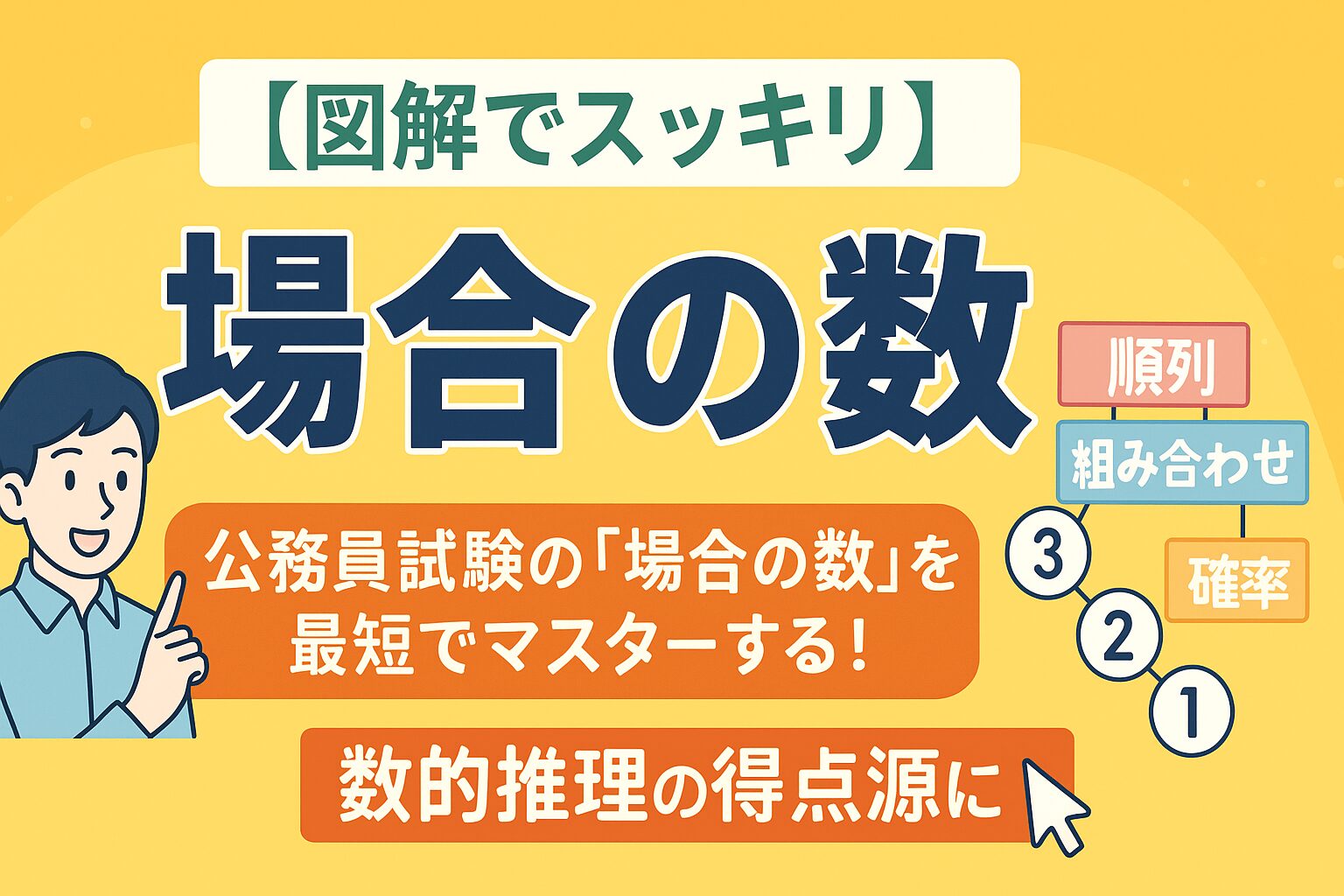はじめに:仕事算は“全体=1”で一気に解ける
公務員試験の数的推理で安定して得点したいなら、まず仕事算から。 「AさんとBさんが一緒に作業」「途中で入れ替え」「一部だけ担当」など、実務に近い設定で頻出です。 コツは、1つの仕事を1(全体)とおき、単位時間あたりの仕事量で比較すること。これだけで式作りがシンプルになります。
- ・「全体=1」「仕事量=速さ×時間」の基本がサッとわかる
- ・よく出る4パターン(協力・交代・分担・逆算)の型を習得
- ・暗算を助ける比・最小公倍数の使い方を身につける
仕事算が得点源になる理由
文章量は多くても、構造は毎回同じ。 「1日あたり(1時間あたり)どれだけ進むか?」を足し引きするだけで、協力でも交代でも同じフレームで解けます。 つまり、型を覚えれば初見でも方針が即決、計算もミスが減ります。
Aは6日、Bは9日で仕事を終える。2人なら? → 1日の合計=1/6+1/9=5/18 → 全体=1だから 1÷(5/18)=3.6日。
以降は、基礎→頻出パターン→例題→ミス対策→勉強法の順で、スマホの流し読みでも再現できる形で解説します。 演習は動画+AI復習が強いスタディング公務員講座を活用すると、短期間で得点が安定します。
仕事算の基本を理解しよう
仕事算の根本は、「全体=1」という考え方です。 つまり、どんなに大きな作業でも、ひとつの仕事を「1」として扱うことで、 仕事量=仕事の速さ×時間 という式に整理できます。 このフレームを覚えれば、協力・交代・分担など、どんな問題も同じ形で解けるようになります。
1日あたり(単位時間あたり)の仕事量を意識しよう
たとえば「Aさんは6日で終える」「Bさんは9日で終える」とき、 1日に進む量は次のように表せます。
| 作業者 | 全体を終える日数 | 1日あたりの仕事量 |
|---|---|---|
| A | 6日 | 1/6 |
| B | 9日 | 1/9 |
2人で同時に作業すれば、1日の進みは 1/6+1/9=5/18。 つまり、18 ÷ 5 = 3.6日で仕事が完了します。 このように「全体=1」で考えると、複雑な問題も分数計算でスッキリ整理できます。
- ・「全体=1」にすることで、どんな作業も同じ土俵で比較できる
- ・「速さ」と「時間」の関係が直感的に理解できる
- ・分数を使うと、協力・交代・残り作業の式をまとめやすい
図でイメージしてみよう
下のように、「進んだ部分」を線で可視化すると、比の関係がつかみやすくなります。 Aが1日に1/6進み、Bが1日に1/9進むなら、 Aの方が速く、同じ時間でより多く進むことが一目でわかります。
📊───────────────────────────────
A:■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■(6日で完了)
B:■■■■■■■■■■■■■■■■(9日で完了)
→ 一緒に進めば、毎日合計5/18ずつ進む!
このように、「全体=1」「単位時間あたり」「合計で足す」だけで、 ほとんどの仕事算は解けるようになります。 次章では、実際に出題されやすい4パターンを分類して、型として整理していきましょう!
よく出る4つの問題パターン
仕事算の問題は、ほぼすべて次の4パターンに分類できます。 各パターンで「全体=1」「単位時間あたりの仕事量」を使い分けることがポイントです。 これを理解すれば、初見の問題でも瞬時に型が見抜けるようになります ✨
① 協力型(最も基本)
Aさん・Bさんが一緒に作業する定番タイプです。 「一緒に行えば何日で終わる?」という問題は、足し算で解けます。
Aが6日、Bが9日で仕事を終えるとき、協力すると? → 1日あたりの合計=1/6+1/9=5/18 → 全体=1 ÷ (5/18)=3.6日
② 交代型(途中で入れ替わる)
Aが最初の〇日作業し、そのあとBが続きます。 進んだ分を合計して全体=1に届くように式を立てます。
Aが2日、Bが3日作業して仕事が終わった。 A単独なら6日、B単独なら9日。 → 2×(1/6)+3×(1/9)=1/3+1/3=2/3 → あと1/3残り! という風に部分的に足して考えます。
③ 分担型(一部をA、残りをB)
「Aが全体の〇割を担当、残りをBが担当」タイプ。 Aの担当部分=全体×割合 で計算し、それぞれの作業時間を足します。
Aが全体の60%を担当(単独なら6日)、Bが残り40%(単独なら8日) → A=0.6×6=3.6日、B=0.4×8=3.2日 → 合計=6.8日
④ 逆算型(人数・時間を求める)
「全体が〇日で終わったとき、A単独なら?」のように、 未知の時間・人数を求める逆算タイプです。 比を使うと暗算が早くなります。
Aが単独なら6日、Bが単独なら9日。2人で3日で終えた。 → (1/6+1/9)×3=5/18×3=5/6(全体の5/6)→あと1/6残り! → もう1人Cが入って1日で終える → Cの速さ=1/6。
これら4パターンをマスターすれば、仕事算の9割は攻略完了です。 次章では、それぞれを実践例題でステップ解説しながら、暗算のコツも紹介します!
例題でステップ解法をマスターしよう
理論を覚えただけでは「本番で解けない」ままです。 ここでは、実際の公務員試験でも出やすい2つのタイプを使って、ステップ解法を身につけましょう 💪
例題①:協力型の基本
Aさんは6日で仕事を終える。Bさんは9日で終える。 では、2人で協力すると何日で終わる?
解き方ステップ
- 全体=1とおく。
- Aの1日あたりの仕事量=1/6、Bの1日あたり=1/9。
- 協力すると1日の合計=1/6+1/9=5/18。
- 全体を1とするので、1÷(5/18)=3.6日で完了。
「速さを足す→時間を短く」になるのが基本。 公倍数(6と9→18)を使うと暗算がスムーズになります。
例題②:交代型(途中で入れ替わる)
Aさんは単独で6日、Bさんは単独で9日で仕事を終える。 最初の2日をAが行い、残りをBが行ったら、全部で何日かかる?
解き方ステップ
- 全体=1。
- Aが2日作業 → 2×(1/6)=1/3 進む。
- 残りは 1−1/3=2/3。
- Bの1日あたり=1/9。 2/3 ÷ 1/9=2/3×9/1=6 → Bが6日で残りを終える。
- 合計=A2日+B6日=8日。
残り量を出したら「÷速さ」で時間を出す。 割るのではなく「×逆数」で計算するのが鉄則!
例題③:逆算型(人数を求める)
Aさんは単独で6日、Bさんは単独で9日で仕事を終える。 2人で3日作業後、Cさんが加わって残りを1日で終えた。 Cさん単独なら何日で仕事を終える?
解き方ステップ
- 2人で3日間: (1/6+1/9)×3=(5/18)×3=5/6 進む。
- 残り=1−5/6=1/6。
- Cを含めた3人の速さをxとする。 1/6=x×1 → x=1/6。
- したがって、C単独なら6日で終える。
①「全体=1」→②「進んだ量」→③「残り」→④「式で整理」 この流れが仕事算の黄金パターンです ✨
ステップ化して整理すれば、複雑な数的推理問題でも迷わず進めます。 次章では、よくあるミスと解答精度を上げる対策を整理しましょう。
間違いやすいポイントと対策
仕事算はパターンが明確な反面、ケアレスミスで点を落とす人が非常に多い分野です。 下の表で、受験生が特にハマりやすい落とし穴と、その防止策を整理しておきましょう 💡
| よくあるミス | 原因 | 対策 |
|---|---|---|
| ① 全体を1に設定し忘れる | 割合や分数の基準がズレる | 最初に「全体=1」を書き出してから式を立てる |
| ② 協力と交代を混同する | 「同時に」「交代で」を読み飛ばす | 問題文の動詞にマーカー:「一緒に」→足す、「交代で」→区切る |
| ③ 残り仕事量を間違える | 進んだ分を引き忘れる/引きすぎ | 「残り=1−進んだ分」を都度明示 |
| ④ 逆算で分母・分子を逆にする | 速さと時間の扱いが逆転 | 「仕事量=速さ×時間」を常に意識 |
| ⑤ 単位(時間・日)を揃えない | 1時間・1日などが混在 | 必ず「単位を統一」してから計算する |
公務員試験の仕事算は「表現トラップ」が頻出です。 「同じ仕事」「2倍の速さ」「残り半分」などの言い換えに惑わされないよう、必ず式で整理してから手を動かしましょう。
精度を上げる3ステップチェック
- ① 全体を1に置いた?
- ② 足す/引く方向は正しい?
- ③ 単位と比の扱いは統一されている?
仕事算は「読む→整理→計算」の3段階で確実に得点できます。 ミスの9割は「読み飛ばし」と「早とちり」です。 慣れれば暗算でも処理できるので、焦らず型通りに進めましょう ✍️
仕事算を得点源に変える勉強法
「仕事算」は、一度理解すれば一気に得点源になる分野です。 本番で安定して点を取るには、次の3ステップで学習を進めるのが最短ルートです 💪
① 理解フェーズ:「型」を頭に入れる
まずは「全体=1」「単位時間あたり」「協力=足す/交代=区切る」という基本3原則を、 図と表で覚えましょう。 紙に書いて整理するより、視覚的に理解するのがポイントです。
② 定着フェーズ:過去問で型を実戦投入
型を理解したら、すぐに過去問演習へ。 公務員試験では「協力」「交代」「分担」「逆算」が交互に出るため、 パターンごとに3問ずつ解くのがおすすめです。
1日目:協力型+交代型
2日目:分担型+逆算型
3日目:総まとめ(4パターン混合)
このサイクルを繰り返すことで、数的推理全体のスピードが向上します。 特に仕事算→ニュートン算→速さ算は構造が似ており、連鎖的に理解が深まります。
③ 実戦フェーズ:AI復習と時間管理
実際の試験では、1問にかけられる時間は約2分。 解答スピードを上げるには、「どの型か」を即断できるようになることが重要です。 スタディングではAIが間違いパターンを分析し、自分専用の復習リストを自動生成してくれます。
④ 仕事算を軸に、数的推理を広げる
仕事算は、速さ算・ニュートン算・濃度算に直結しています。 この分野をマスターすると、数的推理の半分以上をカバーできます。 「仕事=速さ×時間」の理解を土台に、他の分野もスムーズに解けるようになります。
まとめと次の学習ステップ
ここまで、仕事算の基礎から応用・勉強法までを一気に整理してきました。 公務員試験で得点を安定させるためのポイントを、もう一度おさらいしましょう ✅
- ・全体=1 を設定して「仕事量=速さ×時間」で考える
- ・協力=足す/交代=区切る/残り=1−進んだ分 で整理
- ・図と表を使うと混乱を防げる
- ・比や分数の扱いは「速さ算」「ニュートン算」と同じ構造
次に学ぶべきテーマ
仕事算をマスターしたら、次は「ニュートン算」「速さ算」へ進みましょう。 これらは考え方の土台が共通しており、連続で学ぶと理解が倍速で進みます 🚀
この順番で学ぶと、公式の暗記に頼らず「構造理解」で得点できるようになります。
次の行動:実戦トレーニングを始めよう
理論を読んだだけでは、試験本番では点が取れません。 今日学んだ内容を「問題を解いて使う」ことで、初めて本物の実力になります。 スタディングの公務員講座なら、スマホで数的推理の全パターンをAIが自動復習し、 弱点をピンポイントで克服できます。
関連記事(内部リンク)
公務員試験の数的推理は、最初は難しく感じても、 「型を理解 → 問題を解く → 弱点を分析」の流れで確実に点が取れるようになります。 あなたの努力が実を結ぶよう、スタディングと一緒に一歩ずつ前進していきましょう 🌱