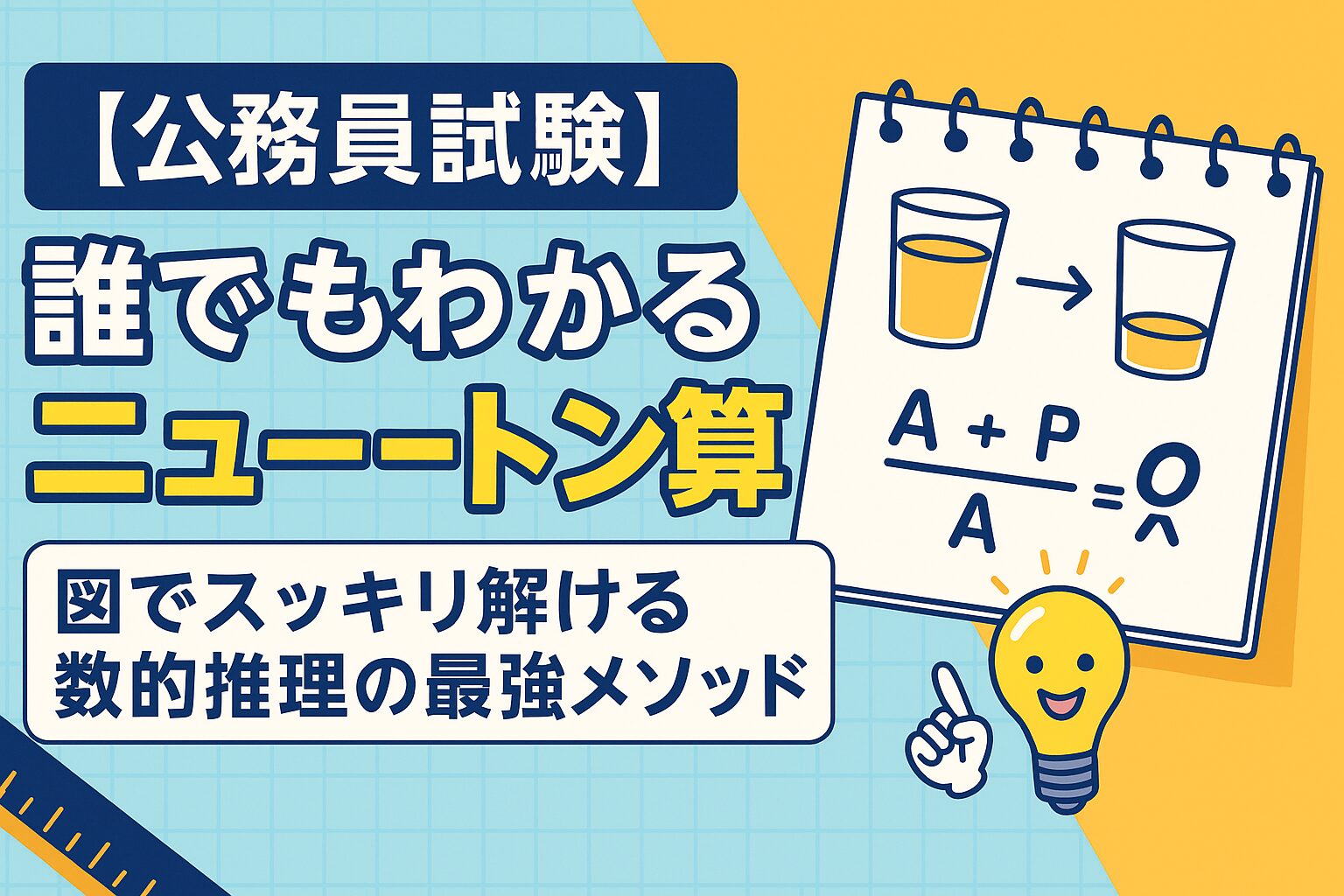はじめに:覆面算・魔法陣は“論理力”のド真ん中
公務員試験の数的推理で毎年ねらわれるのが、文字が数字を表す覆面算と、 たて・よこ・斜めの合計が等しくなる魔法陣。計算力よりも 条件整理・一貫性チェック・消去法が問われるため、思考の順序を持っている受験生ほど有利です。
- ・覆面算:位どり→繰上がり/繰下がり→候補絞りの3手順を習得
- ・魔法陣:中心と対角の関係から最短で埋める型を理解
- ・図・表・チェックリストでスマホ流し読みでも再現できる設計
まず“考え方の型”を体に入れる
覆面算は「同じ文字=同じ数字」「先頭は0不可」などの制約から 矛盾を排除していくゲーム。魔法陣は和の合計固定を軸に、 中心→対角→辺の順で埋めるのが近道です。どちらも「公式暗記」ではなく 手順の固定化が得点化の鍵になります。
MAG+IC=MATH(覆面算)
→ 先頭Mは繰上がりで増えないと成立しない…など、位ごとに矛盾チェック!
以降の章では、基礎→解法ステップ→例題→ミス対策→勉強法の順に、 すぐ真似できる型で解説します。演習は動画+AI復習で回すと定着が段違いです。
覆面算の基礎を理解しよう
覆面算(ふくめんざん)は、数字の代わりに文字や記号を使って表された計算式を解く問題です。 一見パズルのように見えますが、実は数的推理の論理力・条件整理力を測る代表的な出題です。 まずは、ルールと基本構造をしっかり押さえましょう。
① 覆面算とは?
各文字が0〜9の数字を表しており、同じ文字は同じ数字・異なる文字は異なる数字を意味します。 さらに、先頭の文字が0になることはありません。 これらの条件を踏まえて、「どの文字がどの数字か」を筋道立てて推論していくのが基本です。
AB+CD=EFG のような式で、 桁ごとの関係(繰り上がり・繰り下がり)を考えながら数字を特定します。
② 主な出題パターン
- 🔹 加算型:AB+CD=EFG(足し算が最も基本)
- 🔹 減算型:ABC−DE=FG(借りの処理がポイント)
- 🔹 乗算型:A×BC=DEF(段階的に桁を合わせて検証)
③ ルールと注意点
- ・同じ文字は同じ数字、異なる文字は異なる数字
- ・先頭の文字に0は使えない
- ・繰り上がりや借りの有無を常にチェックする
- ・条件の矛盾がないかを逐一確認する
④ 整理のコツ:表と線分図を使う
計算だけに頼ると混乱しやすい分野です。 各桁の「繰り上がり・候補数字・確定数字」を表にまとめると、思考が可視化されて整理しやすくなります。
| 桁 | 繰り上がり | 文字 | 候補数字 |
|---|---|---|---|
| 1の位 | 0 or 1 | G | 3, 8 |
| 10の位 | 0 or 1 | F | 2, 7 |
次章では、覆面算を解くステップと具体的な例題を使って、 実際にどのように考えを進めるのかを体感していきましょう。
覆面算の解法ステップ(例題付き)
覆面算を正確かつスピーディーに解くためには、 「思考の順番」を固定することが大切です。 ここでは、最も頻出の加算型覆面算を題材に、 具体的な手順をステップごとに整理していきます。
① 手順①:位ごとに条件を整理する
まずは、右端(1の位)から順番に見ていきます。 加算や減算では“繰り上がり”が発生するため、 1桁ごとの計算を丁寧に分解して考えるのが鉄則です。
A B + C D = E F G 1の位:B + D → G(繰り上がりがあるか?)
10の位:A + C + (繰り上がり) → F
100の位:必要なら E に繰り上がりが加算される
✅ ポイントは「1桁ごとに条件を分ける」ことです。
② 手順②:繰り上がり・繰り下がりを考慮
覆面算でミスが多いのはこの部分です。 1の位の結果が10を超えたら、次の桁に繰り上がり=1が発生します。 逆に減算型では繰り下がりを加えることもあります。
③ 手順③:候補を表にして絞り込む
各文字に入る可能性のある数字を表形式にまとめます。 この時、矛盾が生じる組み合わせを消すことで、 残った候補が正答に近づきます。
| 文字 | 候補数字 | 理由 |
|---|---|---|
| A | 3, 4 | 繰り上がりを含めて成立する範囲 |
| D | 7, 8 | B + D = 15 となる組み合わせ |
- ① 各桁の条件を分けて書く
- ② 繰り上がり/繰り下がりを反映
- ③ 矛盾がないか都度チェック
- ④ 候補を絞り込んで最終確定
④ 実践例題:A+B=Cパターンを解く
AB+AB=BCD のとき、A・B・C・Dの組を求めよ。
考え方:
① 同じ数字ABを2回足しているため、繰り上がりが発生する可能性が高い。
② 1の位:B+B → D+繰り上がり。 → B+B=D+10×繰り上がり。
③ 10の位:A+A+(繰り上がり)=C+10×(新しい繰り上がり)。
④ 条件を整理すると、A=4, B=7, C=9, D=4 が成立。
✅ よって答えは A=4, B=7, C=9, D=4。
⑤ スタディングで“解法の型”を体で覚える
覆面算は練習量がものを言う分野です。 スタディング公務員講座では、AI復習機能で「間違えた桁ごとの思考」を自動的に再出題。 図付きの動画で手順を復習できるため、短期間で論理の型を定着させられます。
- ・講師が「桁ごとに整理する方法」を実演解説
- ・AIが苦手パターンを分析し、繰り返し出題
- ・スマホで短時間復習できる設計
魔法陣の仕組みと考え方
魔法陣とは、縦・横・斜めのすべての合計が同じになるように数字を配置するパズル型の問題です。 数的推理では「規則性」「構造の見抜き方」を問う代表的なテーマとして、出題頻度も高い分野です。 一見難しそうですが、中心と対角の関係を理解すれば一気に解けるようになります。
① 魔法陣とは?基本ルールを理解する
魔法陣では、すべての行・列・斜めの合計が等しいというルールがあります。 例えば3×3の魔法陣では、縦3列・横3行・2本の斜めラインの合計が同じになります。
| 8 | 1 | 6 |
| 3 | 5 | 7 |
| 4 | 9 | 2 |
➡ どの方向でも合計は「15」になります。
② 基本構造:中心が“全体の平均”になる
3×3魔法陣の最大のポイントは、中央の数が全体の平均値であること。 つまり、1〜9の合計が45なので、その平均は5。したがって中央は必ず「5」になります。 これを利用すれば、他のマスを順に埋めることができます。
③ 3×3魔法陣の作り方(順序を守れば簡単)
- ① 1〜9の数字を使う(1つずつ使用)
- ② 中心に「5」を置く
- ③ 斜め・縦・横がすべて合計15になるように調整
1. 中央=5(固定)
2. 対角線のペアは (2,8), (3,7), (4,6) など平均5になる組み合わせ
3. ペアを対称的に配置すれば完成!
④ 応用:4×4魔法陣の考え方
4×4以上の魔法陣では、ブロック構造を意識します。 各行・列・斜めで合計が同じになるように、「和の均衡」を保つ配置を作るのがポイントです。
- ・数列の合計を行数で割り、目標の合計を求める
- ・中心ブロック(2×2)でバランスを取る
- ・対角線上のペアを反転配置すると完成しやすい
⑤ 実践例題:3×3魔法陣を完成させよう
次の魔法陣を完成させよ。
| 8 | ? | 6 |
| ? | 5 | ? |
| 4 | ? | 2 |
解説:
すべての合計が15になるように、中央を基準に配置。 → 答えは中央の上下左右がそれぞれ (1,7,3,9) 。
魔法陣問題は、構造とパターンを覚えれば得点源になります。 次章では、覆面算・魔法陣に共通する「よくあるミスと対策」を整理していきましょう。
よくあるミスと対策
覆面算・魔法陣のどちらも、ルール自体はシンプルですが、解く手順を誤ると混乱しやすい分野です。 ここでは、公務員試験で多くの受験生が陥る代表的なミスと、その防止策をセットで紹介します。
① 思考の順序を守らない
多くの人が「なんとなく」数字を入れて試してしまうのが典型的な失敗です。 覆面算では必ず右の桁から左へ、魔法陣では中心から外側へと考える順番を固定しましょう。
② 条件の書き忘れ・抜け漏れ
「同じ文字=同じ数字」「合計が一定」などの基本ルールを途中で見失うと、 最後に辻褄が合わなくなります。条件は表やチェックリストにまとめておくと安心です。
✅ 同じ文字に同じ数字を入れているか?
✅ 先頭が0になっていないか?
✅ 繰り上がり/繰り下がりの有無を反映しているか?
✅ すべての行・列・斜めが同じ合計になっているか?(魔法陣)
③ 繰り上がり・借り忘れ
特に覆面算で多いのが「繰り上がり」「借り」の見落としです。 1桁ずつ検証しながら、繰り上がりをメモする癖をつけましょう。
④ 計算を暗算で済ませてしまう
速さよりも「見落とし防止」が重要です。暗算だけで進めると、 思考が飛びやすくミスを招きます。必ず紙に書いて可視化しましょう。
⑤ 魔法陣の構造を丸暗記している
魔法陣を「覚えて」解こうとするのも危険です。 中心が平均である理由や、対角のバランス関係を理解しておけば、 応用問題にも対応できます。
⑥ 演習量不足(典型パターンを知らない)
覆面算・魔法陣は、出題パターンがある程度固定されています。 スタディングではAIが自動で苦手傾向を分析し、 「あなた専用の復習セット」を生成してくれるため、無駄のない演習が可能です。
⑦ 試験本番で焦って読み間違える
難問よりも「凡ミス」で落とす受験生が多いのがこの分野。 試験中は必ず問題文の条件を声に出さず心で読み直す習慣をつけましょう。
- ・焦らず桁を分けて思考する
- ・メモは「小さく・多く・丁寧に」
- ・最後の1分で「整合性チェック」を行う
これらのミスを防げば、数的推理での安定得点が可能になります。 次章では、効率的に得点を伸ばすための勉強法と復習戦略を紹介します。
勉強法とスタディング活用法
覆面算・魔法陣のような数的推理問題は、“解法の再現性”が得点のカギです。 「理解→練習→反復→定着」の4ステップを意識して学ぶことで、どんな形式の問題にも対応できるようになります。
① 理解段階:まずは“型”を覚える
まずは問題を「構造」で捉えることが大切です。 公式や数字の暗記ではなく、“どうしてそうなるのか”を言語化して整理しましょう。
- ・覆面算:右→左の桁順で思考を固定
- ・魔法陣:中心→対角→外枠の順で整理
- ・「なぜ?」を3回問い直すと理解が深まる
② 練習段階:1日1題×パターン別で鍛える
解法を覚えたら、似たパターンを複数解くことで手順を体に染み込ませます。 公務員試験では、同じ考え方で解ける問題が形式を変えて出ることが多いため、 “幅広く浅く”より“狭く深く”練習するのが効率的です。
・覆面算:繰り上がり型/減算型/繰下がり型
・魔法陣:3×3/4×4/変形タイプ(和がズレる条件つき)
③ 反復段階:間違いノートを作る
間違えた問題は「どの手順で間違えたか」をメモしておきましょう。 特に覆面算では「繰り上がりの記入忘れ」、魔法陣では「合計の再確認漏れ」が頻出です。 ノートに“自分専用の注意点リスト”を作ることで、再発防止につながります。
④ 定着段階:AI復習で自動リマインド
せっかく理解しても、時間が経つと忘れてしまうのが人間。 スタディングの公務員講座なら、AIが自動で復習スケジュールを作成し、 間違えたテーマを効率的に出題してくれます。
- ・AI復習機能で苦手テーマを自動分析
- ・スマホでも解説付き動画を視聴可能
- ・短時間で「理解→演習→復習」の流れを回せる
⑤ 学習スケジュール例(1週間プラン)
| 曜日 | 学習内容 |
|---|---|
| 月 | 覆面算(基本)+1題演習 |
| 火 | 魔法陣(構造理解+3×3) |
| 水 | 覆面算(繰り上がりパターン) |
| 木 | 魔法陣(4×4応用)+チェックテスト |
| 金 | 総復習+苦手ノート見直し |
| 土 | 過去問1セット(スタディング使用) |
| 日 | AI復習+ミス分析 |
⑥ 最後に:地道な反復が“得点の再現性”を生む
覆面算も魔法陣も、公式暗記ではなく考え方の型を固定することが最重要です。 問題ごとに考え方を変えず、同じ手順で繰り返せば、どんな問題も「見た瞬間に方針が立つ」ようになります。 継続は力なり。AI学習と人の思考を融合させ、最短合格を目指しましょう。