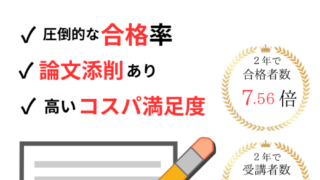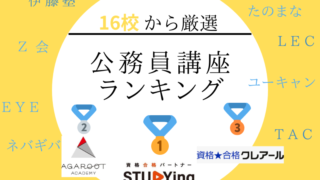捨て科目をうまく作れば、
合格率は飛躍的に向上する…
公務員試験で「捨て科目」をどうしようか迷っている方へ。
この記事では、地方上級などの専門試験において「捨ててもいい科目」を紹介しています。
どれを捨てるかは自分の戦略に合わせて考えてください。
併せて、捨ててはいけない「押さえるべき科目」も紹介します。
・公務員専門試験に捨て科目が必要な理由
・捨て科目を選ぶ基準
・各試験ごとの捨て科目
そもそも公務員試験に捨て科目は必要なの?

早速ですが質問です。
筆記試験で不合格になる人の特徴って分かりますか…?
答えは【真面目な人】です。
真面目な人ほど落ちるのが公務員試験なのです。
なぜ真面目な受験生が落ちるのか…
その理由は・・・
「真面目な人は全科目をまんべんなく勉強しようとしてしまうが、そうやってすべてをしようとすると絶対に時間が足りないから」
手を広げすぎて、重要部分が疎かになる。
その結果、解けるはずの問題で凡ミスして、不合格に直結するわけです。
予備校は過剰な授業とテキストで全て勉強させようとするので注意が必要です。
だってほとんどの人は、
そんなに時間がないですから。
限りある時間の中で考えなければいけません。
時間がない場合は、
・重要な科目に集中し、
・その他の科目は諦める
という戦略で戦うことが重要です。
闇雲に手を広げすぎるのも問題なんですよ。
捨て科目を選ぶ基準の考え方

さて、戦略の重要性を理解していただけたでしょうか?
しかし、何でも自由に捨ててもいいという訳ではありません。
絶対に捨ててはいけない「押さえるべき科目」もあるからです。
ここでは捨て科目を選ぶ基準を解説していきます。
・出題数
・難易度
出題数と難易度
捨て科目を作る際の判断基準は、主に科目ごとの出題数と難易度です。
効率よく勉強していくためには、出題数の多い科目を押さえて、出題数の少ない科目を優先的に捨てるべきです。
また、難易度の高い科目は習得するのに時間がかかるため学習効率はよくありません。
捨てる科目に迷った場合は、出題数を考慮しつつ難易度の高い科目も捨て科目として検討してください。
注意点
科目ごとの出題数については多少年度によって変わる可能性があります。
そのため、この記事は傾向の把握として見てください。
また、選択解答の場合は回答できる問題を選ぶことができるので、必須回答よりは柔軟に捨て科目を選ぶことができます。
ちなみに経済系の科目は、「ミクロ経済学」、「経済事情」など細かく科目分けせずに「経済原論」や「経済学」として、まとめて出題している自治体も多いです。
捨て科目のデメリットとリスク

捨て科目は万能ではない!リスクを把握しよう
捨て科目戦略は効率的な勉強法ですが、過信は禁物です。
出題傾向や難易度によっては「捨てたはずの科目」で意外と易しい問題が出題される場合があります。
また、併願先で捨てた科目が頻出科目だった場合は、大きな失点につながるリスクがあります。
戦略的に捨てつつも、リスク管理を意識しましょう。
出題傾向の変化で痛手を受ける場合も
公務員試験では、年度によって出題数が増減することがあります。
たとえば、前年は2問しか出なかった科目が翌年には4問に増えるケースも珍しくありません。
出題数が変動するリスクを考慮し、「絶対に捨てていい科目」は存在しないことを意識しましょう。
捨てすぎはNG!他科目でミスできなくなるデメリット
捨て科目を増やしすぎると、他の科目での凡ミスが致命的になります。
たとえば、40問中10問を捨ててしまうと、残りの30問で高得点を取らなければ合格できません。
1~2問の凡ミスで不合格になるリスクが高まるため、捨て科目は最低限に留めるのが鉄則です。
併願先との兼ね合いを考慮した捨て科目選び

併願先ごとの出題科目を把握しよう!
公務員試験は試験種ごとに出題科目が異なるため、併願を考慮した戦略が重要です。
例えば、地方上級では「民法」が頻出ですが、市役所では出題されない場合があるなど、試験ごとに傾向が異なります。
捨て科目を選ぶ際は、併願先で頻出になる科目は避けるようにしましょう。
併願する場合に捨ててはいけない科目
併願先で頻出する科目は、たとえ苦手でも捨てるべきではありません。
たとえば、民法・行政法・経済原論などは、多くの試験で出題される重要科目です。
これらの科目を捨てると、他試験でも致命的な失点になるため要注意です。
効率的な戦略:複数試験で使える科目を優先する
併願を考慮する場合は、複数試験で使える科目を優先的に対策しましょう。
例えば、憲法・民法・行政法などは地方上級・市役所・国家一般職のどの試験でも頻出です。
「捨てる科目は1試験でしか出ないもの」を選ぶことで、効率的に併願対策ができます。
地方上級の押さえる科目・捨て科目

地方上級試験で、紹介するのは以下の3つの試験です。
① 地方上級(全国型)
② 地方上級(関東型)
③ 地方上級(中部・北陸型)
出題数と難易度
出題数は各自治体によって多少の違いがあります。
| 科目 | 全 国 | 関 東 | 中部北陸 | 難易度 |
|---|---|---|---|---|
| 政治学 | 2 | 2 | 2 | ★★★☆☆☆ |
| 行政学 | 2 | 2 | 2 | ★★★☆☆☆ |
| 憲法 | 4 | 4 | 5 | ★★☆☆☆☆ |
| 行政法 | 5 | 5 | 8 | ★★★★★☆ |
| 民法 | 4 | 6 | 7 | ★★★★★★ |
| 刑法 | 2 | 2 | 2 | ★★★★☆☆ |
| 労働法 | 2 | 2 | 2 | ★★☆☆☆☆ |
| ミクロ経済学 | 5 | 7 | 5 | ★★★★★☆ |
| マクロ経済学 | 4 | 5 | 3 | ★★★★★☆ |
| 経済政策 | 0 | 2 | 2 | ★★★★☆☆ |
| 経済史 | 0 | 1 | 0 | ★★★☆☆☆ |
| 経済事情 | 0 | 0 | 2 | ★★★☆☆☆ |
| 経営学 | 2 | 2 | 0 | ★★★☆☆☆ |
| 財政学 | 3 | 4 | 4 | ★★★★☆☆ |
| 社会政策 | 3 | 3 | 2 | ★★☆☆☆☆ |
| 国際関係 | 2 | 3 | 2 | ★★★★☆☆ |
| 社会学 | 0 | 0 | 2 | ★★★☆☆☆ |
| 合計 | 40 | 50 | 50 | – |
関東型と中部・北陸型は50問から40問を選択して解答させる自治体が多いです。
①地方上級(全国型)
・ 憲法
・ 民法
・ 行政法
・ ミクロ経済
・ マクロ経済
どれも4問以上出題されるので押さえておくべき科目です。
この5科目だけで22問出題されます。
・ 第一候補:刑法・国際関係・ 民法
・ 第二候補:政治学・行政学・経営学
刑法は出題数が少なく、難解な問題もあるため捨て科目筆頭です。
ただ、捨てる科目を増やすほど、ほかの科目にしわ寄せが来ます。
②地方上級(関東型)
・ マクロ経済
・ 民法
・ 行政法
・ ミクロ経済
選択解答なので、必須解答の試験に比べると絶対的重要度は下がります。
ただ、ミクロ経済学は出題数が多く最も重要な科目です。
・ 第一候補:経済史・刑法・経済政策
・ 第二候補:政治学・行政学・経営学
「経済史」は教養経済、「経済政策」はミクロ・マクロと内容が被るので、元々それらに特化して勉強する人は少ないです。
捨てるというより、ほかの経済系科目の勉強で事足ります。
③地方上級(中部・北陸型)
・ 憲法
・ 民法
・ 行政法
・ ミクロ経済
この4科目だけで半数の25問が出題されます。
50問から40問選択するので、極端な話、この4科目だけで6割点数が取れます。
・ 第一候補:刑法・経済政策・国際関係
・ 第二候補:政治学・行政学・経済事情・社会学
どれも2問ずつのみの出題です。
刑法は他の科目と親和性も低いので、捨てても他の科目に影響はありません。
市役所上級の押さえる科目・捨て科目

市役所上級試験で、紹介するのは以下の3つの試験です。
① 市役所A日程
② 市役所B日程
③ 市役所C日程
市役所A日程は6月の後半、B日程は7月の後半、C日程は9月の後半に試験が実施されます。
出題数と難易度
各自治体によって、出題数は多少の違いがあります。
また、専門試験には、解答必須タイプと選択解答タイプががありますが、ここでは解答必須タイプの出題内訳を記載しています。
| 科目 | A日程 | B日程 | C日程 | 難易度 |
|---|---|---|---|---|
| 政治学 | 2 | 2 | 2 | ★★★☆☆☆ |
| 行政学 | 2 | 2 | 2 | ★★★☆☆☆ |
| 憲法 | 4 | 4 | 4 | ★★☆☆☆☆ |
| 行政法 | 5 | 5 | 5 | ★★★★★☆ |
| 民法 | 4 | 4 | 4 | ★★★★★★ |
| 刑法 | 2 | 2 | 2 | ★★★★☆☆ |
| 労働法 | 2 | 2 | 2 | ★★☆☆☆☆ |
| ミクロ経済学 | 5 | 3 | 2 | ★★★★★☆ |
| マクロ経済学 | 6 | 3 | 4 | ★★★★★☆ |
| 経済政策 | 0 | 3 | 4 | ★★★★☆☆ |
| 経済政策 | 0 | 2 | 1 | ★★★☆☆☆ |
| 経済事情 | 0 | 2 | 1 | ★★★☆☆☆ |
| 財政学 | 3 | 3 | 3 | ★★★★☆☆ |
| 社会政策 | 3 | 3 | 3 | ★★☆☆☆☆ |
| 国際関係 | 2 | 2 | 2 | ★★★★☆☆ |
| 合計 | 40 | 40 | 40 | – |
①市役所A日程
・ 行政法
・ ミクロ経済
・ マクロ経済
マクロ経済学とミクロ経済学は経済原論として11問出題されます。
次いで行政法が5問出ます。
・ 第一候補:刑法・国際関係
・ 第二候補:政治学・行政学
刑法と国際関係が捨て科目の第一候補。
労働法も2問のみの出題ですが、難易度が低いため、捨てるのはもったいない。
②市役所B日程
・ 行政法
・ 憲法
・ 民法
行政法が5問と最も多く出題されます。
憲法は出題数が多く難易度が低いため、押さえておきたい科目です。
・第一候補:刑法
・第二候補:政治学・行政学
捨て科目候補でも、自分の得意な科目であれば学習しても構いません。
経済事情は出題数が少ないですが、経済学として出題されているので、ほかの経済科目と一緒に勉強しましょう。
③市役所C日程
・ 行政法
・ 憲法
・ 民法
憲法は多く出題されますが、難易度が低いためおいしい科目です。
民法は難易度が高いですが、出題数を考えると押さえておきたいところ。
・第一候補:刑法・国際関係
・第二候補:政治学・行政学
自分の得意科目は、出題数が少なくても無理に捨てる必要はありません。
「ミクロ経済学」、「マクロ経済学」、「教養科目の経済」を学習すると、「経済政策」と「経済事情」もカバーできます。
特別区の押さえる科目・捨て科目

特別区は55問から40問を自由に選択して解答できるので、必ず押さえるべき科目はありません。
捨て科目も同様です。
出題数と難易度
| 科目 | 特別区 | 難易度 |
|---|---|---|
| 憲法 | 5 | ★★☆☆☆☆ |
| 行政法 | 5 | ★★★★★☆ |
| 民法Ⅰ | 5 | ★★★★★★ |
| 民法Ⅱ | 5 | ★★★★★★ |
| ミクロ経済学 | 5 | ★★★★★☆ |
| マクロ経済学 | 5 | ★★★★★☆ |
| 財政学 | 5 | ★★★★☆☆ |
| 経営学 | 5 | ★★★☆☆☆ |
| 政治学 | 5 | ★★★☆☆☆ |
| 行政学 | 5 | ★★★☆☆☆ |
| 社会学 | 5 | ★★★★☆☆ |
| 合計 | 55 | – |
特別区
・ 憲法
自由に解答できるので、絶対に押さえるべき科目はありません。
ただ、難易度が低い憲法は得点化しやすいです。
・第一候補:民法Ⅰ・民法Ⅱ
・第二候補:ミクロ経済学・マクロ経済学・行政法
これらの科目は、ほかの試験では重要科目なので、併願を考えている場合は、慎重に選びましょう。
また、特別区はほかの試験に比べ、出題される科目数が少ないので、捨て科目を積極的に作る必要はありません。
国家一般職の押さえる科目・捨て科目

国家一般職は80題から40題を選択して解答することができます。
ただ特別区とは違い、完全に任意の40題を回答するのではなく、8つの科目を選んで回答しなければいけません。
出題数と難易度
| 科目 | A日程 | 難易度 |
|---|---|---|
| 政治学 | 5 | ★★★☆☆☆ |
| 行政学 | 5 | ★★★☆☆☆ |
| 憲法 | 5 | ★★☆☆☆☆ |
| 行政法 | 5 | ★★★★★☆ |
| 民法(総則・物権) | 5 | ★★★★★★ |
| 民法(債権・親族・相続) | 5 | ★★★★★★ |
| ミクロ経済学 | 5 | ★★★★★☆ |
| マクロ経済学 | 5 | ★★★★★☆ |
| 財政学・経済事情 | 5 | ★★★☆☆☆ |
| 経営学 | 5 | ★★★☆☆☆ |
| 国際関係 | 5 | ★★★★☆☆ |
| 社会学 | 5 | ★★★☆☆☆ |
| 心理学 | 5 | ★★★★☆☆ |
| 教育学 | 5 | ★★★☆☆☆ |
| 英語(基礎) | 5 | ★★★★☆☆ |
| 英語(一般) | 5 | ★★★★★★ |
| 合計 | 80 | – |
国家一般職
・ 憲法
特別区と同様に、難易度が低い憲法はオススメです。
また、選択する科目は、ほかの科目と親和性の高いものを、まとめて選ぶといいかもしれません。
・第一候補:民法(総則・物権)・民法(債権・親族・相続)・英語(一般)
・第二候補群:行政法・ミクロ経済学・マクロ経済学
英語(一般)は英語が得意な人以外は避けた方が無難です。
そのほかの捨て科目候補は、ほかの試験では重要科目であることが多いので、併願先との兼ね合いを考えて選びましょう。
捨て科目の効率的な最低限対策法

捨て科目も「ゼロ対策」は危険!最低限の対策法とは?
「捨てる=完全に対策しない」は危険な考え方です。
なぜなら、公務員試験ではまぐれ当たりや消去法で正解できる場合もあるためです。
捨て科目であっても、最低限の基礎知識と頻出問題だけは押さえておくことが重要です。
短時間で抑える!効率的な対策方法
捨て科目は最小限の労力でカバーしましょう。
具体的には以下のような方法が有効です。
✅ 過去問を2~3年分だけ解く
✅ 出題頻度の高い分野に絞る
✅ 用語・定義だけは暗記
このように、最小限の対策で数問の正解を狙う工夫が大切です。
捨て科目で失点を最小限に抑えるコツ
捨て科目でも失点を抑えるテクニックがあります。
✅ 消去法で選択肢を絞る
✅ 「常識的に間違いそうな選択肢」を回避する
✅ 数値問題は極端な数値を避ける
このように、基礎的な解法テクニックだけは身につけておくと得点率が上がります。
教養試験における捨て科目戦略
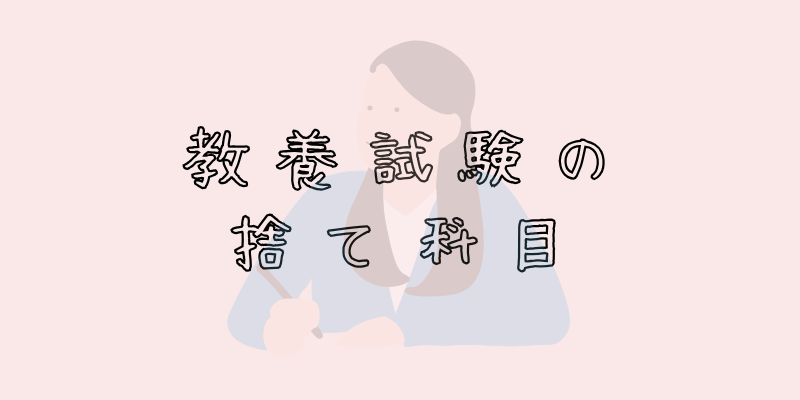
教養試験でも捨て科目戦略は有効?
教養試験でも捨て科目戦略は有効です。
特に、自然科学や人文科学は出題数が少なく対策コスパが悪いため、優先的に捨てる選択肢となります。
ただし、文章理解と数的処理は頻出科目なので絶対に捨ててはいけません。
捨てやすい科目と押さえるべき科目の見極め方
教養試験で捨てやすい科目は以下の3つです。
✅ 自然科学(物理・化学) → 出題数が少なく対策コスパが悪い
✅ 時事・国際関係 → 年度によって難易度が変動する
✅ 日本史・世界史 → 出題数が少なく、対策範囲が広い
文章理解や数的処理は捨てNG!頻出科目を優先
教養試験で最も出題数が多いのは文章理解と数的処理です。
この2科目は、効率的に得点源を作れる分野なので絶対に捨ててはいけません。
他科目を捨ててでも重点的に対策するべき分野です。
合格者の体験談:捨て科目戦略の成功事例

捨て科目戦略で合格!受験生Aさんの成功事例
Aさんは地方上級と市役所試験を併願。
試験ごとに出題傾向が異なることを踏まえ、併願先であまり出題されない科目を捨てる戦略を採用しました。
具体的には、経済事情と社会学を捨て科目と判断。
理由は以下の2点です。
✅ 出題数が少なく得点効率が悪い
✅ 他試験では出題されないため、対策のコスパが低い
その結果、民法・行政法・ミクロ経済に集中できたことで、解法パターンが身につき得点率が大幅に向上しました。
特に、地方上級では民法と行政法で満点に近い得点を獲得。
市役所試験でも経済系科目で7割以上の得点を記録し、最終合格を果たしました。
Aさんは、「捨て科目戦略を実践したことで重要科目の精度が上がり、凡ミスが減った」と振り返っています。
「あれこれ手を広げすぎていたら、合格は難しかったかもしれない」と語っています。
「捨て科目は3つまで」と決めて合格!Bさんの工夫
Bさんは地方上級と国家一般職を併願。
試験対策を始めた当初は「できるだけ満遍なく対策しよう」と考えていましたが、勉強範囲の広さに圧倒される状況に直面。
時間が足りないことを痛感し、捨て科目を3つに制限する戦略に切り替えました。
Bさんが捨てたのは以下の3科目です。
✅ 刑法 → 出題数が少なく、難易度が高い
✅ 国際関係 → 出題頻度が低く対策コスパが悪い
✅ 経済事情 → 他の経済系科目と重複しているため割り切る
代わりに、憲法・行政法・ミクロ経済・マクロ経済に集中。
特に経済分野は、併願先の国家一般職でも高得点が狙えるため、重点的に対策を行いました。
結果として、国家一般職では経済系科目で9割以上の得点を獲得。
地方上級でも行政法と憲法で高得点を記録し、2つの試験で最終合格しました。
Bさんは「捨てる科目を決めることで、他科目に対策時間をしっかり割けた」と話しています。
また、「3つに絞るルールを作ったことで捨てすぎを防げたのが良かった」と振り返っています。
捨て科目を決めた結果、他科目で満点を狙えたCさんの実例
Cさんは特別区と地方上級を併願。
試験ごとの出題傾向を分析し、「頻出でない科目は潔く捨てる」という戦略を立てました。
捨てた科目は以下の通りです。
✅ 社会政策 → 特別区では頻出ではないため捨てる
✅ 国際関係 → 出題数が少なく、他科目への影響が軽微
✅ 刑法 → 難易度が高くコスパが悪い
その分、行政法・民法・経済系科目に集中。
特に行政法は満点を目指す勢いで対策し、実際に本番で満点を獲得しました。
また、捨てた科目も過去問を3年分だけざっと解いておくなど最低限の対策は実施。
「まぐれ当たり」を狙える状態を作ったことで、運良く捨て科目で1問正解できたと振り返っています。
Cさんは、「捨てる科目を決めたことで、他科目で満点を狙えるようになった」と話しています。
「苦手科目をダラダラやるより、得意科目を徹底的に仕上げる方が合格に近づく」と語っています。
まとめ

専門科目の捨て科目について紹介しました。
何も知らずに捨て科目選んでしまうと、失敗する可能性があります。
ここで紹介した内容を参考に、自分のスペックなどに落とし込んで、どの科目を捨てて、どの科目を取りに行くか戦略的に考えていきましょう。
捨て過ぎると、ほかの科目でミスできなくなるので注意してください。