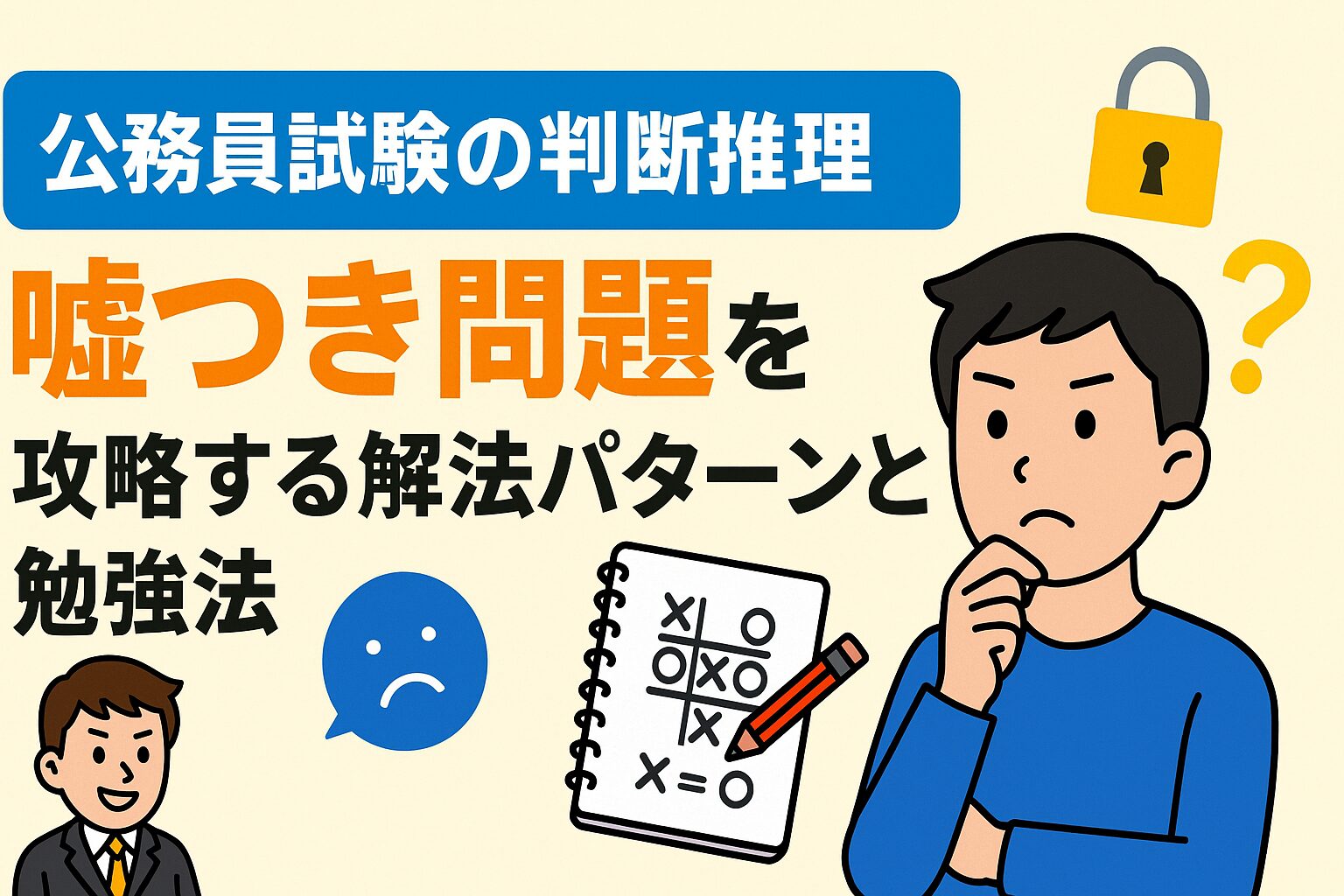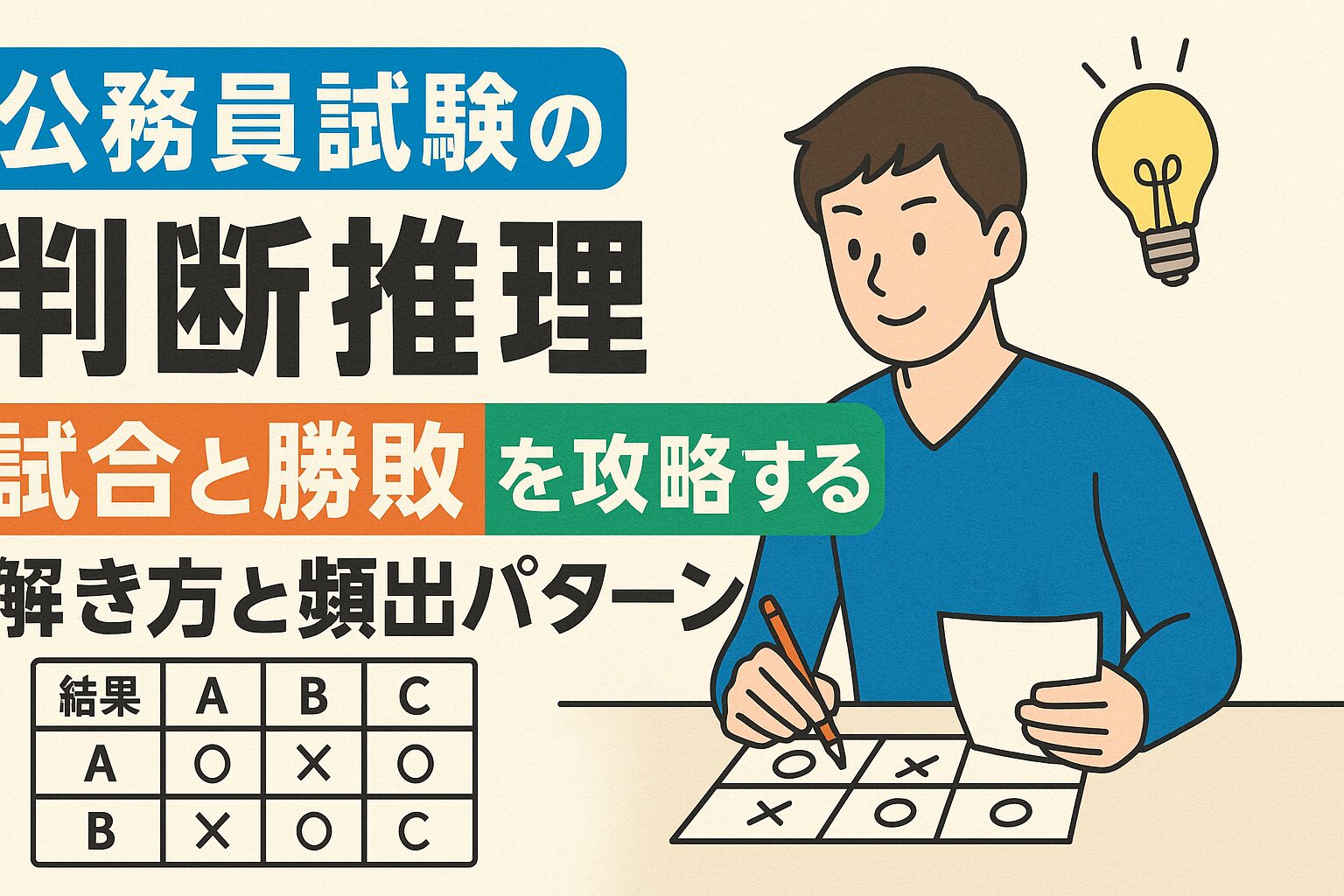はじめに:嘘つき問題とは?なぜ出題されるのか
公務員試験の判断推理分野の中でも、特に受験生を悩ませるのが「嘘つき問題」です。 これは、登場人物の発言の中に正直者と嘘つきが混ざっていて、誰が本当のことを言っているかを見抜きながら答えを導く形式です。
例: A「Bは嘘をついている」 B「Cは正直者だ」 C「Aは嘘をついている」 → このとき正直者は誰か?
このような問題は、単なる暗記ではなく論理的思考力や条件整理力を問うため、公務員試験において非常に重視されています。
💡 なぜ出題されるのか?
- 状況を正確に整理できるかを見るため
- 条件が矛盾しないかを論理的に考える力を試すため
- 行政職に必要な「情報処理力」を測るため
嘘つき問題は最初は難しく感じますが、解法パターンを押さえれば得点源になる分野です。 次の章では、実際に出題傾向と難易度を確認していきましょう。
出題傾向と難易度をチェック
嘘つき問題は、判断推理の中でも頻出度が高いジャンルです。特に国家一般職・地方上級でよく見られ、毎年1問程度は出題される傾向にあります。
📊 出題頻度
| 試験区分 | 出題頻度 | 難易度 |
|---|---|---|
| 国家一般職 | ほぼ毎年 | やや難 |
| 地方上級 | 2〜3年に1回 | 標準 |
| 市役所・警察 | 不定期 | やや易 |
⏱ 難易度と時間配分
- 解答時間の目安は3〜4分
- 1問あたりの得点価値が高い
- 他の判断推理問題よりも条件整理力が試されやすい
📌 得点戦略
嘘つき問題は最初こそ難しく感じますが、解法パターンを覚えれば安定して得点できるのが特徴です。 他の受験生が苦手とする分野だからこそ、ここを得点源にできれば大きな差をつけられるでしょう。
次の章では、嘘つき問題を解く上で欠かせない基本ルールについて詳しく解説します。
嘘つき問題の基本ルールを理解する
嘘つき問題は、登場人物の発言が常に正しい人(正直者)と常に嘘をつく人(嘘つき)でできています。 まずは前提ルールを押さえましょう。
✅ 正直者
- 言った内容はすべて真
- 自分や他人についての発言も一貫して正しい
❌ 嘘つき
- 言った内容はすべて偽
- 発言が事実と一致しない
📌 基本の考え方(仮定法)
1)誰か一人を正直者と仮定する
2)その人の発言を「真」として、他の人の真偽を連鎖的に決める
3)どこかで矛盾が出たら仮定を破棄 → 逆の仮定で再検討
🧭 矛盾チェックのコツ
- 自己言及:「私は嘘つきです」→ 矛盾が生じる典型
- 相互指摘:「Aは嘘つき」「Bは正直者」などを同時に満たせるか確認
- 人数制約:「正直者は1人だけ」などの条件を最後に必ず照合
🗂 図と表で“見える化”
推奨メモ法:人物ごとに「真/偽」欄を作る
- A:□ 真 □ 偽(発言:Bは嘘つき)
- B:□ 真 □ 偽(発言:Cは正直者)
- C:□ 真 □ 偽(発言:Aは嘘つき)
→ Aを真と仮定して塗る → 矛盾が出たらクリアして逆で再トライ
⚠ よくある勘違い
- 「嘘つき=一部は真を言う」と考えてしまう → 基本は発言全体が偽
- 条件文の読み落とし(例:正直者は2人 など)
- 途中で仮定を入れ替えてしまう → 一つの仮定は最後まで検証
ここまでのルールが分かれば、あとは型どおりに整理して矛盾を見るだけ。 次章では、得点直結の頻出パターンをサクッと押さえます。
頻出パターンを押さえよう
嘘つき問題にはよく出る定番パターンがあります。 出題形式をパターンごとに整理しておくと、本番で「あ、これはこの型だ!」と気づけて時間短縮につながります。
🧑🤝🧑 パターン①:2人の発言
例:
A「Bは嘘つきだ」
B「Aは正直者だ」
この場合、どちらかが正直・どちらかが嘘つきであることが多いです。 2人パターンは最も基本的で解きやすい型です。
👨👩👦 パターン②:3人の発言
例:
A「Bは正直者だ」
B「Cは嘘つきだ」
C「Aは嘘つきだ」
3人が互いを指摘し合う構図です。 1人を仮定→他の2人の矛盾を検証するのが鉄則。
👥👥 パターン③:複数人+条件付き
例:
A「BとCは同じタイプだ」
B「正直者は2人いる」
C「私は嘘つきだ」
「正直者は○人」「全員同じタイプ」などの条件付き発言は応用問題に多いです。 人数制約を最後に照合するのがポイント。
📊 まとめ
嘘つき問題の多くはこの3パターンに集約されます。 まずは型ごとに練習し、応用問題に対応できるようにしましょう。
次の章では、実際の例題を使って解法ステップを解説していきます。
【例題付き】嘘つき問題を実際に解いてみよう
ここからは実際の例題を通して、解法の流れを確認していきましょう。 初級レベルと応用レベルの2段階で解説します。
📌 初級例題
問題:
A「Bは嘘つきだ」
B「Aは正直者だ」
このとき、AとBのタイプを答えよ。
解き方:
① Aを正直と仮定すると → Bは嘘つき。
② その場合、Bの発言「Aは正直者」は嘘なので矛盾なし。
→ よってA=正直者、B=嘘つき。
📌 応用例題
問題:
A「Bは正直者だ」
B「Cは嘘つきだ」
C「Aは嘘つきだ」
正直者は2人いるとき、A・B・Cのタイプを答えよ。
解き方:
① Aを正直と仮定 → Bは正直、Cは嘘つき。
→ この場合、正直者はAとBの2人で条件に一致。
② 矛盾が出ないため、A=正直者、B=正直者、C=嘘つきが正解。
📌 ポイント整理
- まず仮定を置く
- 条件に照らし合わせて矛盾を探す
- 問題文にある「正直者は○人」などの条件は最後に照合
次の章では、合格者が実際に実践していた解法テクニックを紹介します。
合格者が実践した解法テクニック
嘘つき問題は型を知る+練習することが合格の近道です。 ここでは、実際に合格した受験生が使っていた効率的なテクニックを紹介します。
✍️ テクニック①:仮定は迷わず固定
「誰を正直者と仮定するか」で迷わない。
→ 最初に出てきた人物を仮定すればOK。
矛盾したら逆にするだけなので、時間短縮になります。
📑 テクニック②:表に整理する
- A:□ 真 □ 偽
- B:□ 真 □ 偽
- C:□ 真 □ 偽
このように人物ごとにチェック欄を作っておくと、ミスが激減します。
🕒 テクニック③:条件は最後に照合
「正直者は2人」などの人数制約は最後に確認。 途中で人数に引っ張られると誤答しやすいため注意。
⚡ テクニック④:最初の矛盾に注目
発言同士の最初の矛盾を見つけると一気に整理できます。 矛盾が出たら仮定を切り替えるサインです。
💡 テクニック⑤:過去問で型を定着
合格者は「過去問の嘘つき問題」を繰り返し解いていました。 何度も触れることで型が身体に染みつくため、本番でも迷わず解けます。
次の章では、受験生がやりがちなミスと回避法を紹介します。
よくあるミスとその回避法
嘘つき問題では、思わぬところでミスをして失点してしまう受験生が多いです。 ここでは代表的な失敗例と、すぐに実践できる回避法をまとめます。
⚠️ ミス①:嘘つきが「一部真を言う」と考えてしまう
嘘つきの発言はすべて偽が基本。 「この部分は合っているかも」と考えると解答がぶれる原因になります。
👉 回避法:「嘘つき=完全に逆」と徹底的に意識する。
⚠️ ミス②:人数条件を見落とす
「正直者は2人だけ」などの条件を最後に確認せず、途中で答えを決めてしまうパターン。 これで不正解になるケースが非常に多いです。
👉 回避法:必ず最後に人数条件を照合してから答えを確定。
⚠️ ミス③:仮定を途中で変えてしまう
最初にAを正直者と仮定したのに、矛盾を見つけたら途中で「やっぱりBが正直」と入れ替えてしまう。 これでは混乱の元になります。
👉 回避法:仮定は最後まで貫く。矛盾が出たら完全に破棄し、逆仮定からやり直す。
⚠️ ミス④:メモを取らずに暗算する
嘘つき問題は条件が複雑になりやすく、暗算では高確率でミスします。
👉 回避法:人物ごとに真/偽チェック表を必ず作る。
まとめ:
嘘つき問題のミスはほぼ基本ルールの勘違いか手順の省略から生まれます。
正しい手順を守ることが最大の防止策です。
次の章では、効率的に力をつけるための練習法とスタディング活用術を紹介します。
効率的な練習法とスタディング活用術
嘘つき問題を得点源にするには、ただ解くだけでなく戦略的な練習が大切です。 ここでは効率の良い勉強法と、オンライン講座「スタディング」の活用方法を紹介します。
📝 ステップ練習法
- STEP1:2人パターンだけを集中的に練習
- STEP2:3人パターンに挑戦
- STEP3:条件付きの応用問題で仕上げ
この流れで学習すると、徐々に難易度を上げながら確実に理解が定着します。
⏰ 時間を意識した練習
本番では1問3〜4分が目安。 過去問を解くときからタイマーを使い、時間内で処理できるかをチェックしましょう。
💻 スタディング活用術
スタディングの公務員講座には、判断推理の解法講義+問題演習が充実しています。 特に嘘つき問題のようなパターン別解法を動画で学べるのは大きなメリットです。
こんな人におすすめ:
- スキマ時間に効率よく学びたい
- 動画でテンポよく理解したい
- アウトプット中心に実力を伸ばしたい
次の章では、この記事全体を振り返り、嘘つき問題を合格への武器にするためのまとめをお届けします。
まとめ:嘘つき問題を得点源にして合格へ
嘘つき問題は、一見ややこしく感じますがルールと型を押さえれば得点源にできます。 他の受験生が苦戦する分野だからこそ、ここを攻略できれば大きな差をつけるチャンスです。
この記事で学んだポイント
- 嘘つき問題の基本ルールを理解する
- 頻出パターンを押さえて型を見抜く
- 例題で仮定と矛盾チェックの流れを習得
- 合格者のテクニックを実践する
- スタディング講座で効率よく練習する
公務員試験は科目数が多く、すべてを独学で対策するのは大変です。 だからこそ、短期間で効率よく学べるオンライン講座を活用するのが合格への近道。
嘘つき問題を得点源にできれば、判断推理で安定して点を稼げます。 ぜひ今日から練習を始め、合格への一歩を踏み出しましょう!