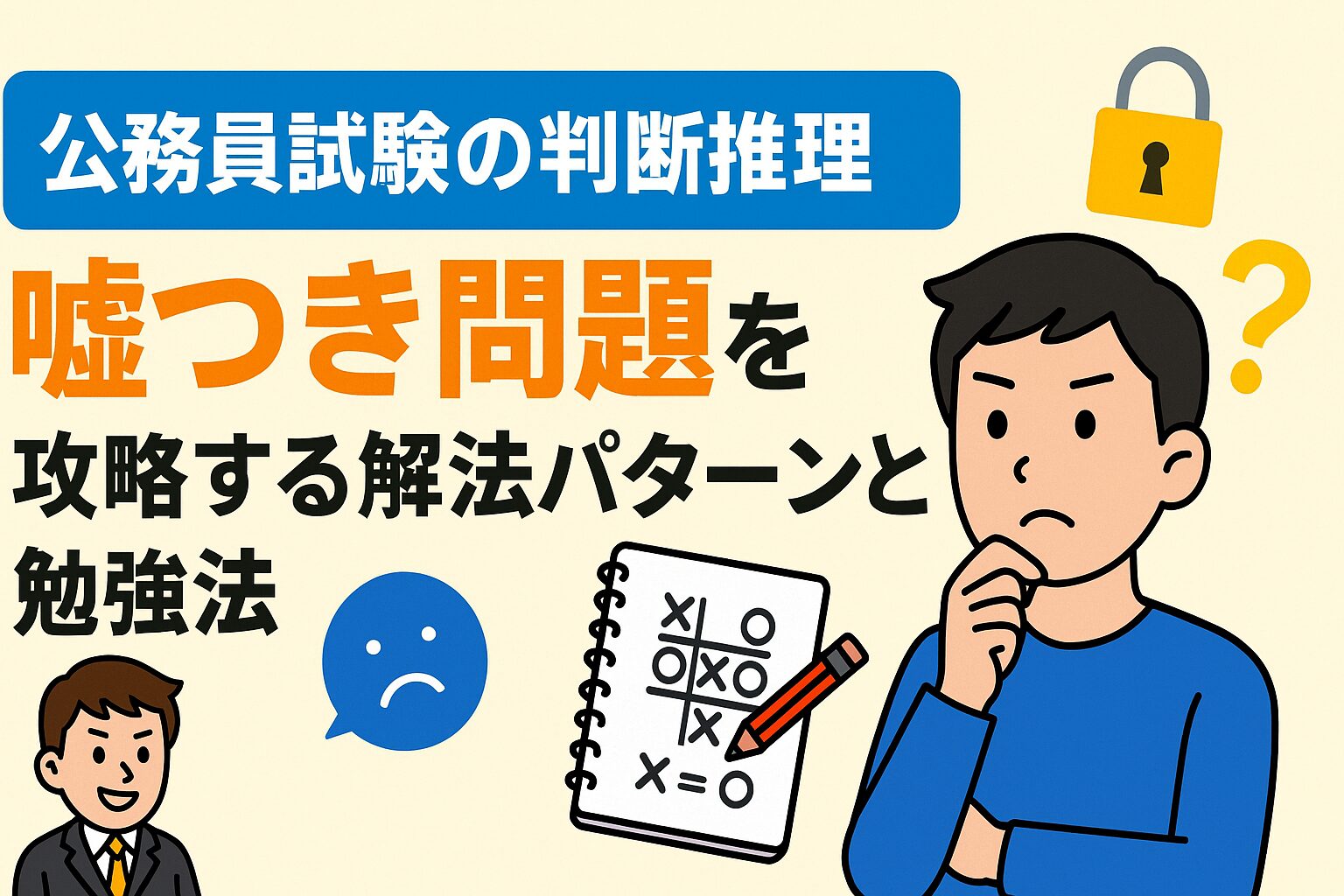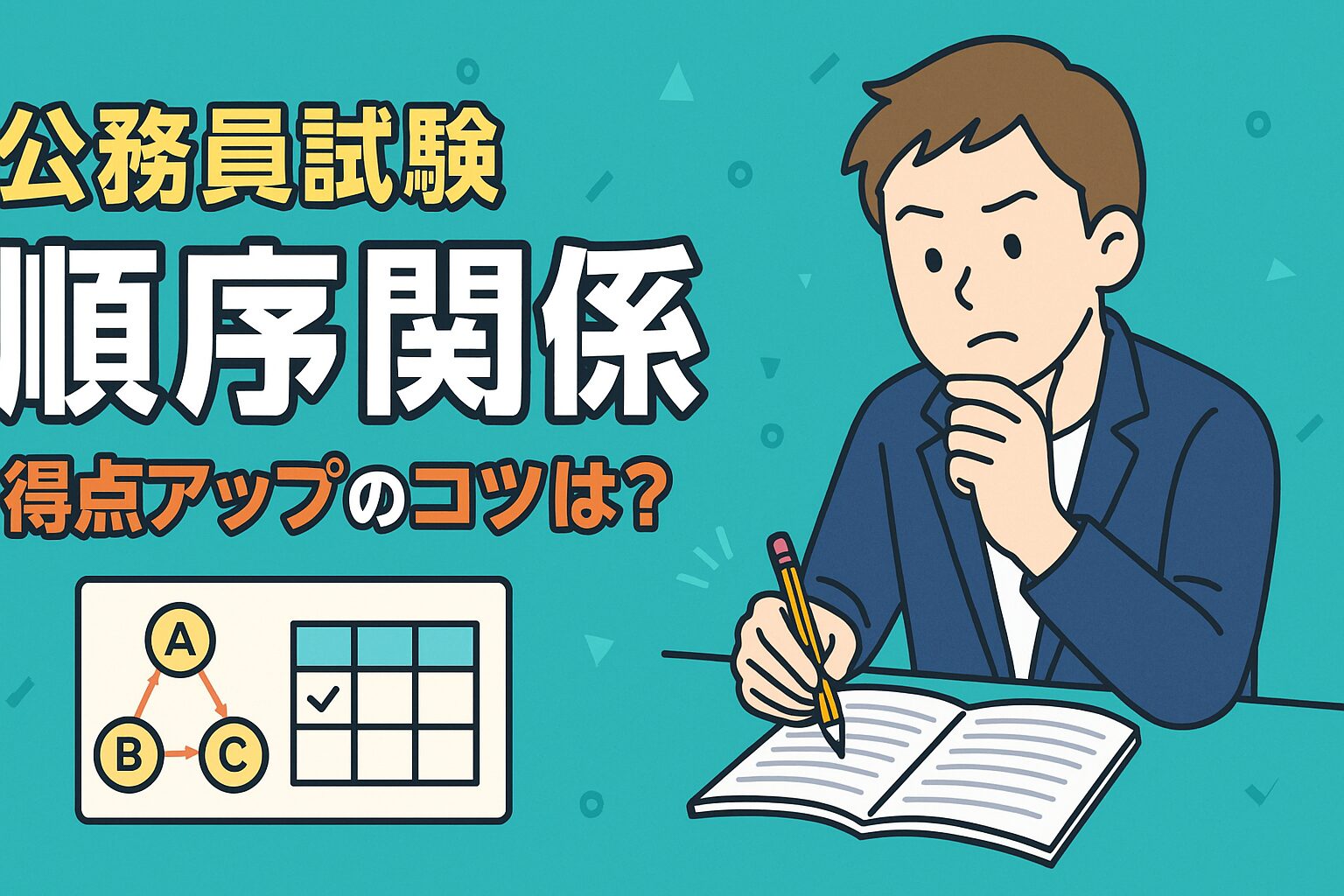はじめに|対応関係とは?なぜ重要なのか?
公務員試験の判断推理で頻出の対応関係は、
「人・色・座席・番号」など複数の要素を一対一で対応づけるタイプの問題です。
例)Aさん=赤、Bさん=青、Cさん=緑…のように、重複なしで正しい組を決めるのがゴールになります。
📌 判断推理の中での位置づけ
- 「条件整理」「矛盾発見」「表現換え」を問う基礎力評価の代表格
- 数的知識より論理整理力が重要 → 文系・理系どちらでも得点源にしやすい
- 図表で処理できるため、慣れると短時間で安定して正解を出せる
📈 出題頻度と難易度の特徴
- 国家一般職・地方上級・市役所などで高頻度に出題
- 基本問題は「一対一対応」、応用は「条件付き・順序混在」
- 処理量はあるが、型を覚えれば難度は標準〜やや易に感じる
対応関係は表(マトリクス)に落とすのが最速。
「確定 → 消去 → 矛盾チェック」の順で埋めれば、迷いが減り取りこぼしが激減します。
🎯 対応関係が得点源になる理由
- 手順化しやすい(表作成→確定→消去→矛盾)
- 条件の追加・変更にも柔軟に対応できる
- 短時間(目安3〜4分)で確実に1点を狙える
次章では、対応関係の基本ルールと考え方を図とともに整理し、最短で正解にたどり着くコツを解説します。
対応関係の基本ルールと考え方
対応関係問題を正確に解くためには、ルールを理解し整理の型を身につけることが重要です。 ここでは、基礎となる考え方を3ステップで解説します。
📘 ステップ1:対応関係の定義を理解しよう
対応関係とは、「AとBの組み合わせを特定する問題」です。
例えば、「3人(A・B・C)が3色(赤・青・黄)の帽子をかぶる」とき、
誰がどの色をかぶるかを決めるのが対応関係です。
重要なのは、一人につき一つ、重複しないというルール。 これが「一対一対応」と呼ばれる基本形です。
🧩 ステップ2:表(マトリクス)で整理しよう
条件が増えると混乱しやすいので、表形式で整理します。 例えば、次のような表を作ると視覚的に分かりやすくなります👇
| 人 | 赤 | 青 | 黄 |
|---|---|---|---|
| A | ✔️ | × | × |
| B | × | ✔️ | × |
| C | × | × | ✔️ |
このように確定→消去を繰り返すと、論理の流れが一目で見えます。
💬 コツ: 消去法を使うときは「確定した行(または列)」をまず埋め、残りを×で消す。 迷ったときは「矛盾が起きないパターン」から試すのが安全です。
🔍 ステップ3:矛盾を見抜く思考パターン
対応関係では、「Aが赤である」「Bが赤ではない」などの条件が交錯します。 このときの基本手順は次の通りです。
- ① 条件を表に反映(✔️ or ×)
- ② 条件同士に矛盾がないか確認
- ③ 確定したら他の行・列を更新
一見複雑でも、「表を中心に一方向で整理」すればミスは激減します。 慣れると、複数条件を見ても自動的に対応表が浮かぶようになります。
次章では、この基本を踏まえて頻出パターンを具体例で解説します。
頻出パターンを押さえよう!
対応関係問題では、毎年似たようなパターンが繰り返し出題されています。 この章では、得点に直結する3大パターンを分かりやすく解説します。
① 一対一対応型
もっとも基本的で頻出のタイプです。 「A・B・Cの3人」と「赤・青・黄の3色」のように、人数と要素が同数で対応します。
解法の流れ:
- ① 条件をそのまま表に反映する
- ② 「○○でない」条件を×で消す
- ③ 各行・列に1つだけ残る✔️を確定
💬 ポイント:
「一対一」は最も得点しやすい!まずはこのパターンを完璧にマスターしよう。
② 条件付き対応型
「Aは赤ではない」「BとCは同じ色をかぶらない」など、条件が複数絡むタイプです。 一見難しそうですが、一つずつ表に反映して整理すればOK。
整理のコツ:
- 「~ではない」条件から×を優先して記入
- 残った選択肢を見て✔️を確定
- 矛盾が出たら直前の条件を見直す
💬 ワンポイント:
条件を言い換えると理解しやすい。
例:「Aは赤ではない」=「Aは青か黄のどちらか」
③ 並び替え・順序型
「左から何番目」「上位にいる」「~の隣に座る」など、位置関係を含むパターンです。 図と表を併用して整理するのがコツです。
おすすめの整理法:
- ① 順序を線で描き、「位置」を意識して記入
- ② 「~の隣」「~より前」など相対条件を矢印で表す
- ③ 最後に表で整合性をチェック
このパターンは一見複雑ですが、位置関係を図に落とすだけで劇的に解きやすくなります。
📊 出題傾向まとめ
| パターン | 出題頻度 | 難易度 | 得点効率 |
|---|---|---|---|
| 一対一対応型 | ★★★★★ | 易 | ◎ |
| 条件付き対応型 | ★★★★☆ | 中 | ○ |
| 順序型 | ★★★☆☆ | やや難 | △ |
次章では、これらのパターンを踏まえて実際の例題を使って解法を学びましょう!
例題で理解を深めよう(初級〜中級)
ここでは、実際の対応関係の例題を使って解き方を確認していきます。 初級から中級レベルまで順に見ていきましょう!
🟢 例題①:一対一対応(基本)
問題:
A・B・Cの3人が「りんご」「バナナ」「みかん」を1つずつ選びました。
次の条件から、それぞれがどの果物を選んだか答えましょう。
- ① Aはりんごを選んでいない。
- ② Bはみかんを選んでいない。
- ③ Cはりんごを選んだ。
表で整理:
| りんご | バナナ | みかん | |
|---|---|---|---|
| A | × | ✔️ | × |
| B | × | × | ✔️ |
| C | ✔️ | × | × |
答え: A=バナナ、B=みかん、C=りんご
💬 解説: 条件③からC=りんごが確定 → 残りを×で消していくと自然に答えが見えてきます。 この「確定→消去」の流れが対応関係の基本です。
🟡 例題②:条件付き対応(やや応用)
問題:
A・B・C・Dの4人がそれぞれ「サッカー」「野球」「テニス」「バスケ」のいずれかをしています。
次の条件を満たすように対応を考えましょう。
- ① Aは野球ではない。
- ② サッカーをしている人はBではない。
- ③ DはAよりも番号の大きいスポーツ(アルファベット順で後ろ)をしている。
- ④ テニスをしている人はCではない。
ポイント:
条件①と②から「AとBを消去」し、③・④の関係を後で整理します。
ここで表を書いて消去法を使うと矛盾なく対応が決まります。
💬 コツ:
条件に「より大きい」「~ではない」が出たら、
順序と除外の両方を意識するのがポイントです。
🔵 例題③:矛盾型の応用問題
問題:
3人(A・B・C)が「赤・青・緑」のカードを1枚ずつ持っています。
次の発言から、正しい持ち主を判断してください。
- ① A:「Bのカードは青だ。」
- ② B:「Aのカードは赤ではない。」
- ③ C:「AとBのどちらかが緑を持っている。」
もし誰かの発言がすべて真であれば、その条件を表に落とし、矛盾を確認します。 一方で、誰かが嘘をついている前提のときは、「嘘の人を仮定」→「整合性チェック」という手順で進めましょう。
💬 テクニック: 嘘つき要素がある場合、すべての条件を「もしAが嘘なら」「もしBが嘘なら」と仮定して検証します。 最後に矛盾が出ない組み合わせを採用すれば正解です。
例題を通して見えてきたのは、整理と仮定の流れが鍵ということ。 次章では、合格者が使うスピード解法テクニックを紹介します!
合格者が実践した解法テクニック
対応関係を得点源にするには、スピードと正確さの両立がカギ。 ここでは、実際に多くの合格者が使っていた3つの解法テクニックを紹介します。
① 対応表を「速く」書くコツ
問題を見た瞬間に表の構造をイメージできるとスピードが劇的に上がります。
- ✔️ 問題文を読んだ段階で「何と何の対応か」をメモ
- ✔️ 表の見出しだけ先に書き、条件を読みながら埋めていく
- ✔️ 2行目以降は略字や記号(○×✔️)で処理
💬 ポイント:
「丁寧に書く」より「素早く整理する」が正解。
ミスが起きたら再構築しやすいように書きすぎない表を意識しましょう。
② 条件文から「先に整理」する
条件の中には、「~ではない」「~の隣」といった情報が多く含まれます。 これを最初に処理しておくと、解答スピードが一気に上がります。
- ① 「確定条件」と「除外条件」に分ける
- ② 「確定条件」から表に✔️を入れる
- ③ 「除外条件」は×を記入して矛盾を確認
💬 例: 「Aは赤ではない」「CはAの隣に座る」 → まずAの列に赤を×、次にAとCの位置を隣同士に配置。 条件の優先度を意識すると整理がスムーズです。
③ 「除外思考」で矛盾を発見する
対応関係問題では、すべての条件が正しくても「ありえない組」が必ず存在します。 これを除外していく思考が、正答率を上げる秘訣です。
- ① 「条件を満たさないペア」をすぐ消す
- ② 矛盾が起きたときは直前のステップに戻る
- ③ 最後に残る組み合わせ=正解!
💬 合格者の声:
「嘘を探すより、消して残す方が早い!」
対応関係は“探す問題ではなく、消す問題”と意識するだけでミスが減ります。
次章では、これらのテクニックを日々の学習に落とし込むための 効率的な勉強法とスタディング活用術を紹介します!
効率的な勉強法とスタディング活用術
対応関係問題は「慣れ」が勝負。 ここでは、短期間で判断推理を得点源に変えるための 勉強法+スタディング活用術を紹介します。
① 最短で力をつける3ステップ学習法
- ステップ1: まずは1日1問、表の書き方を練習
- ステップ2: 出題パターンを分析して「型」を覚える
- ステップ3: 制限時間を設けて実戦形式で解く
ポイントは、1問ずつ確実に理解すること。 量より質を重視することで、ミスが減りスピードも向上します。
② スタディング講座でできること
スタディングの公務員講座では、判断推理を含む数的処理を 動画+問題演習+AI分析で効率的に学べます。
- ✅ 対応関係などの頻出パターンを動画で体系的に学習
- ✅ 問題ごとに解説・思考手順が明確
- ✅ スマホでスキマ時間に演習できる
💬 合格者の声:
「電車の中でスタディングを見ながら解法を理解、家で復習を繰り返すだけで得点が安定しました!」
③ スキマ時間の活用で差をつける
判断推理は1問あたり3〜5分で解けるため、 通勤中や休憩中の“ちょい勉”に最適です。
- 📱 スマホで1問演習 → 解説を読む → スクショで復習
- 🧠 苦手パターンだけを繰り返し練習
- 📅 1週間単位で進捗をチェック
スタディングは学習履歴が自動で記録されるので、 自分の苦手分野を可視化しやすく、効率的に成長できます。
次章では、学んだ内容を総まとめし、 合格へ直結する勉強ステップを紹介します!
まとめ:対応関係は「整理力」で差がつく!
公務員試験の判断推理「対応関係」は、 パターンを理解して整理する力が問われます。 難しい計算よりも、「考え方の筋道」を素早く見抜ける人が圧倒的に有利です。
🧩 今回のポイントまとめ
- ・対応関係は確定 → 消去の流れで解く
- ・表や図を活用して「見える化」する
- ・除外思考で矛盾を消すと正解が浮かび上がる
- ・日々1問でも継続すれば必ず得点源になる!
💬 編集部コメント:
対応関係の問題は、一見複雑でもルールはシンプル。
「表を書いて、確定させて、矛盾を消す」
― この3ステップを繰り返すことで確実に得点力が上がります。
🎯 次にやるべき行動
ここまで理解できたら、次は実際に問題を解いてみましょう! 自分で表を作る練習を重ねることで、対応関係の感覚が身につきます。
おすすめの学習ステップ:
- ① この記事で紹介した例題をもう一度解く
- ② 似た問題を3〜5問解いて型を定着
- ③ スタディング講座で過去問+応用問題に挑戦!
判断推理の中でも対応関係は「慣れ」で差がつく分野です。 今日から少しずつ練習を始めて、あなたも合格への一歩を踏み出しましょう!