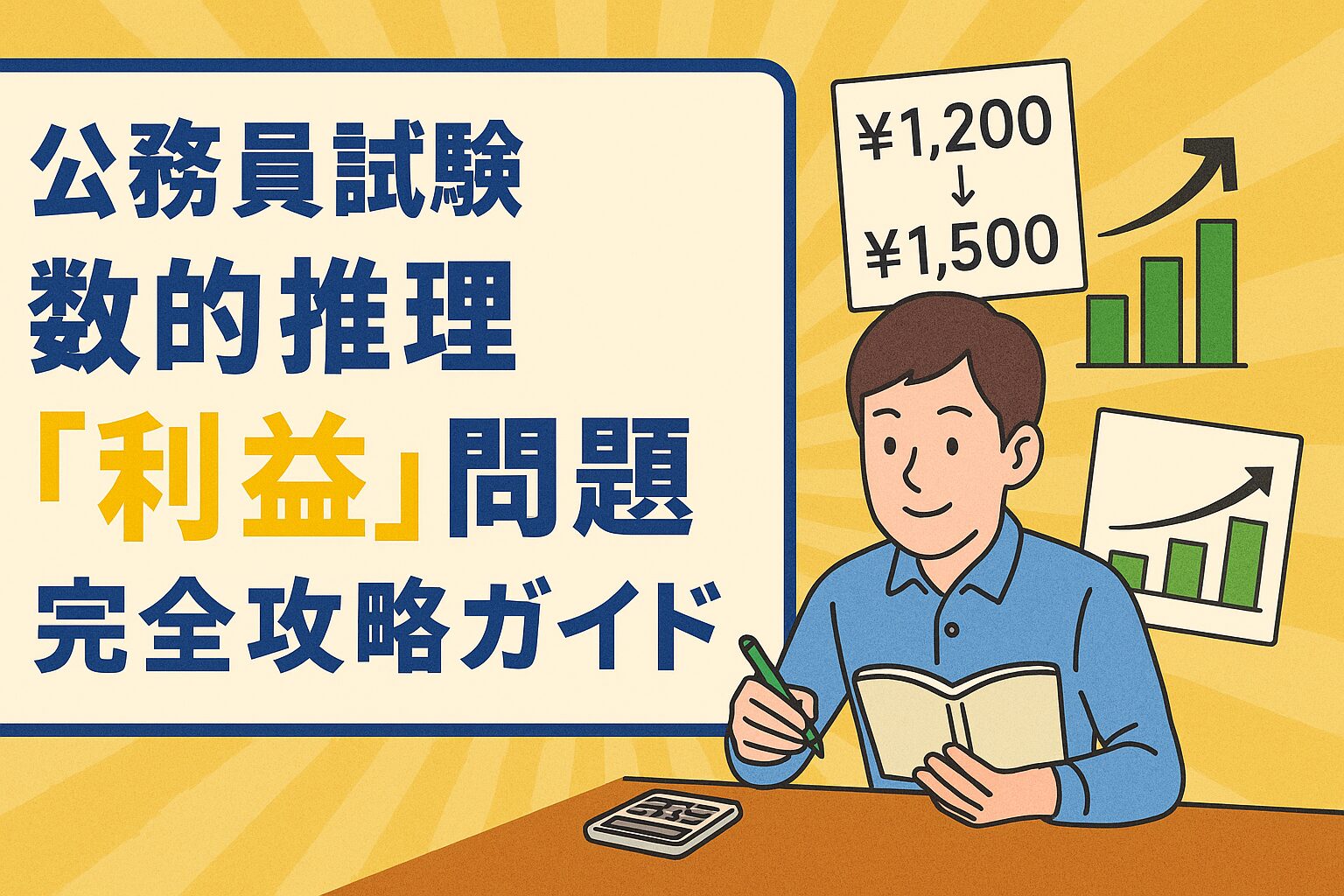基礎から理解!「利益」「損失」「利益率」の関係を整理 ✏️
まずは用語の意味と基準(どの値を基準に割合を出すか)をはっきりさせましょう。ここが分かると計算ミスが激減します。
📚 キホン用語を図で確認
| 用語 | 意味 | よくある記号 |
|---|---|---|
| 原価 | 仕入れ・製造にかかった元の値段 | C |
| 定価 | 売るために付けた値札の価格 | L |
| 売価 | 実際に売った価格(値引き後のことも) | S |
| 利益 | 売価 − 原価 | P = S − C |
| 損失 | 原価 − 売価 | Loss = C − S |
🧮 利益率・損失率は「原価」基準が基本!
公務員試験では、特に指定がない限り利益率・損失率は原価基準です。
損失率 = 損失 ÷ 原価 = (C − S) ÷ C
利益率(原価基準)と混同しないように、基準の違いにマーカー!
🧩 例題①(超基本):利益・利益率
- ① 利益 P = 9,600 − 8,000 = 1,600円
- ② 利益率 = 1,600 ÷ 8,000 = 0.2 = 20%
🏷️ 例題②:割引(定価基準)と利益(原価基準)を両立
- ① 割引額 = 10,000×0.20 = 2,000円 → 売価 S = 8,000円
- ② 利益 P = S − C = 8,000 − 8,000 = 0 → 利益率0%
→ 割引でちょうど原価売りになりました。
ややこしいときは「原価を1に置く」と一気に整理できます。
例:原価1、定価1.25(=25%上乗せ)、2割引→売価=1.25×0.8=1.0 → 利益率0%(原価基準)
🔗 例題③:原価・定価・売価の関係を“掛け算で”つなぐ
比・割合の連鎖は掛け算で処理すると速いです。
売価 = 定価 × (1 − 割引率)
利益率(原価基準) = (売価 ÷ 原価) − 1
売価 = 1×1.3×0.9 = 1.17 → 利益率 = 1.17 − 1 = 17%
🧠 つまずきポイント早見表
| つまずき | 原因 | 対策 |
|---|---|---|
| 割引率と利益率を混同 | 基準の違い | 割引=定価基準/利益=原価基準とメモ |
| パーセントの往復で迷う | 足し算・引き算で処理 | 掛け算連鎖(×1.○○/×0.○○)に統一 |
| 数字が複雑で時間ロス | 途中で基準がブレる | 原価=1で置換して比で処理 |
- 利益率・損失率は原価基準、割引率は定価基準
- 「原価=1」で置くと複合条件でも一発整理
- 計算は掛け算連鎖でスピーディーに!
次章では、試験に出る典型パターン(4分類)を、ステップと暗算コツつきで解説します。
典型問題を解く!よく出る利益問題の4パターン
公務員試験の「利益」分野は、次の4パターンを押さえればほぼ対応できます。各パターンで思考ステップ→例題→時短コツの順に確認しましょう。
① 基本:利益率・損失率を求める
- ① 用語整理(原価C・定価L・売価S)。
- ② 利益率は原価基準: (S−C)/C。
- ③ 数字が複雑なら 原価=1 に置換。
① 利益=2,400円 ② 利益率=2,400/12,000=20%
② 値引き(割引)を含む損益
割引率は定価基準。利益率は原価基準。基準の切替に注意!
利益率 = (S ÷ 原価) − 1
① 売価 S=11,000×0.85=9,350
② 利益率=(9,350/8,000)−1=1.16875−1=16.875%(約16.9%)
③ 仕入れ・まとめ売りなど複合利益
複数商品の合算では「合計の利益率」を直接出すのが鉄則。各商品の個別利益率を平均してはダメ。
- ① 合計原価 Ctot=C₁+C₂+…
- ② 合計売価 Stot=S₁+S₂+…
- ③ 合計利益率=(Stot − Ctot) ÷ Ctot
A品:原価3,000→売価3,600 B品:原価5,000→売価5,200。全体の利益率は?
① 合計原価=8,000 合計売価=8,800
② 利益=800 → 利益率=800/8,000=10%
④ 損益合算(利益と損失が混在)
一部は利益、一部は損失でも、合計原価と合計売価で一本化すればOK。
商品X:原価4,000を20%利益で販売。商品Y:原価6,000を10%損失で販売。全体の利益率は?
① Xの売価=4,000×1.2=4,800(利益=800)
② Yの売価=6,000×0.9=5,400(損失=600)
③ 合計原価=10,000 合計売価=10,200 → 利益=200
④ 合計利益率=200/10,000=2%
🔑 4パターンの共通フレームワーク
2) 掛け算連鎖で「上乗せ(×1.○○)」「値引き(×0.○○)」を処理
3) 合算は金額ベースで(比や率の単純平均はしない)
次章では、今の4パターンを使った実践例題をステップ解説+暗算テク付きで解いていきます。ここで手を動かして、スピードと正確性を同時に鍛えましょう!
実践例題で理解を定着!ステップ解説と暗算テク
ここでは、実際に公務員試験で出題されたレベルの「利益」問題を使って、 ステップ解説+暗算のコツでスピーディーに解けるよう練習していきましょう!
💡 例題①:割引と利益率の複合
原価6,000円、定価8,000円の商品を定価の15%引きで販売した。利益率はいくらか?
- ① 売価S=8,000×0.85=6,800円
- ② 利益=6,800−6,000=800円
- ③ 利益率=800÷6,000=13.3%
💰 例題②:損益合算(利益+損失)
A商品は原価4,000円を25%の利益で販売、B商品は原価6,000円を10%の損失で販売した。全体の利益率を求めよ。
- ① Aの売価=4,000×1.25=5,000円
- ② Bの売価=6,000×0.9=5,400円
- ③ 合計原価=10,000円、合計売価=10,400円
- ④ 利益=400円 → 利益率=400÷10,000=4%
📦 例題③:定価設定を求める逆算型
原価が9,000円の商品を定価の10%引きで販売したところ、原価の20%の利益が出た。定価を求めよ。
- ① 売価S=原価×1.2=9,000×1.2=10,800円
- ② 割引後価格=定価×0.9=10,800円
- ③ 定価=10,800÷0.9=12,000円
🏷️ 例題④:利益率から原価を求める
ある商品を15,000円で販売し、20%の利益を得た。原価を求めよ。
- ① 利益率=20% → 売価=原価×1.2
- ② 原価=15,000÷1.2=12,500円
🚀 スピードアップのための思考整理
- ✅ 「原価・定価・売価」のどれが基準かを即確認!
- ✅ 割引・上乗せはすべて「×1.○○」で統一!
- ✅ 合計利益率は金額加重で、単純平均は使わない!
このパターンと例題を理解すれば、公務員試験の利益問題は怖くありません。
あとは過去問演習+オンライン講座でスピードと精度を鍛えるだけです。
次章では、「利益」問題の出題傾向と実際の試験対策を紹介します。ここで“点を取る練習法”を知っておきましょう!
出題傾向と得点戦略:利益問題で差をつける!
「利益」問題は、数的推理の中でも頻出かつ得点源にしやすい分野です。 難問よりも“正確さとスピード”が求められるため、パターンを押さえておくことで確実に点が取れます!
📊 出題傾向まとめ
- ① 国家一般職・地方上級試験では、利益+割引の複合問題が定番。
- ② 市役所・警察・消防では、割合の感覚を見る基本計算問題が多い。
- ③ 近年は文章型の利益問題(表・グラフ付き)も増加傾向。
💡 得点戦略
利益問題は、他の数的推理分野に比べて「短時間で確実に正解できる」ジャンルです。 ここを得点源にすることで、合格ライン突破がぐっと近づきます。
- ① 「原価=1」で考える習慣をつける(暗算が速くなる)
- ② 割合は「×1.○○」「×0.○○」で統一して処理
- ③ 割引・利益・損失の基準の違いを即判断できるように
公務員試験の利益問題は「解き方を知っているか」で差がつきます。 計算力よりも、整理力と手順力を磨きましょう。
📘 よくある失敗と対策
| 失敗例 | 原因 | 対策 |
|---|---|---|
| 割引率と利益率を混同 | 基準(定価/原価)の混乱 | 基準を書き出して整理する習慣を! |
| 計算途中で数字が崩れる | 整数にこだわりすぎ | 比や1基準でシンプルに処理 |
| 損益混在で混乱 | 個別利益率の平均を取るミス | 合計金額ベースでまとめて計算 |
🚀 仕上げに向けての勉強法
- ① 過去問3年分を解いて「出る型」を把握
- ② 1問1分で解けるまでスピード演習
- ③ 苦手分野はオンライン講座で反復(動画で理解が早い)
「数的推理を基礎から理解したい」「暗算力を鍛えたい」なら スタディング公務員講座 が最短ルート。スマホでもスキマ時間で利益分野をマスターできます!
次章では、この記事のまとめと、合格に向けた最終アドバイスをお伝えします。
まとめ:利益問題は「型」で勝負!スタディングで最短攻略を
公務員試験の数的推理における「利益」問題は、 一見ややこしそうに見えても、実は「型」を押さえれば得点源になる分野です。 最後に、この記事のポイントをおさらいしましょう👇
- ✅ 利益率は「原価基準」、割引率は「定価基準」で整理!
- ✅ 値引き・上乗せは「×1.○○」の掛け算連鎖で処理!
- ✅ 複合問題は「金額合算」で考えるのが鉄則!
- ✅ 基礎パターン4種+応用例題で試験レベルを完全カバー!
特に原価を1に置き換えて考える思考法をマスターすれば、 計算スピードも正確性も格段にアップします。 公務員試験の時間制限下では、こうした「思考の省エネ化」が合格への近道です。
🎯 次のステップ:学習を加速させよう
利益・損益算を含む数的推理を体系的に学びたい方へ👇
スタディング公務員講座で効率学習を始める
🧠 合格者からの声
💬 「数的推理が苦手だったけど、スタディングの講義で一気に理解できた!」
― 地方上級 合格者(24歳)
💬 「通勤中に動画で復習できたのが大きい。利益の問題も一瞬で解けるようになりました!」
― 国家一般職 合格者(27歳)
公務員試験は「戦略と習慣」で決まります。 難しい問題を追うより、出る問題を確実に取る力を磨きましょう。 この記事で学んだ内容をもとに、あなたも「利益問題マスター」へ!