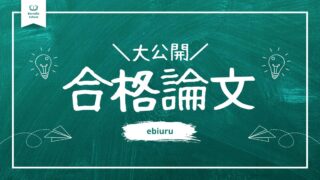公務員試験では、「論文試験」か「作文試験」のどちらかが課される場合が多いです。
基本的に、
✔ 大卒・上級レベルの試験→「論文」試験
✔ 高卒・初級レベルの試験→「作文」試験
を受験することになります。
ところが、この論文と作文の違いをよく理解しないまま受験をして、大失敗してしまう人がいます。
実は「論文試験」と「作文試験」には決定的な違いがあります。
この違いを理解しておかないと合格点に達する文章を書くことができないんです。
そこでこの記事では、論文と作文の違いについて紹介します。
・ 論文試験と作文試験の違い
・ 論作文試験の採点基準
・ 論文・作文の書き方
論文・作文試験で差をつけるならアガルート!
\無料サンプル講座で実力をチェック👇/
論文と作文の根本的な違い

「論文」と「作文」は全く違う種類の文章です。
論文と作文の見分けポイントは「採点者を説得・納得させる必要があるかないか」という点です。
〇 論文試験→「採点者」を説得・納得させる必要がある。
〇 作文試験→「採点者」を説得する必要はなく、好きに書いていい。
論文試験
論文とは「論:物事の筋道を述べる」という意味があるように、100人が聞いて100人が納得する文章のことを言います。
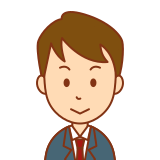
イメージでいえば、大学で書くレポートのようなものです!
論文試験は、数値やデータを元に論理的に文章を展開していきます。
後述しますが、自分の主観や考え方は極力控えて、実データに基づいた根拠のある文章展開が求められます。
基本的な文体は「である調」「私は~だから~と考える」。
課題テーマにもよりますが、基本的には以下のとおり進めていくことになります。
① まずは論理構成を考える
② テーマの背景(序論)を書く
③ 課題点をいくつか書き出す
④ 対応策を書き出す
⑤ まとめ(今後の方針)を書く
⑥ 見直し
作文試験
逆に作文とは、自分の経験や体験からの考察・そこから何を学んだか感じたか、自分の考えを書いていく文章です。
論文とは対照的に、作文試験には必ず自分の意見・考えを書く必要があるんです。
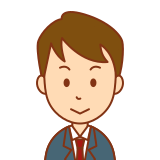
イメージとしては、小学校~高校生までの読書感想文のようなものです!
基本的な文体は「ですます調」「私は~だと思う」。
進め方としては、以下のとおりです。
① 構成を考える(文章の流れを決める)
② 自分の思った感想を表現力・発想力豊かに書く
③ 見直し
論文・作文試験で差をつけるならアガルート!
\無料サンプル講座で実力をチェック👇/
論文と作文のテーマの違い

上述したように、論文と作文では全く種類が異なります。
それは【課題テーマ】も同じことが言えます!
論文であれば「対策を述べよ」
作文であれば「あなたの感想・思っていることを書きなさい」
という形式になっています。
論文試験のテーマ(例)
例① 地方自治の重要性
「地方自治の強化が地域住民の生活に与える影響について論じ、具体例を挙げて説明せよ。」
例② 少子高齢化社会への対応
「少子高齢化が日本社会に及ぼす影響を分析し、効果的な政策を提案せよ。」
例③ 環境保護と持続可能な開発
「環境保護と経済成長のバランスを保つための具体的な政策を考察せよ。」
例④ 災害対策と地域防災力の向上
「地域防災力を向上させるために必要な施策を挙げ、それらがどのように機能するかを説明せよ。」
例⑤ 情報通信技術(ICT)の活用による行政サービスの向上
「ICTの活用が行政サービスの質をどのように向上させるか、具体的な事例を用いて論じよ。」
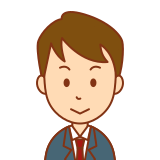
簡単にまとめると論文のテーマは、深く分析して論理的に議論することが目的です。
作文試験のテーマ(例)
例① 地域社会の活性化
「あなたの地域における地域活性化のためのアイデアを述べ、その実現に向けた具体的な行動計画を示せ。」
例② 公務員の役割と責任
「公務員としての自分の役割と責任について考え、それをどのように果たしていくかを具体的に述べよ。」
例③ 公共交通の重要性
「公共交通の利用促進が地域社会に与える影響について論じ、改善策を提案せよ。」
例④ 市民参加の促進
「市民参加を促進するための具体的な施策を考え、その必要性を説明せよ。」
例⑤ 環境問題への取り組み
「環境問題に対するあなたの考えを述べ、地域や個人としてどのように貢献できるかを考察せよ。」
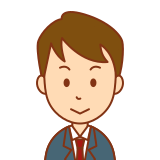
簡単にまとめると作文のテーマは、自分の考えや感情を自由に表現することが目的です
論文・作文試験で差をつけるならアガルート!
\無料サンプル講座で実力をチェック👇/
論文・作文試験の頻出テーマと傾向分析
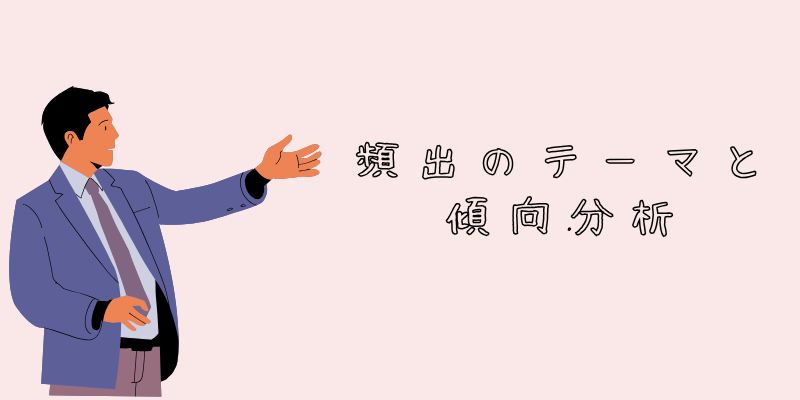
【論文試験の頻出テーマと傾向】
公務員試験の論文では、社会問題や行政課題を題材にした「課題解決型テーマ」が頻出しています。近年は時事問題と関連したテーマが増加傾向にあり、具体的な政策提案や施策の実現性が求められます。
📌 頻出テーマ一覧
- 少子高齢化と人口減少対策
- 少子化による労働力不足と経済縮小への影響を分析し、解決策を提案するテーマ
- 地域活性化と地方創生
- 地域経済を活性化させるための施策や、住民参加の促進方法を問うテーマ
- 防災・減災対策と災害時の行政対応
- 災害対策における自治体の役割や、住民の防災意識向上策を論じるテーマ
- 行政のデジタル化(DX)と効率化
- ICTやAIを活用した行政サービスの向上と課題解決策を提案するテーマ
- 環境問題と持続可能な開発(SDGs)
- 気候変動対策や再生可能エネルギー促進に関するテーマ
- 市民参加と行政の透明性向上
- 住民参画を促進するための具体策や、行政の情報公開制度について論じるテーマ
📊 最近の出題傾向
- 政策提言型が増加: 「課題→原因→解決策」の流れで具体策を述べる論文が増加。
- 実現可能性が重視: 現実的で実現可能な施策を示すことが高評価につながる。
- 時事問題との関連性: 少子高齢化や災害対策などニュースで話題になっているテーマが出題されやすい。
【作文試験の頻出テーマと傾向】
作文試験では自分の体験や考えを述べるテーマが頻出しています。特に公務員の適性や使命感を問う内容が多く、行政への理解や住民目線が重視されます。
📌 頻出テーマ一覧
- 地域社会への貢献と自分にできること
- 「住民としてできる地域貢献」や「公務員として果たすべき役割」を考察するテーマ
- 理想の公務員像と公務員の責任
- 公務員に求められる倫理観や職務への姿勢について考えを述べるテーマ
- 市民と行政の信頼関係
- 行政への信頼を高めるために必要な姿勢や施策について意見を述べるテーマ
- 身近な社会課題と解決策
- 環境保護や防災、福祉など身近な課題への自分なりの考えと対策を述べるテーマ
- 働くうえで大切にしたい価値観
- 「責任感」「誠実さ」「協調性」など、公務員に必要な資質について意見を述べるテーマ
📊 最近の出題傾向
- 公務員の適性を問うテーマが増加: 公務員に求められる「責任感」「住民への誠実さ」を問う内容が頻出。
- 具体的な体験やエピソードが評価される: 体験談や具体例を交えた説得力のある文章が高得点につながる。
- 公共性と住民目線が重視: 「市民目線で考える姿勢」が評価ポイントとなっている。
【頻出テーマへの対策法】
頻出テーマに対策するには、過去問の傾向分析と構成案の作成が効果的です。
📚 対策法①:過去問からテーマを予測
- 過去3年分の論文・作文テーマを調査し、出題傾向を把握する。
- 繰り返し出題されているテーマは重点的に対策する。
✍️ 対策法②:構成案を作成して練習
- 頻出テーマに対して、**「序論→本論→結論」**の構成を事前に作成する。
- 実際に時間を計って書く練習を繰り返す。
📰 対策法③:時事問題をチェック
- 新聞やニュースアプリで時事問題をチェックする。
- 社会問題や行政課題に対して自分の考えをまとめておく。
論文・作文試験で差をつけるならアガルート!
\無料サンプル講座で実力をチェック👇/
論文試験・作文試験の採点基準

論文試験の採点基準
論文試験の採点基準は以下の3点がポイントです。
・ 設問に対しての結論が論理的であるか
・ 結論に対して、論理的な根拠や証拠があるか
・ 実現可能な方法かどうか
どこかが著しく欠けている場合は、点数がもらえないこともあるため必ず押さえておいてください。
採点イメージは以下の通りです。(今回は50点満点と仮定)
・設問に対しての結論が論理的であるか
基準点(A:30点 B:20点 C:10点 D:0点)が設けられており、結論の妥当性を評価され点数が付与される。
・結論に対して、論理的な根拠や証拠があるか
この部分は、減点方式が取られる。
・実現可能な方法かどうか
残り20点は、具体的な提案が実現可能かどうか整合性が取れているかで加点される。
理想の空論ばかりを述べている文章は点数が低くなることがあります。
日頃からニュースや新聞などを読みつつ、自分の提案が本当に実現可能なのか意識して対策をしていきましょう!
作文試験の採点基準
作文試験で高得点をとるためには、以下の5点を意識してください。
・ 設問に正しく答えられているか
・ 説得力のある主張が述べられているか
・ 誤字脱字がないか
・ 原稿用紙の使い方が間違っていないか
・ 時間、文字制限などのルールが守られているか
上記でも述べたように、作文試験とは自分自身の考えや主張をアピールする試験です。
そのため、説得力のある主張、採点者が納得する考えをいかに書けるかが重要です。
さらに「誤字脱字」「原稿用紙の使い方」「文字制限」などの細かなルールを見落としている人がかなり多い。
論文試験にも当てはまりますが、公務員は法律、規則(ルール)を根拠に業務を行います。
設問に「⚪︎⚪︎文字以内」「根拠を3つ出して」などの制約がある場合は、必ずチェックをつけて見落とさないようにしましょう!
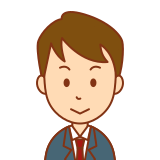
見落としで減点もしくは不合格になるのはもったいない!設問は最低3回読んでしっかりと理解しよう!
論文・作文試験で差をつけるならアガルート!
\無料サンプル講座で実力をチェック👇/
論文・作文の書き方

論文試験・作文試験の違いがわかったところで、具体的な書き方に入っていきましょう。
いきなり書き始めない
論文試験・作文試験でいきなり文章を書き始める人がいますが、これはNGです。
なぜなら、途中で間違いを見つけても書き直すことができないからです。
論文・作文試験は原稿用紙に書いていく場合がほとんど。途中で間違えてしまうと隙間があいたり、不自然な使い方になってしまったりします。
そうなると、全てを消して書き直すしかなくなりますよね。
なので、いきなり書き始めることはしないようにしましょう。
分析→構成を考える→書く
では、どのように本文を書けば良いのか。書くまでの流れを解説していきます。
結論、情報を分析し構成を考えて、本文を書き始める

時間的には、情報分析③:構成を考える⑤:本文を書く② くらいのイメージでOKです。
論文試験・作文試験は準備が9割です。上記1〜3にしっかりと時間を使い採点者を納得させる文章を作りましょう!
行政職員の視点を入れ込む
いくら素晴らしい文章が書けていても行政職員の視点が抜けている文章は評価されません。
本文を書く際には、以下の考え方を入れて書いてみてください。
・ 行政は適応できる人ではなく、適応できない人を救う職である
・ 住民目線で考える
・ 実現可能な施策・提案か
適応できる人ではなく、適応できない人を救う
公務員の業務は「最終ネット」とよく言われます。(生活保護などが良い例)その業務の特性上、何かしらに適応できない人も助けられる施策・提案が求められるんです。
民間企業との違いですが、民間企業は利益を求める必要があるため対象者を絞って施策を行います。
しかし、公務員は営利目的ではない。市民、国民の税金を使って施策を行うわけです。そのため、対象者は全市民、全国民です。
民間企業の施策から漏れ出た人を救う、全ての人に納得してもらえる。そんな施策・提案が求められることを意識しましょう。
住民目線で考える
例えば、あなたが地方創生の事業責任者であるとします。
上司から「この地域を盛り上げ住民を活発にする施策を考えてほしい」と言われました。あなたは、どのような案を考えますか?
案:映画館やショッピングモールをつくって移住者を呼び込み経済を回す
これだとNGです。
なぜなら、地方を都市化して喜ぶのであれば、そこに住む住民は都市部へ引っ越しているはず。
長年、その地域に住み続けている理由は、その地域が好きだからですよね。そのため、景観を損なうような施策を提案することは住民の反感を買うことになります。
常に住民目線で施策やサービスを考える。思いつきの施策の列挙は控えましょう。
実現可能な施策・提案か
採点基準の項目でも説明した通り、近年の論文試験・作文試験は「実現可能な施策か?」という視点が重要です。
人口減少、少子高齢化などにより行政は施策やサービスにかける予算の削減が求められている現状にあります。
少ない予算の中で住民を満足させるサービスを考えるのも公務員として必要な能力です。
自分が提案した施策・サービスが本当にその自治体の規模で実現可能なのか。この視点も忘れないようにしてください。
論文・作文試験で差をつけるならアガルート!
\無料サンプル講座で実力をチェック👇/
【合格者が実践した論文・作文対策法】
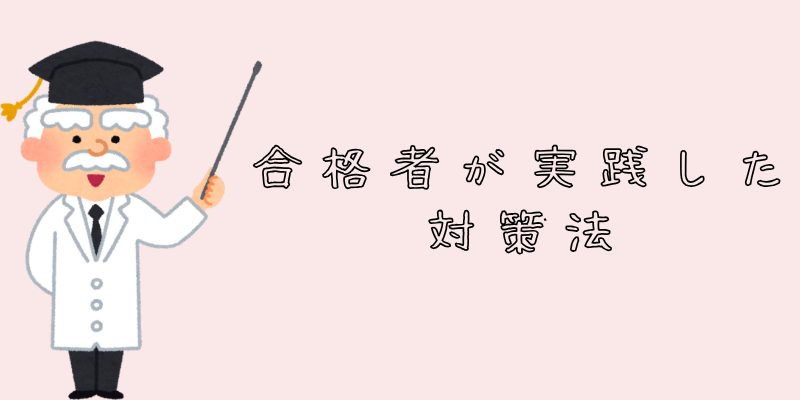
【合格者が実践した論文対策法】
論文試験は論理的な構成力と説得力が求められます。合格者はこれらを磨くために、実践的な対策を行っています。
📚 ① 過去問を徹底的に研究する
- 合格者は過去3〜5年分の論文テーマを分析し、頻出傾向を把握しています。
- 同様のテーマが出題された場合に備え、事前に構成パターンと施策案を準備しています。
✅ 例:頻出テーマへの事前準備
- 【少子高齢化】→「背景→課題→解決策」の型で構成案を作成
- 【防災対策】→「現状の課題→具体策→実現性と効果」をパターン化
✍️ ②「型」を決めて構成をテンプレ化
- 合格者は論文の型をテンプレ化して対策しています。
- 本番でテーマが変わっても、テンプレートに沿って書くことで構成が崩れず安定した文章が書けるようになります。
✅ 論文テンプレ構成例
- 序論: テーマの背景と重要性を提示(現状や課題の説明)
- 本論: 課題の詳細な分析と具体的な対策を提案
- 結論: 実現可能性と期待される効果を述べる
📰 ③ 時事問題を絡めた具体策を準備
- 合格者は最新の時事問題と行政施策をチェックし、論文で使える具体例をストックしています。
- ニュース記事や行政の公式発表を引用することで、説得力が増します。
✅ 例:時事問題を取り入れた具体策
- 「DX推進による行政効率化」をテーマに、マイナンバー活用の事例を引用
- 「防災対策」をテーマに、能登半島地震での行政支援を具体例として紹介
📊 ④ 模範答案と自作論文を比較する
- 合格者は予備校の模範答案や合格者の論文例と自作論文を比較して対策しています。
- 論理展開や説得力の違いを確認し、修正を繰り返すことで完成度を高めます。
✅ 実践方法
- 模範答案と自作論文を並べて比較
- 論理展開や表現をチェックし、改善ポイントを洗い出す
- 再度修正して完成度を高める
【合格者が実践した作文対策法】
作文試験は自己表現力と説得力が重要です。合格者は読み手に伝わる文章を書くために、次の対策を行っています。
📚 ①「体験談+意見」の型で対策
- 合格者は作文で具体的な体験を交えて説得力を高める工夫をしています。
- 抽象的な意見だけでなく、具体的なエピソードを交えることで説得力がアップします。
✅ 作文の構成パターン
- 導入: テーマに関連する体験談を述べる
- 本論: 体験から得た教訓や考えを論じる
- 結論: 自分が公務員としてどう活かすかを述べる
✍️ ② 感情や想いを具体的に表現
- 合格者は作文で感情や価値観を具体的に表現しています。
- 「嬉しかった」「悔しかった」などの心情を丁寧に描写することで共感を得やすくなります。
✅ 例:感情表現を具体的にする
- NG:「ボランティアでやりがいを感じた」
- OK:「被災地で瓦礫を撤去する作業は体力的に辛かったが、『ありがとう』と言われた瞬間、達成感と喜びで胸がいっぱいになった」
📊 ③「原稿用紙の使い方」を徹底練習
- 合格者は原稿用紙の使い方でミスを防ぐ練習を繰り返しています。
- 「文字数」「行の折り返し」「句読点の位置」など細かなルールを守ることで、減点を防ぎます。
✅ 原稿用紙のミス防止ポイント
- 「。」や「、」で行が変わる場合は1マス空ける
- 「改行時に一文字下げる」を徹底
- 文字数制限内で収める練習を繰り返す
📰 ④ 第三者に添削を依頼して修正
- 合格者は第三者に作文を見てもらい、フィードバックを受けることで完成度を高めています。
- 特に「表現がわかりづらい箇所」や「説得力の弱い部分」を指摘してもらうことで修正精度が向上します。
✅ 実践方法
- 自作作文を予備校や指導サービスで添削依頼
- 指摘された箇所を修正し、文章の質を向上させる
- フィードバックを基に再度書き直す
論文・作文試験で差をつけるならアガルート!
\無料サンプル講座で実力をチェック👇/
【論文・作文で評価が下がるNG例と対策】
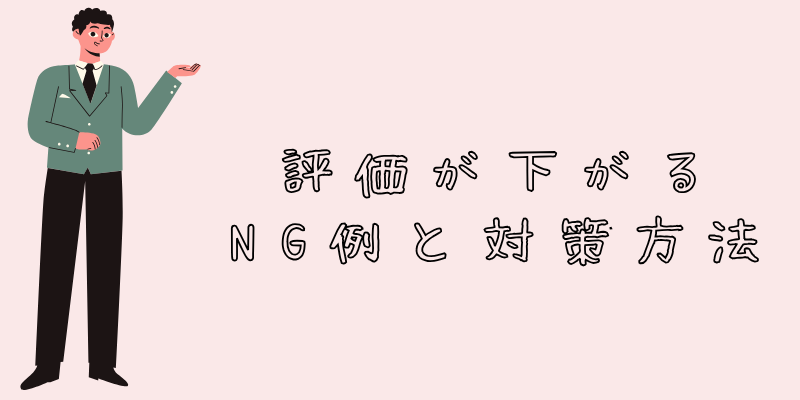
【論文試験で評価が下がるNG例と対策】
NG例1:論理が飛躍しすぎている
- 論文は一貫した論理的な展開が求められますが、論理が飛躍していると評価が大きく下がります。
- 対策: 各段落の内容が前後と論理的に繋がるように、結論に至るまでの流れを丁寧に組み立てましょう。特に**「なぜその結論に至るのか」を説明**し、読者に理解させることが重要です。
✅ 改善方法:
- 各段落のテーマを意識し、一つの論点を深掘り
- 例え話やデータを使って論理を裏付ける
NG例2:解決策が抽象的で具体性に欠ける
- 提案する解決策が抽象的で漠然としている場合、説得力に欠けてしまいます。
- 対策: 提案する施策や解決策は具体的かつ現実的な内容にしましょう。現状分析に基づいた具体例や事例を用いることで、より実現可能性の高い説得力ある解決策が提示できます。
✅ 改善方法:
- 自分の提案を具体的な事例やデータで支える
- 具体的な施策(予算案、施策実施手順)を提示
NG例3:テーマから逸脱してしまう
- テーマから外れた内容を述べると、評価が下がります。特に論点がずれた内容や関係のない話題を持ち出すことが問題です。
- 対策: 出題されたテーマにしっかりと沿った内容を展開し、脱線しないように毎段落でテーマに関連する話題を述べることを意識しましょう。
✅ 改善方法:
- テーマを明確に意識して、脱線しない構成を作る
- 論点を整理し、中心から外れないように確認する
【作文試験で評価が下がるNG例と対策】
NG例1:感情の表現が過剰または不自然
- 作文では自己表現が重要ですが、感情を過剰に表現することで不自然さが出てしまうことがあります。
- 対策: 感情を表現する際は具体的な状況や体験を交えて自然に伝えることが大切です。「感動した」「嬉しかった」などの表現だけではなく、どのような状況でどんな感情が湧いたのかを詳しく説明しましょう。
✅ 改善方法:
- 具体的なエピソードや体験を交えた感情表現を使う
- 感情に言葉を与えることで、読者が共感できる表現を心がける
NG例2:表現が単調で退屈
- 一辺倒な表現や繰り返しを多く使ってしまうと、作文が退屈に感じられます。
- 対策: 表現にバリエーションを持たせることで、読者を引き込むことができます。異なる言葉や視点で意見を述べたり、比喩や具体例を使うことが効果的です。
✅ 改善方法:
- 同じ言葉の繰り返しを避け、表現に工夫を加える
- 例え話や比喩を使って印象を強める
NG例3:誤字・脱字が多い
- 作文は字数制限の中でスムーズに書く必要があり、誤字や脱字が多いと減点対象になります。
- 対策: 書き終わったら必ず文章を見直し、誤字・脱字をチェックします。また、時間を意識して余裕を持った見直しをすることが重要です。
✅ 改善方法:
- 見直し時間を必ず確保し、誤字脱字を確認
- 長文を書く際は、段階的に確認しながら進める
論文・作文試験で差をつけるならアガルート!
\無料サンプル講座で実力をチェック👇/
📌 論文・作文対策に役立つおすすめ講座
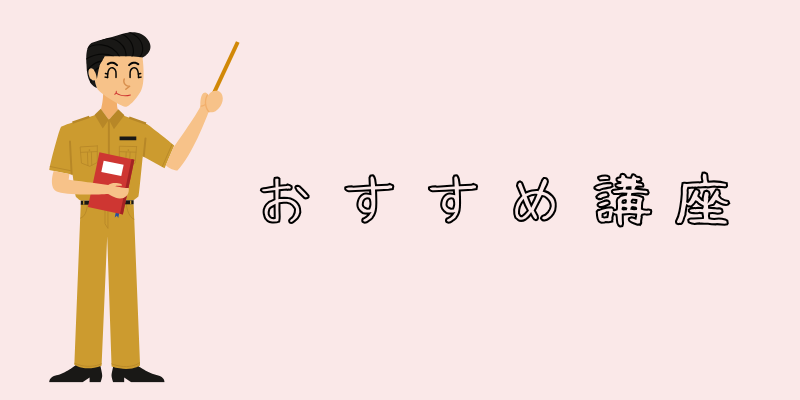
アガルートの論文対策講座
論文・作文試験の合格には、効果的な学習と適切な指導が不可欠です。そこでおすすめするのが、アガルートの論文対策講座です。アガルートは、豊富な教材と丁寧な指導で多くの合格者を輩出している信頼性の高い講座です。
特徴とメリット
- 実践的な内容: 実際の試験に即した演習を通じて、論文作成のスキルを効率よく向上させることができます。
- 個別指導: 提出された論文に対して、講師から具体的なフィードバックがもらえるため、自分の弱点を明確にし、短期間で改善できます。
- カリキュラムの充実: 初心者から上級者まで対応できる段階的なカリキュラムが用意されており、自分のペースで学習を進めることができます。
- 過去問を中心に学ぶ: 過去の試験問題を徹底分析し、試験に出やすいテーマや解法を学べるため、実践力が身につきます。
まずはサンプル講座を受講してみましょう
アガルートの論文対策講座には、無料サンプル講座も提供されているので、まずはそれを受講してみましょう。サンプル講座を通じて、実際の講座の内容や講師の指導スタイルを体験できるため、自分に合った講座かどうかを確認できます。
サンプル講座では、基礎的な部分から実践的な演習まで、短時間で効果的に学べる内容が盛り込まれています。これにより、アガルートの講座が自分の学習スタイルに合うかどうかを試すことができます。
論文・作文試験で差をつけるならアガルート!
\無料サンプル講座で実力をチェック👇/
論文・作文が上手くなるコツ

最後に、論文・作文がうまくなる秘訣を紹介します。
- 合格する論文・作文を読む
- 実際に書いて比較・添削する
上記2点が、論文・作文のレベルを上げるためには必須です。
合格する論文・作文を読む
あなたの最終目標は「合格する論文・作文を書くことができる」ですよね。
であれば、まずはどの論文・作文が合格できるのか、そのレベルを把握しておく必要があります。
多くの受験生はここができておらず、読みづらい構成、中身のない文章を書いてしまうケースが多いんです。
自分が書くべき合格する論文・作文がわからないと、どの方向性で対策を進めていけばいいかわかりませんよね?
まずは、合格レベルの論文・作文をしっかり読み込んで自分自身が書けるようになるべき文章を理解するようにしましょう。
実際に書いて比較・添削する
合格できる論文・作文が理解できたら、あとは実際に書いていくだけです。
この記事で紹介した、論文を書く時の注意点や視点を織り込んで、合格論文・作文の構成、書き方を見本に書いていきましょう。
そして、書いたあとは合格論文・作文と比較する。もしくは、第三者に添削してもらいフィードバックを必ず受けてください。
論文試験は、あくまで人が採点します。第三者が見てどう思うのか、その意見は貴重です。
可能であれば、近くの論作文に精通した人に見てもらうのがベストですが、難しいようであれば以下のサービスを利用してみてください!
はじめはうまく文章を書くことができないと思います。
しかし、このステップを繰り返し行うことで確実に合格レベルの論文・作文に近づくはずです。
論文・作文試験で差をつけるならアガルート!
\無料サンプル講座で実力をチェック👇/
まとめ

本日は、論文・作文の違いから出題例、書く際の注意点についてお話ししました。
以下に、本記事のまとめを作成しておきます!
・論文とは、100人が読んで100人が納得する論理的な構造の文章である
・論文試験は国家一般職、都県職員、地方市役所(大卒程度)で多く出題される
・作文とは、自分の体験、経験から学んだ自分自身の意見、考えである
・作文試験は地方市役所(高卒程度・初級)公安系で多く出題される
・いきなり書き始めない
・情報分析→構成の立案→本文の順で書く
・行政職員の視点を入れ込む
これらの内容を意識して対策を進めていけば、高い確率で合格する論文・作文が書けるようになるはずです。
また、以下の記事ではさらに詳しく【論文の書き方】にフォーカスしてまとめていますので、ぜひご参考にしてみてください。
論文・作文試験で差をつけるならアガルート!
\無料サンプル講座で実力をチェック👇/