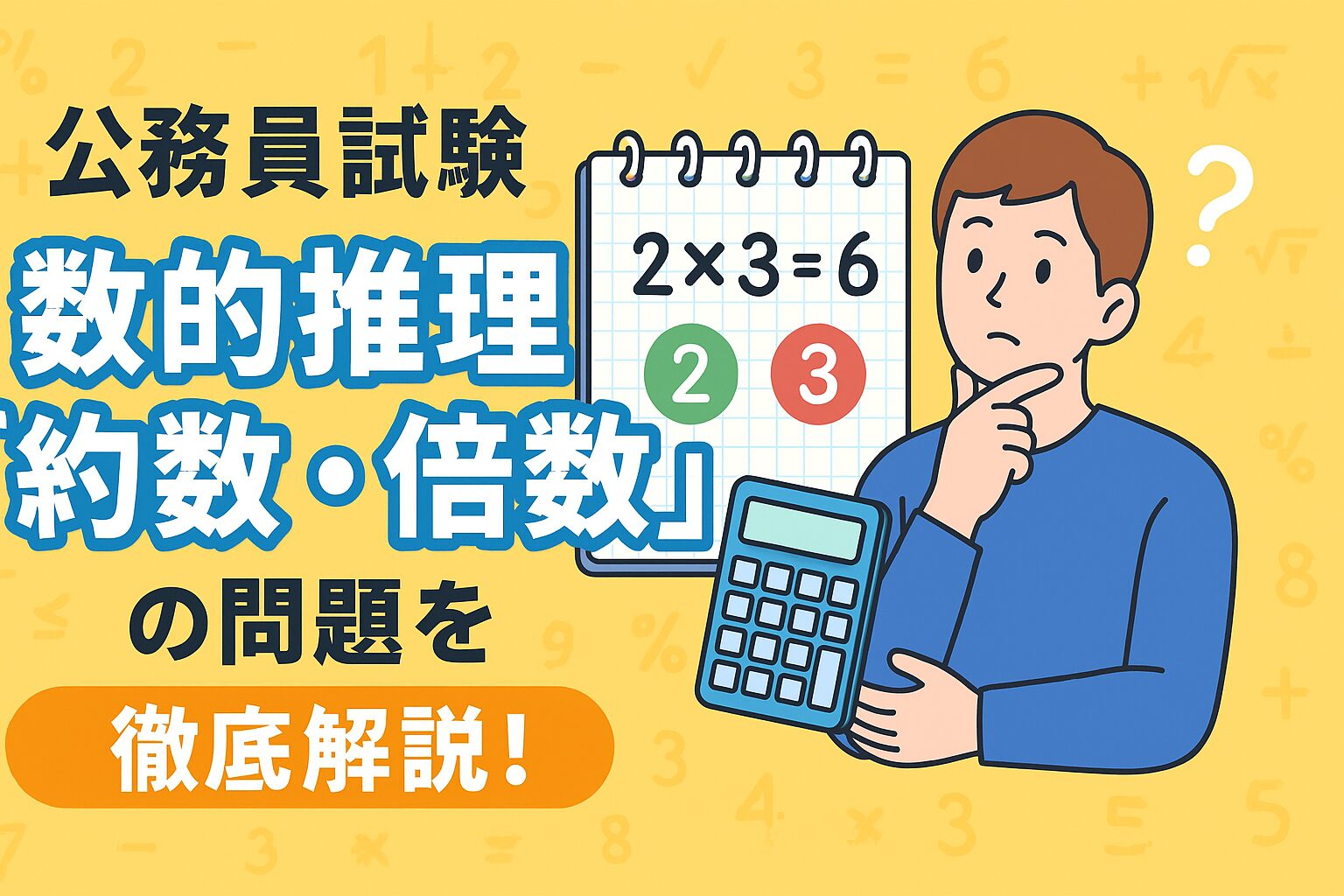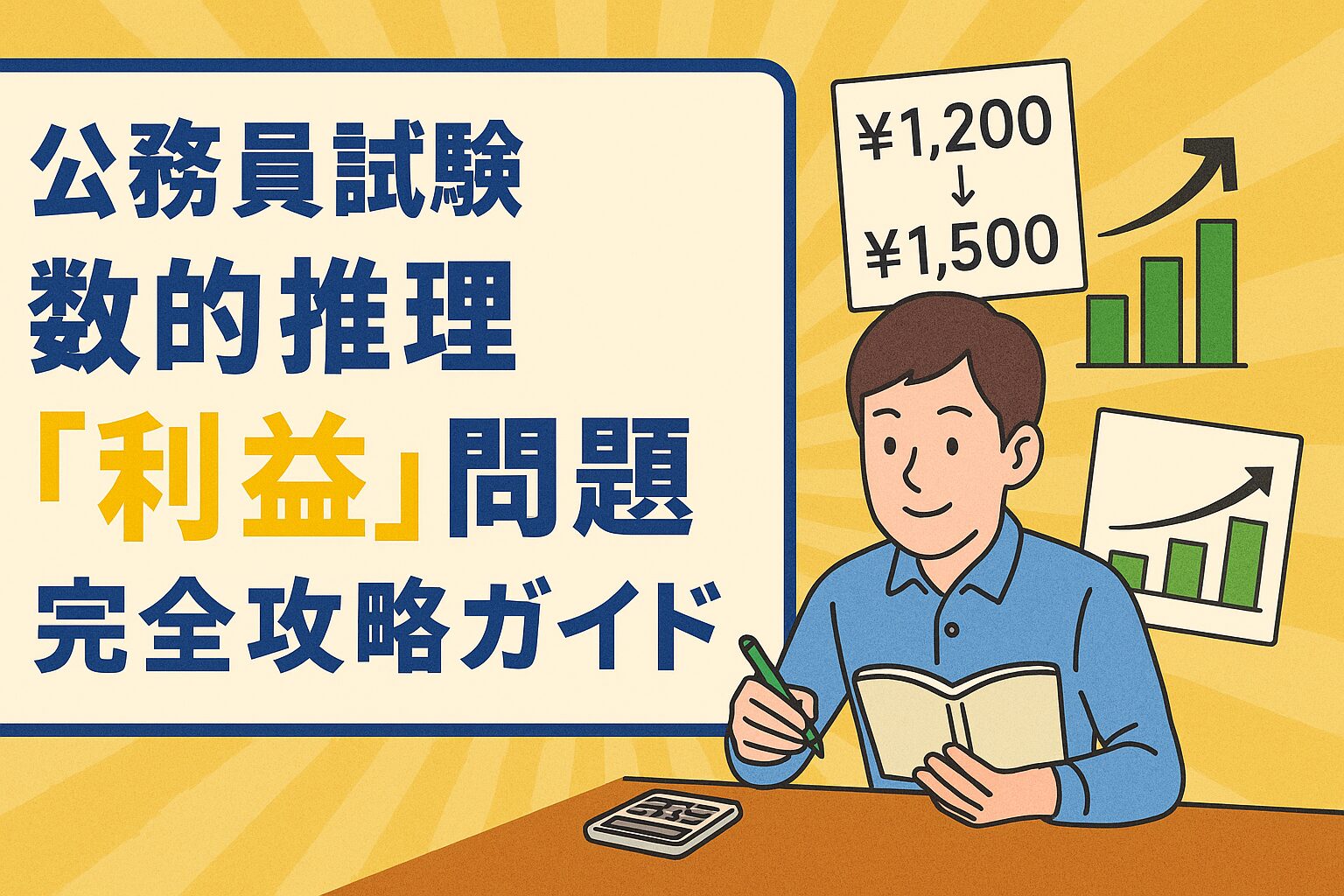はじめに:なぜ「比と割合」は数的推理で超重要なのか?
公務員試験の数的推理の中でも、「比と割合」は最も基礎でありながら、得点差がつきやすい分野です。 一見シンプルに見えますが、問題の中では速さ・仕事・食塩水など、他のテーマと複雑に組み合わされて出題されることが多いのが特徴です。
「比と割合」は数的推理の“基礎公式”のような存在。 この単元を理解していないと、他の分野(速さ・濃度・損益など)の解法がすべて曖昧になります。
📊 出題頻度が高く、得点効率が抜群!
各自治体の公務員試験では、数的推理の出題の約3〜4問に1問が「比と割合」に関連しています。 特に国家一般職、市役所、警察官・消防官試験などでは、出題頻度トップクラスです。
また、「比と割合」は一度理解してしまえば、暗記ではなく“考え方”で解けるため、 学習効果が非常に高い分野です。つまり、ここをマスターすると他の単元も一気に理解しやすくなります。
💬 苦手を放置するとどうなる?
「比と割合」が苦手なまま数的推理を進めると、速さ・濃度・損益・仕事算などの応用問題で必ずつまずきます。 これらのテーマはすべて、“比の考え方”を使って解く構造になっているためです。
📈 合格者は“比と割合”を得点源にしている!
実際、合格者の多くは口を揃えてこう言います。
👉「最初に“比と割合”を完璧にしておくと、後が本当に楽になる」と。
それほどまでに得点アップのカギを握る単元です。
この記事では、そんな「比と割合」を初学者にもわかりやすく、 図解や例題を交えながら解説していきます。💪 スタディングの教材を活用しつつ、一緒に“苦手を得点源”に変えていきましょう!
「比と割合」の基本を3分で理解する
ここでは、数的推理でよく出る「比と割合」の考え方を、 3分で理解できるようにシンプルに整理します。 この基礎が理解できれば、応用問題でも迷わなくなります!
📏 比と割合の違いを整理しよう
まず、「比」と「割合」は似ているようで目的が違う概念です。
たとえば、AさんとBさんの得点が「60点と80点」の場合、 比は 60:80=3:4 になります。 一方、「Aさんの点数はBさんの75%」という表現は割合です。
「比」はもの同士をくらべる。
「割合」は全体を1(100%)としてくらべる。
🧮 比例・反比例の考え方もセットで理解
比と割合を学ぶときにセットで出てくるのが比例・反比例です。 これは“比の変化”を扱う考え方です。
⚙️ 反比例: 片方が増えるともう一方が減る(例:人数×作業時間=一定)
公務員試験では「仕事算」「速さ」などで頻繁に使われます。 つまり、“比を正しく使える=応用問題が速く解ける”ということです。
💡 「1を基準に考える」割合思考がカギ
割合の問題では、“1を基準”に考える習慣をつけましょう。 例えば「AはBの120%」というのは、 「A = B × 1.2」と考えるだけで、暗算もスムーズになります。
あるクラスの男子が女子の1.5倍いるとき、女子が20人なら男子は?
→ 男子 = 20 × 1.5 = 30人
👉 「割合=基準×何倍」 の考え方を使えば即答!
このように、「比」と「割合」は別々の概念に見えて、 実は“同じ考え方で整理できる”ことがわかります。 次章では、この基礎をもとに頻出パターンを攻略していきましょう!
公務員試験でよく出る「比と割合」頻出パターン
「比と割合」の問題はバリエーションが多く、混乱しやすい分野ですが、 実際にはいくつかの定番パターンを理解しておけば十分対応できます。 ここでは、特に公務員試験で頻出の4パターンを紹介します!
① 内項・外項を使った比の計算
「比の内項・外項」とは、比の関係を利用して未知数を求める考え方です。 公式の形で覚えるより、次のように理解するのがおすすめです。
3:x=6:8 のとき、xを求めよ。
→ 外項どうし 3×8 = 内項どうし 6×x
→ x = (3×8) ÷ 6 = 4
このように、比の関係では「外項の積=内項の積」が常に成り立ちます。 “クロス掛け”をイメージするとすぐに解けます!
② 食塩水などの混合問題
混合問題は、「濃度の比」で考えるのがポイントです。 「量」と「濃度」を比で整理すると、頭の中がスッキリします。
濃度10%の食塩水200gと、濃度20%の食塩水300gを混ぜると?
→ 食塩の量=200×0.1+300×0.2=80g
→ 全体の重さ=200+300=500g
→ 濃度=80÷500=16%
このように、“全体の重さを1にする”考え方を使うと計算がスムーズです。 割合を数字で扱えるようにしておくと、応用問題にも対応できます。
③ 速さ・時間・距離を比で処理する問題
公務員試験では「速さ×時間=距離」の関係を比で扱う問題が多いです。 3つのうち2つの比を知れば、もう1つも自動的に決まるのが特徴です。
AとBが同じ距離を走る。Aの速さはBの1.5倍、時間の比を求めよ。
→ 距離一定 → 時間は速さに反比例
→ 時間の比=1:1.5 の逆比 → 2:3
この「反比例」を理解していると、速さ・仕事算などの応用問題が一気に簡単になります!
④ 比の分配・配分問題(応用)
比を使った「お金・人数・作業量」の分け方問題も頻出です。 このときは、全体を比の合計で割る考え方を使いましょう。
3000円を A:B:C=2:3:5 で分けるとき、Bの金額は?
→ 合計比=2+3+5=10
→ Bの取り分=3000×(3/10)=900円
この考え方は、「仕事の配分」「収益の分担」などにも応用可能です。 比を“全体のうちの割合”としてとらえるのがコツです。
公務員試験では、以下4パターンを確実にマスターしておけばOK!
・内項・外項の比の計算
・濃度や割合の混合問題
・速さや時間の比活用
・配分・分配の応用問題
次章では、これらのパターンを実際に使った例題と解法ステップを紹介します!📘 図と一緒に理解すると、頭の中で整理しやすくなりますよ。
実際に解いてみよう!比と割合の例題と解法ステップ
ここでは、実際の公務員試験で出題されるような「比と割合」問題を例に、 ステップごとに解法を解説します。 解き方の流れをつかむことで、どんな問題でも迷わずアプローチできるようになります!
例題①:速さの比を使った基本問題 🚗
AとBが同じ距離を走る。Aの速さはBの1.25倍である。 それぞれがかかる時間の比を求めよ。
ステップ①:速さの比を設定する → A:B=1.25:1=5:4
ステップ②:距離が同じなら時間は反比例 → 時間の比=4:5
✅ 答え: A:B=4:5
このように、「速さが大きい人は時間が短い」という反比例の関係を 比で整理すると、一瞬で答えが出ます。
例題②:混合問題(食塩水)🧂
濃度10%の食塩水200gと、濃度30%の食塩水300gを混ぜたとき、 何%の食塩水ができるか?
ステップ①:食塩の量を出す。 → 200×0.1+300×0.3=20+90=110g
ステップ②:全体の重さを求める。 → 200+300=500g
ステップ③:割合を出す。 → 110÷500=0.22=22%
混合問題では「全体を1にする」考え方がカギです。 濃度=食塩の量 ÷ 全体の重さ、の形で整理すると計算が迷いません。
例題③:比の配分問題 💰
A・B・Cの3人がある仕事を分担した。作業量の比が 2:3:5 のとき、 報酬30万円を比に応じて分ける。それぞれの取り分はいくらか?
ステップ①:比の合計=2+3+5=10
ステップ②:1単位あたりの金額=30万円÷10=3万円
ステップ③:比に応じて分配 → A:6万円/B:9万円/C:15万円
✅ 答え: A=6万円、B=9万円、C=15万円
公務員試験では、「仕事量」「報酬」「時間」「人数」などを すべて“比で処理”できるようにしておくと、計算が圧倒的に速くなります。
例題④:応用問題(複合割合)📊
ある商品の原価が1,200円で、これを20%の利益を見込んで定価をつけた。 さらに定価の10%引きで販売したとき、利益率はいくらか?
ステップ①:定価=1,200×1.2=1,440円
ステップ②:販売価格=1,440×0.9=1,296円
ステップ③:利益=1,296−1,200=96円
ステップ④:利益率=96÷1,200=8%
このように、割合の連鎖は“掛け算でつなげる”と速く正確に求められます。 公務員試験では特に「損益・値引き」系の問題で頻出です。
まとめ 📘
「比と割合」は、一見単純に見えて多くの問題の根本を支える基礎力です。 本章で扱ったステップをマスターすれば、応用問題もスムーズに解けるようになります。
・比=もの同士の関係、割合=全体に対する関係
・混合・速さ・仕事・損益など、すべて比の応用で解ける
・数値を「1」基準で考えるクセをつける
次章では、これらの知識をどう活用して数的推理の得点を最短で伸ばすかを解説します!✨
「比と割合」を攻略して数的推理を得点源にする勉強法
「比と割合」は、数的推理の中でも基礎であり最強の得点源です。 ここからは、公務員試験に向けて効率的に点を取るための学習戦略を紹介します💪
① 理屈よりも“比の感覚”を身につけよう
公務員試験の出題では、計算式よりも比の感覚が問われます。 たとえば、「速さが1.2倍になったら時間はどうなる?」といった問題では、 反比例のイメージで “時間は1/1.2=5/6倍になる” と瞬時に判断できるかが勝負。
比と割合の問題は「公式」ではなく「イメージ化」がカギ!
速さ=車のスピードメーター、割合=円グラフの切れ目、など
視覚的に覚えると長期記憶に定着しやすくなります。
② 問題演習は「パターン別」に固める
いきなり過去問を解くよりも、まずはパターン別に反復練習するのがコツです。 たとえば次のように分類して演習を進めましょう。
① 基礎比(内項・外項)
② 割合・濃度・配分
③ 速さ・時間・距離の比
④ 応用(損益・混合・仕事算)
これらを一日1テーマずつ進めると、1週間で比と割合の全パターンを網羅できます。 模試や本試験では「どのパターンか瞬時に見抜く」訓練が最重要です。
③ ミスを分析して「思考の型」を作る
問題演習をしても、同じミスを繰り返す場合は、思考の順番に原因があります。 そのため、以下の3ステップを毎回意識しましょう👇
① 「何を比べているのか」を明確にする(速さ?人数?金額?)
② 「全体=1」を意識して整理する
③ “比を使って計算を簡略化”する
この型を使うことで、公式を暗記しなくても自然と答えにたどり着けるようになります。 試験時間の短縮にもつながるため、得点効率が一気に上がります✨
④ 効率よく学ぶなら「スタディング」で一気に攻略
比と割合は「わかっているつもり」になりやすい分野です。 そこでおすすめなのが、動画+スマホでサクッと学べる スタディング公務員講座です。
・通勤時間などのスキマで学べる動画講義🎧
・数的推理・判断推理の「出題傾向別講義」で超効率的
・AI分析で自分の弱点を自動チェック🧩
実際、スタディング受講者の多くが「数的推理が得点源になった」と回答しています。 体系的に比と割合を学べる教材として、特に初学者に最適です。
⑤ 継続のコツ:「毎日15分×7日ルール」
難しい問題を長時間解くより、毎日短時間で反復する方が効果的です。 1日15分、1テーマずつ復習するだけで、1週間後には確実に“得点力”が上がります。
月:比の基本/火:割合の基本/水:速さと比
木:配分/金:濃度/土:応用問題/日:復習+過去問
継続できる人が合格に一番近いです。 無理のないペースで、比と割合を自分の武器にしましょう💪
・比の“感覚”を身につけることが最優先
・パターン別に整理して繰り返す
・勉強の流れをサポートしてくれる教材を活用する
次章では、実際に合格者がどのように比と割合を学んで得点を伸ばしたか、 スタディング受講者の実例を紹介します!
スタディングで「比と割合」を武器にした合格者の声
「比と割合は苦手だったのに、スタディングを使って得点源になった」 ― そんな受講者の声が多く寄せられています。ここでは、実際に合格をつかんだ 公務員試験受験者のリアルな体験談を紹介します。✨
🎓 受講者Aさん(地方上級・合格)
After: 「スタディングの動画で『なぜそうなるのか』を図で説明してくれるから、 数字の関係が一瞬で理解できました。繰り返し視聴できるので、 苦手意識がなくなり、試験本番ではこの分野で満点を取れました!」
👩💼 受講者Bさん(市役所上級・合格)
After: 「スタディングの講義では“実際の数値で考える練習”ができるのが良かった! クイズ形式でテンポよく進むので飽きずに学べ、 気づけば比の問題が一番得意になっていました。」
🧠 受講者Cさん(国家一般職・合格)
After: 「『速さ・割合・仕事算』の関係が図で整理されていて、 問題を見るたびにどの公式を使えばいいかわかるように。 AI分析機能で弱点をピンポイント復習できたのも大きかったです。」
どの合格者も口をそろえて言うのが、「理解の速さ」と「効率の良さ」です。 スタディングは、苦手をつぶすだけでなく、 “得点を最短で上げる導線”を設計してくれる教材です。
スタディングを活用するメリットまとめ 💡
- 📱 スマホ1つでスキマ時間に学習できる
- 🎥 図とアニメーションで比・割合を直感的に理解できる
- 🧩 AIが自動で弱点分析をしてくれる
- 🕐 忙しい社会人・学生でも無理なく継続できる
公務員試験対策を最短で進めたいなら、今すぐチェック👇 ▶ スタディング公務員講座公式サイトはこちら
次章では、比と割合をマスターした後に取り組むべき 「数的推理の得点アップ戦略」を紹介します。📘
まとめ:比と割合を制す者が数的推理を制す!
「比と割合」は、公務員試験の数的推理における基礎中の基礎であり、最大の得点源です。 ここまで学んできた内容を整理して、今後の学習に役立てましょう📘
✅ 「比」と「割合」は数的推理の土台。速さ・仕事・濃度など全ての問題に応用できる。
✅ 問題は“比の感覚”で捉えると計算が一気にラクになる。
✅ 図や表を使って整理するクセをつけよう。
✅ 継続学習がカギ。短時間×毎日の習慣化で得点が安定する。
✅ 苦手克服には「動画+AI学習」で効率UPできる教材を活用!
💡 最後に:スタディングで「理解の速さ」を体感しよう
「比と割合」は、ただの暗記ではなく理解と慣れがすべてです。 そこで最もおすすめなのが、 スマホ1つで体系的に学べる スタディング公務員講座 です。
・数的推理の基礎を効率よく学びたい
・問題を解くスピードを上げたい
・スマホでスキマ時間を活用したい
・自分の弱点をAIで分析して克服したい
公務員試験は、知識量よりも思考スピードが問われる試験です。 「比と割合」をマスターすれば、数的推理全体の得点が安定し、 合格ラインをぐっと引き上げることができます。
まずは一歩踏み出して、スタディングで自分のペースで学び始めましょう🚀 ▶ スタディング公務員講座【公式サイトを見る】
「比と割合」を制する者は、数的推理を制す。 小さな理解の積み重ねが、合格への最短ルートです!
公務員試験は「理解力×継続力」で勝てる!あなたも今日から一歩前へ✨