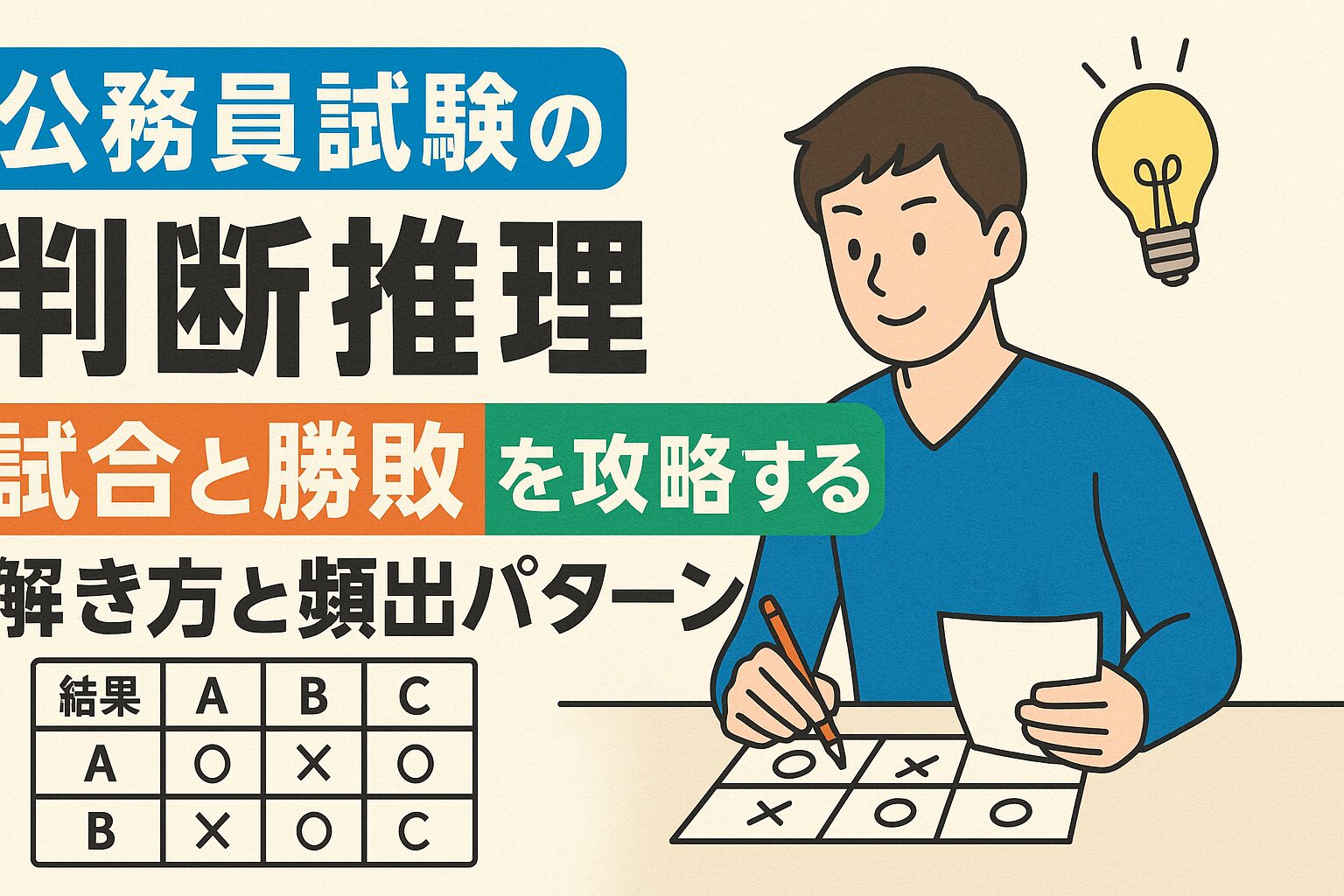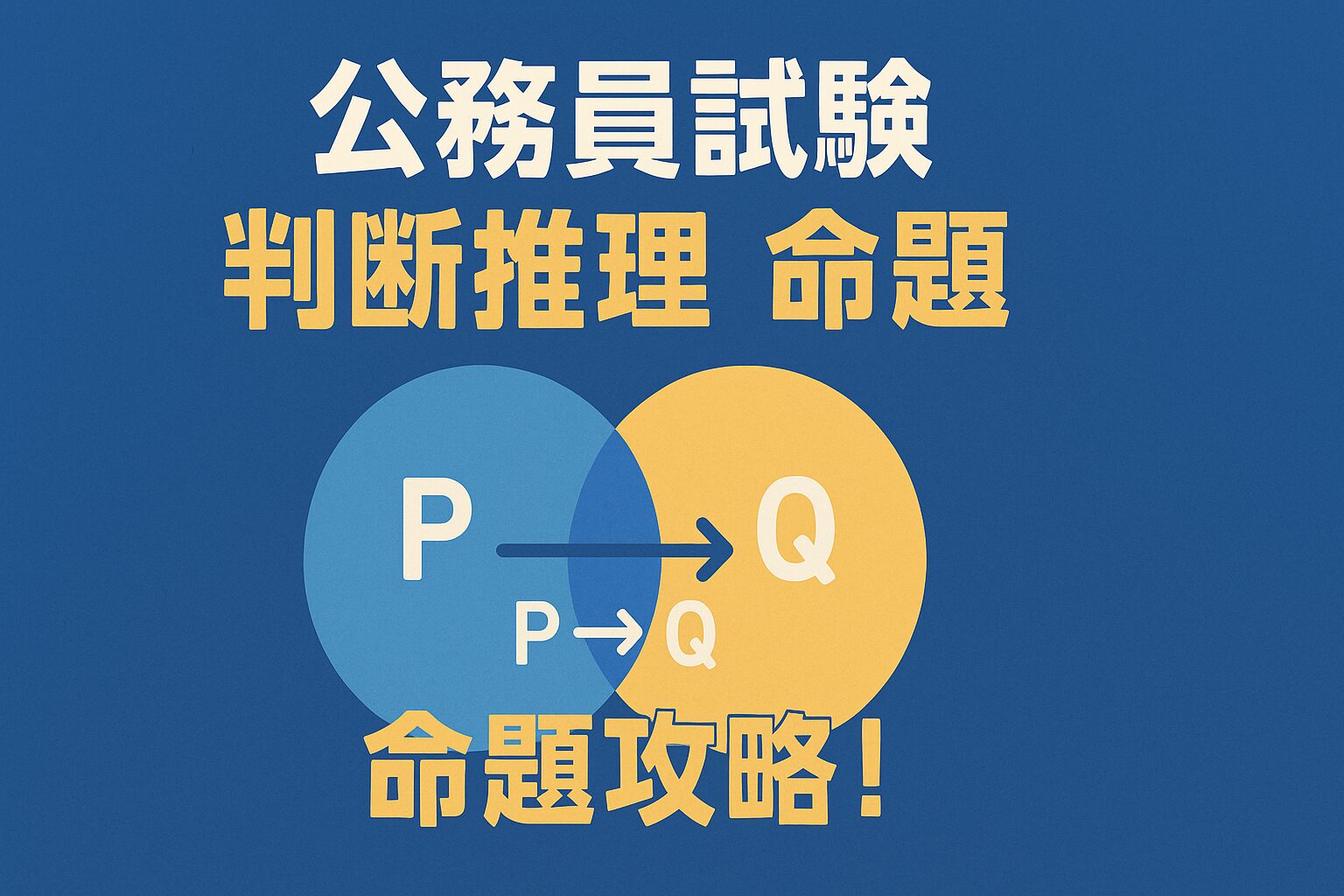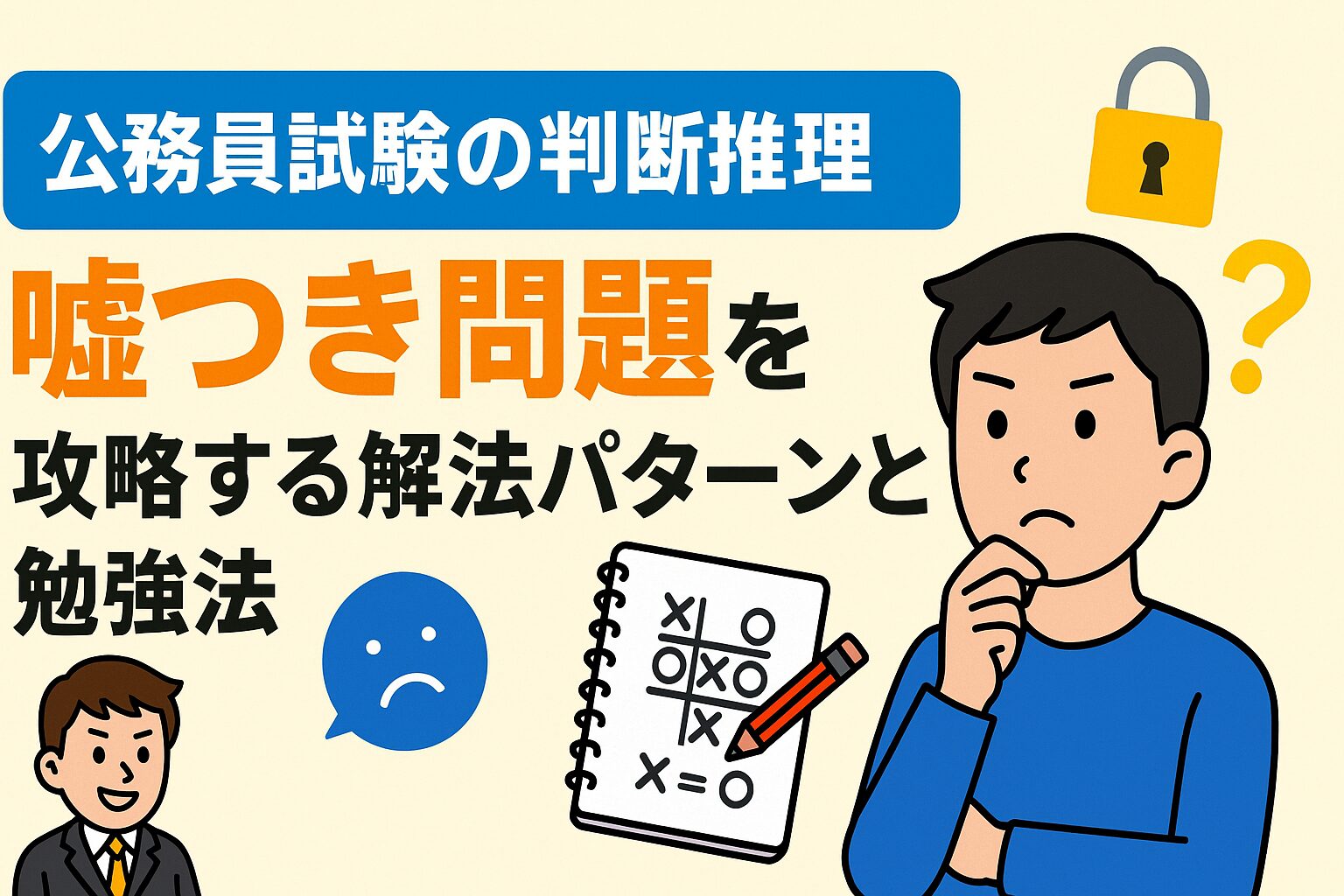判断推理「試合と勝敗」はなぜ重要?
公務員試験の判断推理分野の中でも、試合と勝敗は毎年のように出題される定番テーマです。 「スポーツの結果をもとに順位を決める」といった身近な内容ですが、論理的思考力・情報整理力が問われます。
📌 試合と勝敗が出題される理由
- 限られた条件から正しい結論を導く力を見るため
- 短時間で複数の情報を整理する力を測るため
- 論理的に矛盾を見抜く力を評価するため
📌 苦手にする人が多い理由
- 勝敗表や順位表の作り方に慣れていない
- 情報が多く、どこから手をつけていいか分からない
- ミスすると芋づる式に間違える
実は「試合と勝敗」はパターンを覚えれば一気に得点源になります💡
しかも出題頻度が高いので、コスパが非常に高い分野です。
次の章では、実際の公務員試験でどれくらい出題されているのか、出題傾向と頻出パターンを紹介します。
出題傾向と頻出パターン
判断推理「試合と勝敗」は、国家・地方問わず毎年コンスタントに出題されています。 出題形式は主にトーナメント形式と総当たり形式の2つに分かれ、どちらもパターンをつかめば確実に得点できます。
📊 過去の出題頻度(目安)
| 試験区分 | 出題頻度 | 難易度 |
|---|---|---|
| 国家一般職 | 2年に1回程度 | やや難 |
| 地方上級 | ほぼ毎年 | 標準 |
| 市役所・警察・消防 | ほぼ毎年 | やさしめ |
※年度によって多少の変動はあります
📌 主な出題パターン
- トーナメント形式:勝ち抜き戦で優勝者を決める問題
- 総当たり形式:全員が一度ずつ対戦し、順位を決める問題
- 順位決定型:一部の結果が分かっている状態で、残りを推理する
📌 得点戦略としての重要性
・グラフや表で整理できるので慣れると短時間で解ける ・論理的に正解が一つに決まるのでケアレスミスが少ない ・時間をかけずに確実に点が取れる=得点効率が高い
次の章では、「試合と勝敗」を解くために欠かせない基礎ルールをわかりやすく解説します。
基礎ルールをマスターしよう
「試合と勝敗」の問題を解くには、勝敗表(○×表)や順位決定のルールをしっかり理解しておく必要があります。 ここでは、最初に覚えるべき基本ルールを紹介します。
📌 勝敗表(○×表)の作り方
総当たり戦では、選手A〜Dがそれぞれ全員と1回ずつ対戦します。結果を次のように記録します。
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| A | – | ○ | × | ○ |
| B | × | – | ○ | × |
| C | ○ | × | – | ○ |
| D | × | ○ | × | – |
○=勝ち ×=負け
📌 順位の決め方
- 勝ち数(勝ち点)が多い選手が上位
- 同点の場合は得失点差や直接対決結果で順位を決める
- トーナメント戦では、負けたら即敗退(シングルエリミネーション)
📌 引き分け・得失点差の扱い
- 引き分け=勝ち点0.5または1としてカウントされる場合がある
- 得失点差は「得点−失点」で計算
- 条件に書かれている場合のみ使用される(問題文をよく読む!)
このような基礎ルールを頭に入れておくことで、複雑な問題もスムーズに解けるようになります✨ 次は、実際に例題を使って解き方の流れを確認していきましょう。
【例題付き】試合と勝敗を解いてみよう
ここでは、実際の公務員試験でも出題される形式に近い例題を用いて、解き方の流れを解説します。
📌 例題
A〜Dの4人が総当たり戦を行い、以下の結果がわかっています。
- AはBとCに勝ち、Dに負けた
- BはCに勝ち、Dに負けた
- CはDに勝った
このとき、勝ち数が最も多い人は誰か?
📌 ステップ① 勝敗表を作る
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| A | – | ○ | ○ | × |
| B | × | – | ○ | × |
| C | × | × | – | ○ |
| D | ○ | ○ | × | – |
📌 ステップ② 勝ち数を数える
- A:2勝
- B:1勝
- C:1勝
- D:2勝
📌 ステップ③ 結論を出す
勝ち数が最も多いのはAとD(2勝ずつ)です。
このように、表にしてから数えることでミスを防げます✨
次の章では、合格者が実際にやっていた解き方のコツを紹介します。
合格者が実践した解法テクニック
「試合と勝敗」問題は、慣れれば短時間で正確に解けます。 ここでは、実際に合格者が使っていたコツを紹介します。
📌 コツ① 表や図を先に作る
情報を読みながら頭の中で整理しようとすると混乱しがちです。 まず勝敗表(○×表)やトーナメント表を作成し、そこに結果を書き込むようにします。
📌 コツ② 確定情報から埋める
「Aは全勝」や「Bは全敗」など、確実な情報から埋めることで、他の結果も自然に決まっていきます。 推理問題は確定から広げるのが基本です。
📌 コツ③ 仮定を置いて考える
情報が少なくて判断できない場合は、仮にAが勝ったとすると…という形で2パターンに分けて考えます。 どちらかが矛盾すれば、もう一方が正解です。
📌 コツ④ 制限時間を意識する
「試合と勝敗」問題は、1問3〜4分を目安に解き切る練習をしましょう⏱ 本番では時間配分が得点力に直結します。
次の章では、受験生がやりがちなよくあるミスとその回避法を紹介します。
よくあるミスとその回避法
「試合と勝敗」問題は、ちょっとした見落としで全体が崩れてしまうのが怖いところです。 ここでは、受験生がやりがちなミスと、その防ぎ方を紹介します。
⚠️ ミス① 順位の取り違え
勝ち数が同じ選手が複数いた場合、直接対決の結果や得失点差が優先されることがあります。 問題文に順位決定の条件が書かれていないか必ず確認しましょう。
⚠️ ミス② 情報の見落とし
問題文の中に「Aは全勝した」などのヒント情報が紛れていることがあります。 最初に条件を箇条書きにするクセをつけると防げます。
⚠️ ミス③ 引き分けや得失点差の扱いミス
引き分けや得失点差は問題文に特別ルールが書かれていることが多いです。 普段通りのルールで解いてしまうと間違えるので、最初に確認しましょう。
💡ミス防止のコツは、「条件をすべて表にしてから考える」こと!
次の章では、合格者も実践していた効率的な練習方法と、短期間で力を伸ばすためのスタディング公務員講座の活用法を紹介します。
まとめ:試合と勝敗を得点源にして合格へ!
判断推理の試合と勝敗は、慣れれば確実に得点できる分野です。 苦手意識をなくして得点源にできれば、公務員試験全体の合格率もグッと上がります。
✔ 本記事のまとめ
- 「試合と勝敗」は出題頻度が高い定番テーマ
- 勝敗表(○×表)で整理するとミスが減る
- 確定情報から埋める・仮定を置いて考えるのがコツ
- ミス防止には条件を最初に箇条書きする
- 効率よく学ぶなら公務員講座が最短ルート
判断推理が苦手なままだと、他の受験生に差をつけられてしまいます。 今こそ「試合と勝敗」を攻略して合格にグッと近づきましょう!
試合と勝敗を制すれば、判断推理を制す。今日から一歩踏み出し、合格への道を切り開きましょう!