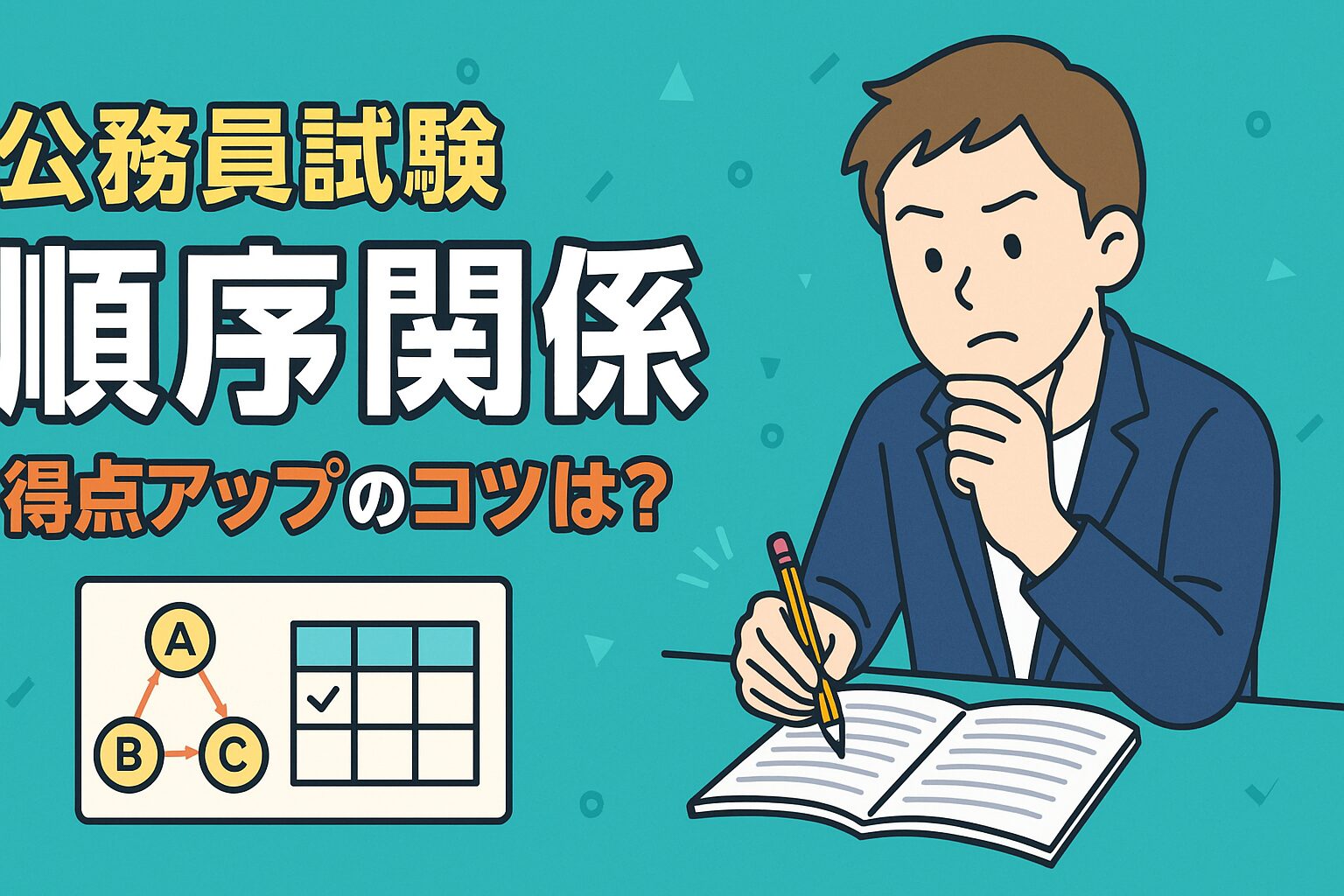はじめに:順序関係はなぜ重要なのか?
公務員試験の判断推理の中でも、「順序関係」は毎年ほぼ確実に出題される超定番分野です。 問題文に「AはBより前に並ぶ」「CはAの右隣に座る」など、位置や順番を推理する形式が多く出てきます。
✅ 出題の特徴
・人物・モノ・時間の「並び順」や「順位」を考える問題が中心
・論理力+整理力を問われる
・他の受験生と差がつきやすい“得点源”分野!
🎯 順序関係を制すと判断推理が得点源になる
順序関係は「表や線で整理すれば解ける」タイプの問題です。 計算問題のような公式暗記は不要で、論理の筋道を理解すれば誰でも得点できるのが魅力。
💬 例:
「AはBより早く到着し、Cより遅い」
→ AはBより上、Cより下と位置関係を整理すれば一瞬で図にできる!
📊 合格者が語る「順序関係」の重要性
実際に多くの合格者が、「判断推理の中でも順序関係が一番得点しやすい」と口を揃えています。 理由は、ルールを覚えたらパターンが決まっているから。
- 📘 条件を整理 → 表にまとめる → 矛盾を探すだけ!
- 🧩 難問でも手順は共通している
- ⚡ 繰り返し練習でスピードが上がる
✨ ここでの結論:
順序関係は「考えるより整理する」タイプの問題。
コツさえつかめば短期間で得点源に変えられる分野です。
次章では、順序関係の基本的な考え方と、代表的な出題タイプをわかりやすく整理していきましょう!
順序関係の基本:考え方と出題タイプ
順序関係の問題は、「条件を整理して順番を決める」という、判断推理の中でも基礎的な分野です。 一見難しそうに見えても、出題パターンは限られており、仕組みを理解すればスラスラ解けます。
🔍 順序関係とは?
複数の人・モノ・時間などに関して、
「どちらが先か」「何番目か」「どの位置か」などを推理して順番を決める問題です。
🧩 出題タイプはこの4つ!
| タイプ | 例 | 特徴 |
|---|---|---|
| ① 人物型 | AはBより前に並ぶ | 最も基本。順位や順番を整理 |
| ② 位置型 | Aは左から3番目 | 座席や並び位置を考える |
| ③ 時間型 | AはBより早く到着 | 時系列で前後関係を整理 |
| ④ 混合型 | AはCの右隣で、Bより先に出発 | 複数条件の融合型 |
💬 ワンポイント:
「誰が」「どの順で」「何をしているのか」
3つの視点で整理すると、情報の見落としが減ります!
🧠 解くときの基本手順(3ステップ)
- ① 登場人物や要素をリスト化(例:A・B・C・D)
- ② 条件文を読んで矢印や位置で関係づける
例:「A→B」ならAが先、Bが後 - ③ 表や線図を使って全体像を整理(※頭の中でやらない!)
✅ 重要ポイント:
文章をそのまま覚えようとせず、条件を“図に変換する”練習をしましょう。
これが順序関係攻略の第一歩です。
📈 順序関係が得意になる考え方
順序関係は、「矛盾がない配置」を探すゲームのようなものです。 だからこそ、正確さよりスピード重視で何度も練習すると感覚が身につきます。
💬 合格者の声:
「最初は時間がかかったけど、3問目あたりから自然に図が浮かぶようになった!」
→ つまり、順序関係は“慣れ”で差がつく分野です。
次章では、実際の例題を図解つきで紹介しながら、解き方の流れを体感していきましょう!
例題で理解する順序関係(図解付き)
順序関係は「慣れ」がすべて。ここでは、初級〜中級レベルの例題を使って、 実際の思考プロセスを体感していきましょう。
🟢 例題①:基本の「AはBより前」タイプ
問題:
3人(A・B・C)が横一列に並んでいます。
次の条件のもとで、並び順を答えましょう。
- ① AはBより前に並ぶ。
- ② CはAより後ろにいる。
💬 解き方のポイント:
条件①「A→B」、条件②「A→C」
よって順序は A → B,C(Aが最初)
解答: Aが1番目、BとCはAの後。
| 順番 | 人 |
|---|---|
| 1 | A |
| 2 | B or C |
| 3 | C or B |
🟡 例題②:「○番目」「間に何人いる」タイプ
問題:
5人(A〜E)が1列に並んでいます。
次の条件のとき、中央にいる人を求めましょう。
- ① Aは左から2番目。
- ② BはAの右隣。
- ③ Dは一番右。
💬 図で整理:
左から [_][A][B][_][D]
→ 残るCとEを空欄に入れると、中央はB!
答え: Bが中央に位置します。
🔵 例題③:時間・日付が関わるタイプ
問題:
3人(A・B・C)が順番に試験を受けます。
次の条件のもとで、試験順を求めなさい。
- ① BはCより先に受けた。
- ② AはBの後に受けた。
💬 思考の流れ:
条件①:B→C、条件②:B→A
→ B → A → C の順で確定。
答え: 1番目=B、2番目=A、3番目=C
| 順番 | 受験者 |
|---|---|
| 1 | B |
| 2 | A |
| 3 | C |
✨ まとめ:
順序関係は、「条件を図で整理」+「矢印でつなぐ」のが鉄則。
難しい文章でも、図にしてしまえば一瞬で関係が見えてきます。
次章では、合格者が使うスピード解法テクニックを紹介します。 「時間が足りない!」という受験生は必見です。
合格者が使うスピード解法テクニック
順序関係の問題は、理解するだけでなく「早く正確に」解けることが重要です。 ここでは、実際に多くの合格者が使っている“スピード解法”を3つ紹介します。
⚡ テクニック①:条件文を「矢印」に変換せよ!
文章をそのまま読んで頭の中で整理するのはNG。 「AはBより前にいる」→ A → B と矢印に変換して、紙に書き出しましょう。
- 矢印を使うと「誰がどこにいるか」が一目でわかる
- 複数条件を重ねても矛盾を発見しやすい
- 迷ったときは“逆矢印”を描いて確認!
💬 合格者の声:
「矢印にするだけで頭が整理される。
文章で混乱する時間がゼロになりました!」
⏱ テクニック②:表を書きすぎない!
丁寧に全部書こうとすると、時間がかかります。 重要なのは「変化する部分」だけをメモすること。
- 位置が動く人・条件に関わる人だけ記入
- 決定部分には○、未確定部分には△をつける
- 最終的に全体像を1行でまとめる
💬 ワンポイント:
すべて書く=混乱のもと。
“シンプルな表”がスピードアップの鍵です!
🧠 テクニック③:「除外思考」で逆から考える
条件が多くて整理しにくいときは、 あえて「ありえない順番を消していく」アプローチが有効です。
- 一番前に来られない人を消す
- 次に2番目に来られない人を消す
- 最後に残った人が正解!
💬 例:
「AはBより前」「CはAの後」なら、
Aが先頭の可能性が高い → 他を除外すればすぐ確定!
📈 テクニック④:迷ったら“仮置き”で検証する
複雑な問題では、まず仮に配置してみるのが効果的です。
- 「Aを1番に置く」と仮定して条件を当てはめる
- 矛盾したら次のパターンに切り替える
💬 ポイント:
迷う時間よりも、“手を動かして試す”ほうが速い。
スピード勝負の試験では特に有効!
次章では、これらのテクニックをさらに伸ばすために、 効率的な学習法とおすすめの勉強ツールを紹介します。
効率的な学習法とおすすめ教材
✅ 3ステップ学習法(毎日15〜20分)
- インプット: 例題1問を読み、矢印・線図・表で条件を書き出す(5分)
- アウトプット: タイマー3〜4分で解答→理由を1行でメモ(8〜10分)
- 復習: 間違いの原因を「見落とし/図の不足/時間配分」に分類(3〜5分)
※「毎日少量×継続」が最短。週末にまとめ解き(5〜10問)で仕上げ。
🧭 自作ノートの作り方(スコアが伸びるコツ)
- 見開き左に問題・条件の図、右に解法手順と気づき
- ミスはタグ化(#読み落とし #矢印逆 #表不足)して再発防止
- 頻出型は「型カード」(例:A→B、隣接、間に◯人)としてまとめる
📱 スタディングで順序関係を強化する
スタディング公務員講座は、動画×演習×復習設計で判断推理を効率学習。 スマホで線図の描き方や時短テクをサクッとインプット→通勤時間に演習で定着できます。
- 講義で「矢印・表・再配置」の思考手順を標準化
- 演習モードで3〜4分の時短トレ
- 弱点可視化で「順序関係」だけ集中特訓
関連記事:スタディング体験レビューはこちら
💬 ミニTIP:
「最初の3秒で図に落とす」→「確定→矛盾→再配置」
この型だけで、順序関係は安定して得点源になります。
次章では、ここまでの内容を振り返り、合格へ直結する学習ループをまとめます。
まとめ:順序関係を制す者が判断推理を制す!
ここまで、順序関係の基礎・例題・スピード解法・学習法を学んできました。 最後に、合格に直結する要点を一気に整理しましょう。
🧩 本記事の要点まとめ
- 順序関係=情報整理力を問う問題。矢印と表で可視化が基本。
- 解法の流れ:確定 → 矛盾チェック → 再配置。
- 時間短縮の鍵:「矢印化」「仮置き」「除外思考」。
- 練習法:毎日15分、少量×継続で感覚を定着。
💬 合格者の共通点:
「順序関係が得意になってから、他の判断推理も一気に伸びた!」
→ 思考整理スキルが全分野に波及する、まさに“伸びしろ分野”です。
📈 次にやるべきこと
独学でも理解はできますが、 本番レベルのスピードと精度を身につけるにはプロの解説+演習量が必要です。
そこでおすすめなのが、スタディング公務員講座。
- スマホでスキマ時間に学習できる
- 順序関係を含む判断推理を動画で体系的に理解
- AI復習機能で弱点を自動補強
順序関係は、最初は苦手でも、考え方が身につけば一気に得点源になります。 今日から少しずつ練習を重ねて、あなたも「判断推理マスター」を目指しましょう!
💬 次に読む記事:
【判断推理】他の頻出テーマまとめはこちら▶